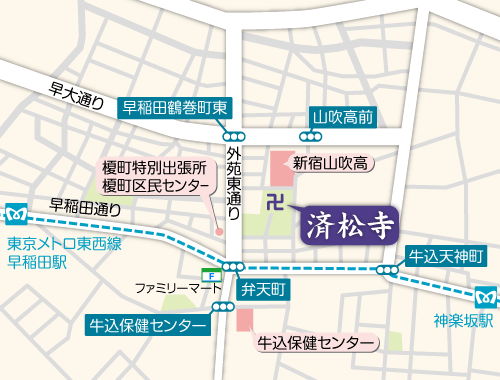芳賀善次郎氏の『新宿の散歩道』(三交社、1972年)「牛込地域 55.馬ぐそを拾う仙人」では……
| 馬ぐそを拾う仙人 (榎町) 済松寺のあるあたり一帯は榎町であるが、これは榎の大樹があったので名づけられた町名である。その榎の大樹はどの辺にあったか分らないが、鎌倉海道すじにあったものだという(戸塚28参照)。 この榎の根元には洞穴ができていて、大人一人が自由に出入りできる大きさだった。貞享の頃(1684-87)、この洞穴に、「馬ぐそ仙人」と呼ばれる奇人が住みついた。 身にボロをまとい、杖一本とかご二つをもって、早朝から往来に出て牛や馬の糞を拾い集め、かごいっぱいたまると、四谷あたりへ行って売るのであった。そして米を買い腰につるしてある古なべに入れ、道ばたに落ちている枯木などを拾い集め、煮炊きをして食べる生活をしていた。 天気のよい日には、榎の洞穴の前に立って、子どもたちを集め、古歌を書いた紙片などをやったりするが、大人とは一言も話をしない隠遁の奇人、変人であった。 〔参考〕御府内備考 南向茶話追考 新宿と伝説 |
済松寺 さいしょうじ。新宿区榎町にある臨済宗妙心寺派の寺。三代将軍徳川家光が帰依し、牛込村大橋立慶(龍慶)の屋敷を寺地にするよう命じ、1646年に創建。
榎 えのき。夏に日陰を作る樹。江戸時代には街道の一里塚に植えられた。
鎌倉海道 鎌倉街道。かまくらかいどう。鎌倉幕府から諸国に通じる主要道路。
隠遁 いんとん。俗世間を逃れて隠れ住むこと
最初に「南向茶話追考」を読んでみます。
| 牛込榎町 古老云、昔は大木の榎有。依て号する由、是木は古来鎌倉海道の由申伝 |
では「御府内備考」を見てみます。
| 一或老翁の記をみしに正徳元年の條云江戸に三十年前 今推考するに貞享のころか 一谷郷尾張殿の邸のうしろに大なる榎木あり ことに年ふりし木にてその根の所ほらのことくなり 人ありてその内に住すること数年なり 身に襤褸をきて拐一ツ籃ニツをもてり 日出るころおき出て路頭に新し牛馬の糞を拾ふ 籃にみつるころ四ツ谷といふ所の民家または官家の小吏のもとにいたりて 牛通馬矢をうれり その価ひわつかに八錢にすきず その帰るさに米あきなふ所にて一しゃくの米にかへて道傍に落たる草木の枝なとひろひとり 四谷大榎町といふ所の石橋ある所に至りて腰より鑵子をとり出して水をこひ火を求てかの米を煮て鑵子なから口に入水をのみこゝろよけにうちゑみて かの樹下の洞に帰りいり 空のとかなる時は洞の前にて出ひとりごこし わらべなとし来り ともなふ大人とは一言をまじへす 童子にもの書ておくらんといるほとに紙筆なと具すれは 手うるはしくふるきふみの文哉 古歌なとかけり 今の世村閭の挙子とは同日の談にあらすかくてその所にて身まかりぬと 案に是榎町の大榎にしてかの隠者は瓢に儈の馬糞仙人なりと さもあるにや 以上江戸志 |
正徳元年 1711年
一谷郷 不明
ほら 洞。がけ・岩・大木などにできた、中のうつろな穴。
襤褸 ぼろ。使い古しの布。ぼろきれ。着古して破れた衣服。つぎだらけの衣服。
拐 かい。拐杖。杖。つえ。
籃 かご。竹で編んだかご。
牛通 牛の通じ。牛の大便
馬矢 ばし。馬糞。ばふん。
しゃく 勺。約18mL
鑵子 かんす。銅・真鍮などで作った湯沸かし。
うるはしく うつくしい。折り目正しく、きちょうめん
ふみ 文書。書物。手紙。書状。学問。特に漢学。漢詩
村閭 そんりょ。村の入口の門
挙子 擧子。きょし。中国の官吏登用試験である科挙に応ずる人
同日の談にあらず 同様に見なして談ずべきことでない。同じ扱いにはできない。
身まかる あの世へ行く。死ぬ。
瓢 ひさご。ひょうたん
僧 そう。仏道を修行する人の集団。「瓢に僧」の句はありませんでした。「新編江戸志」ではこの文章を「この隠者は瓢々傳言処の馬糞仙人なり」と変えています。「瓢々」は「考えや行動が世間ばなれしていて、つかまえどころのない様子」だそうです。「傳言」は「伝言」で、言い伝えること。
ボロを着て、牛馬の糞をお金に替える。しかし、一旦筆をとると、古い文章や古歌はすらすらと出てくる。いかにも統合失調症らしい感じです。