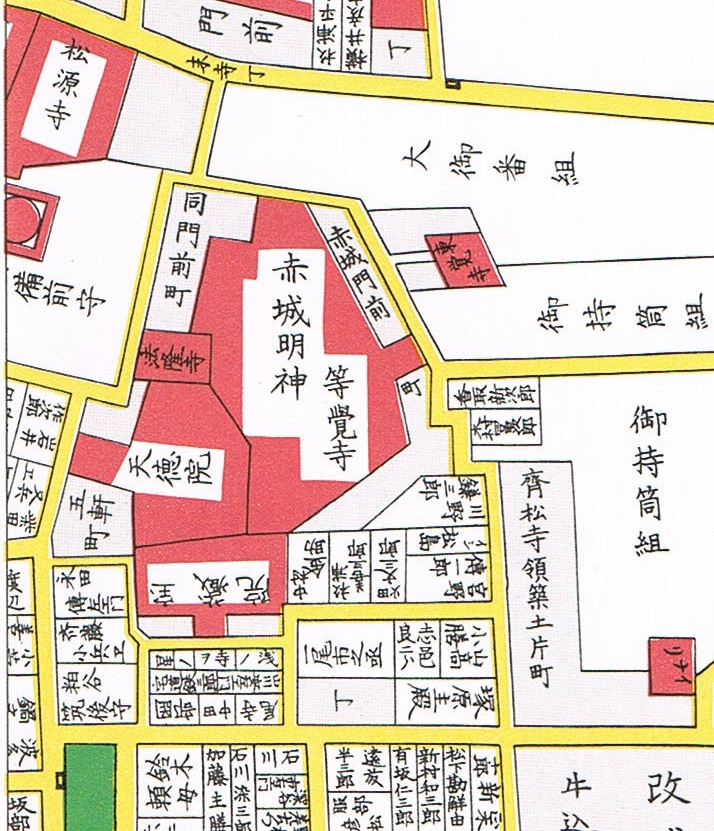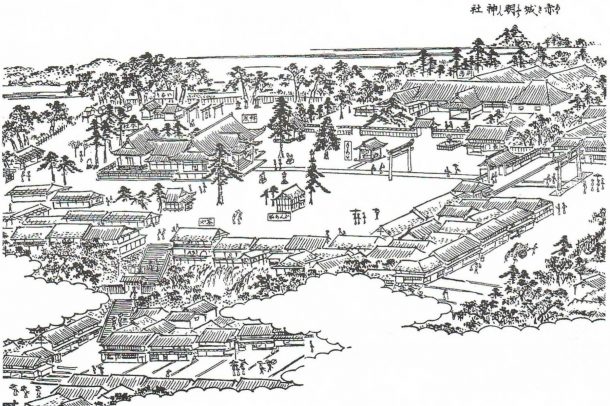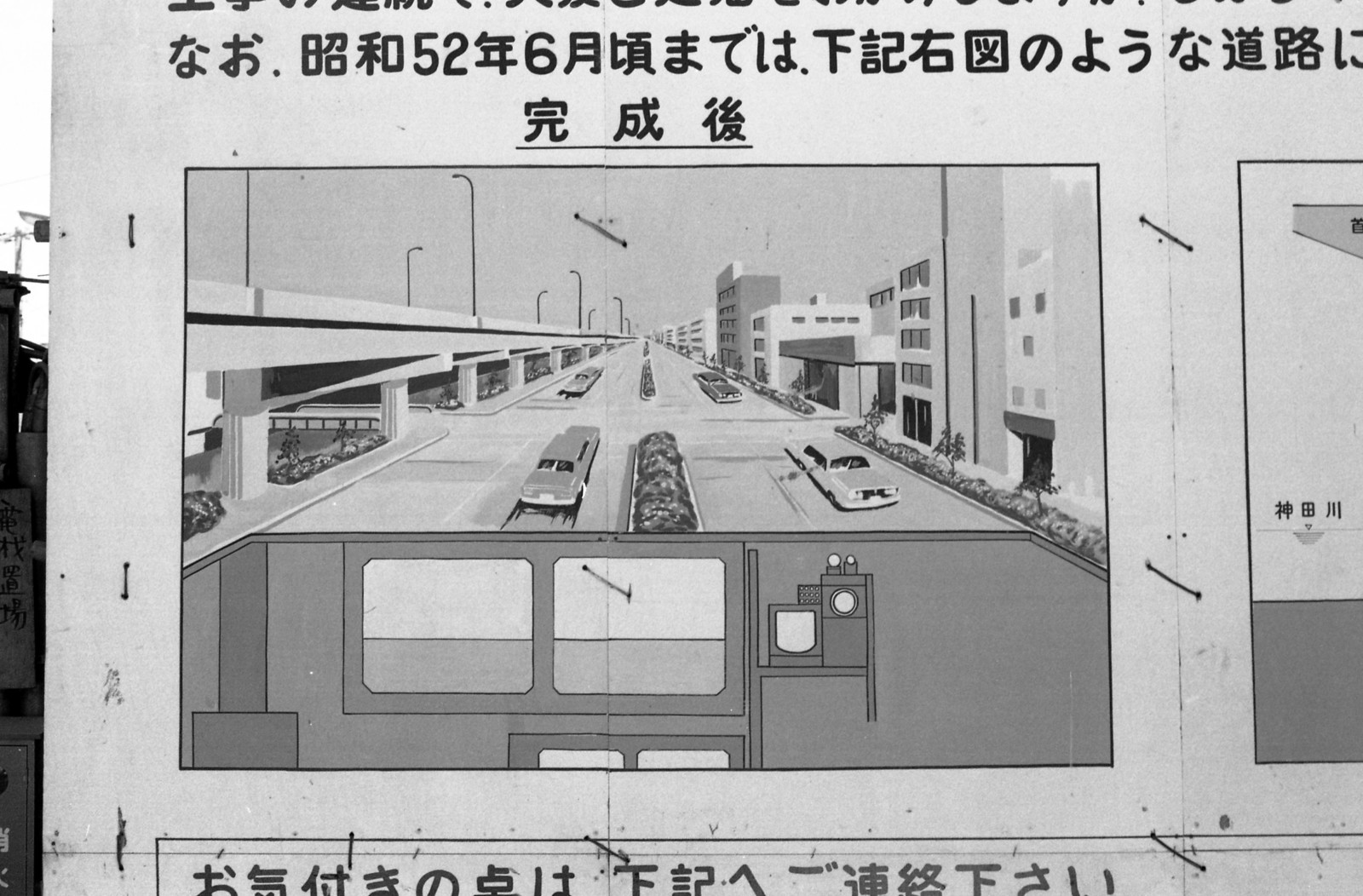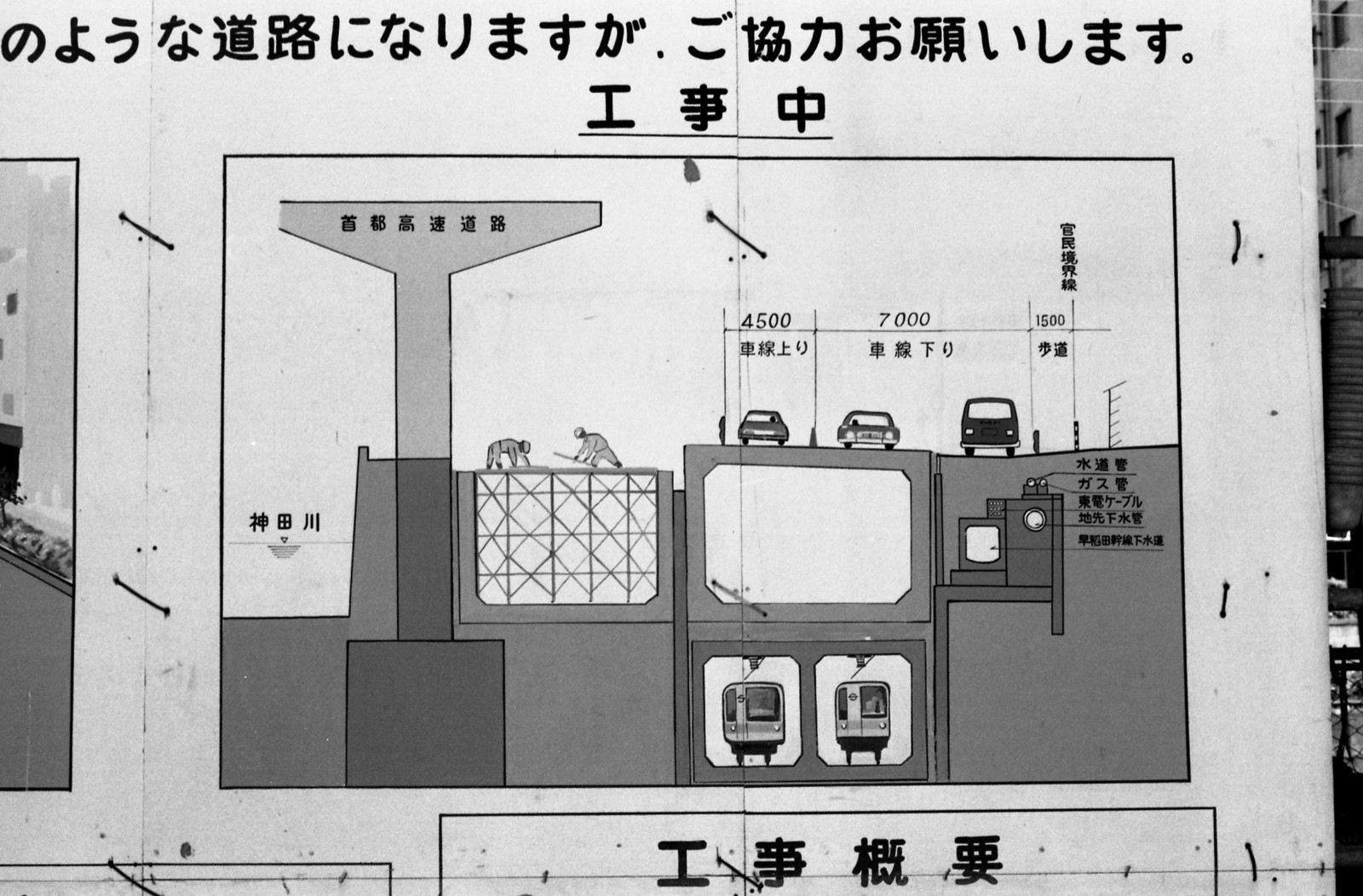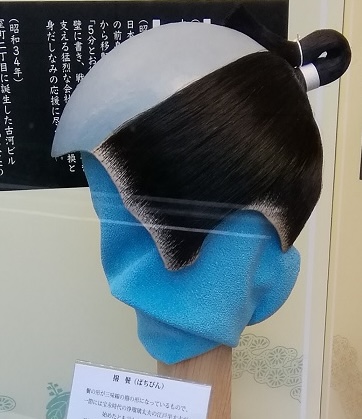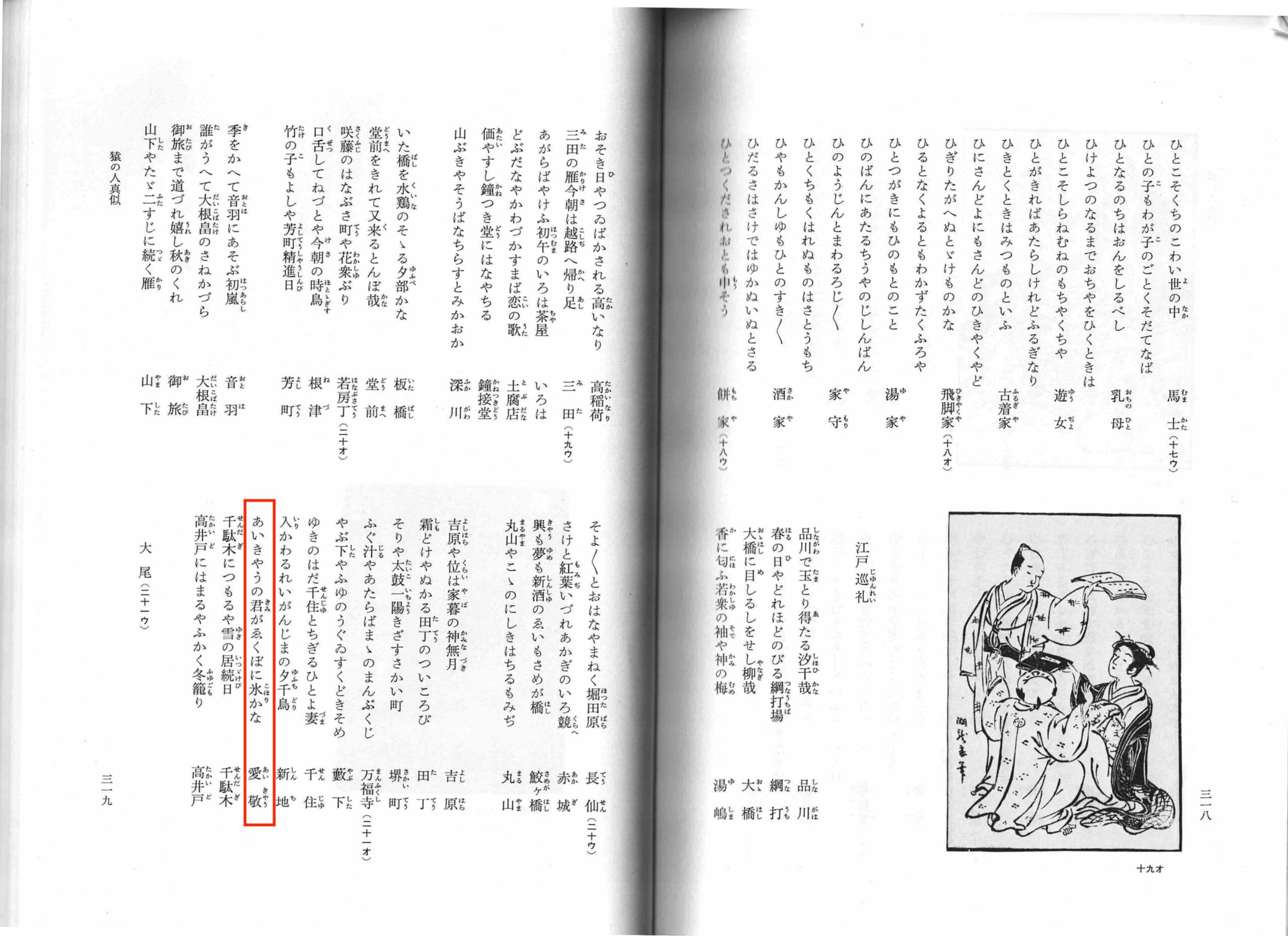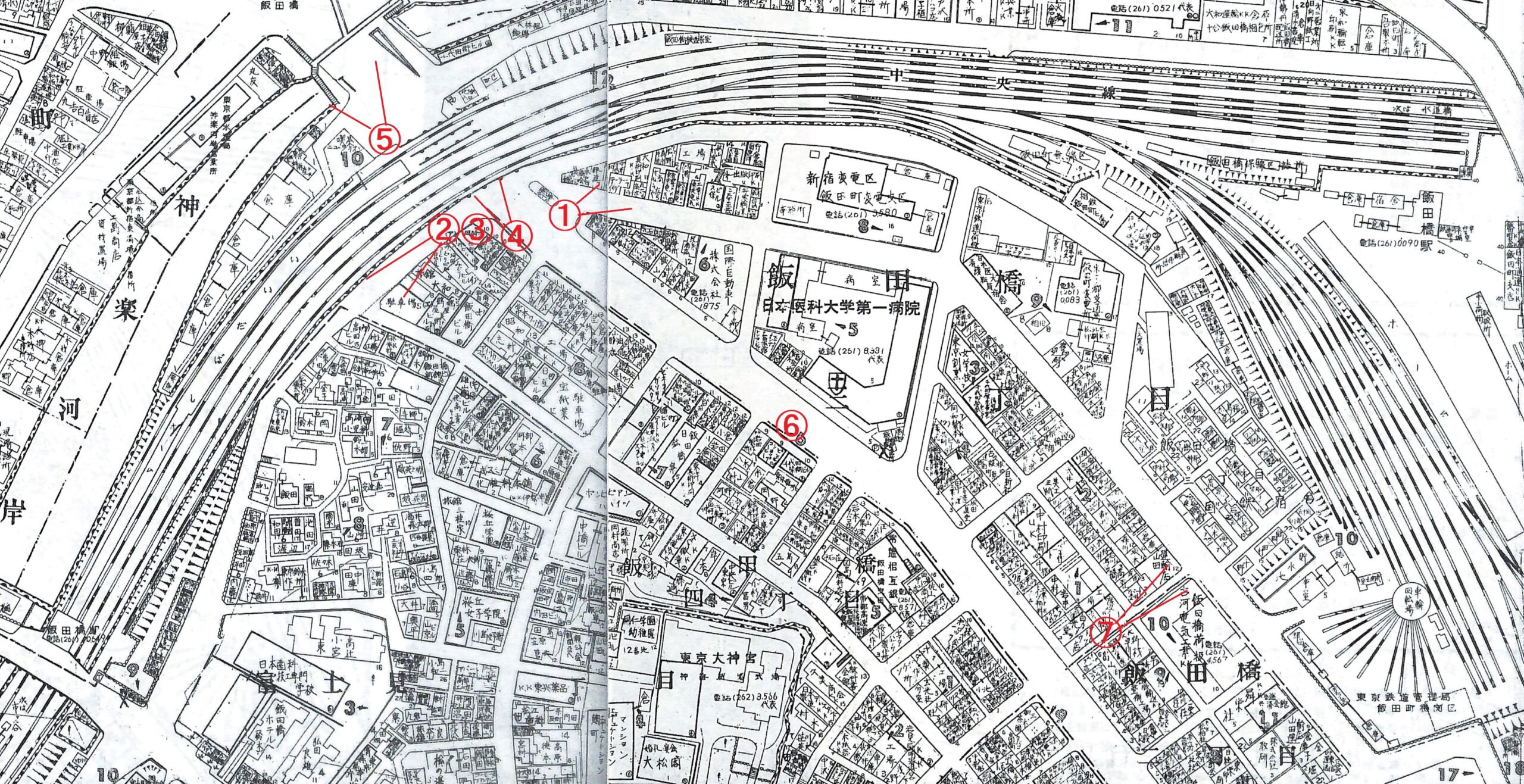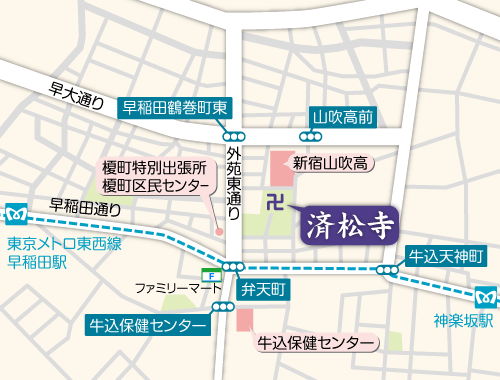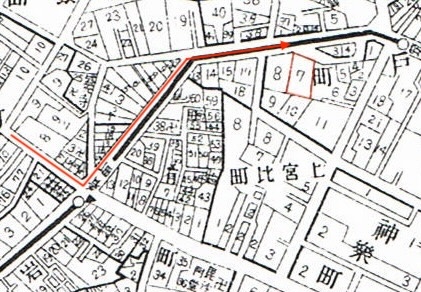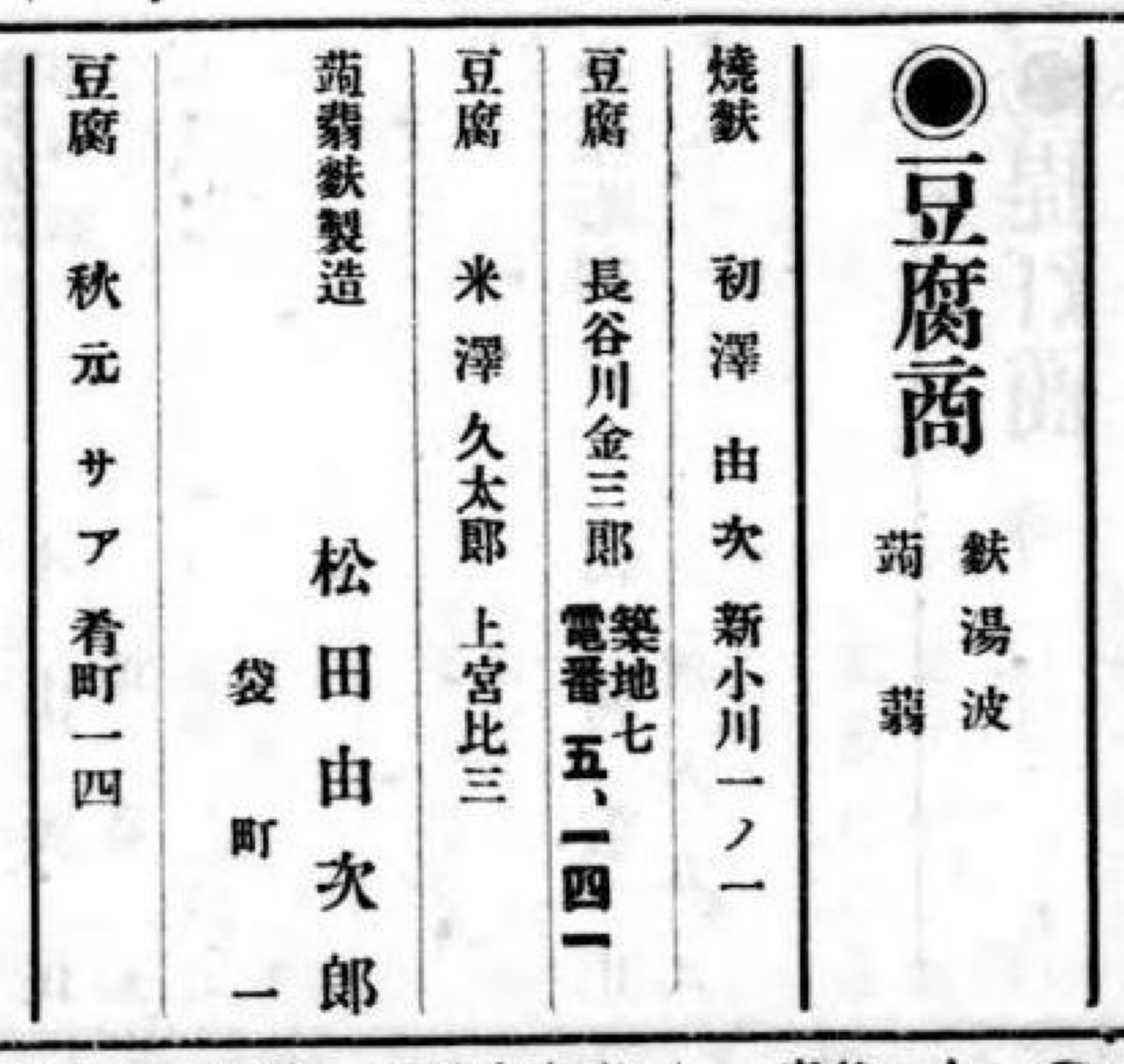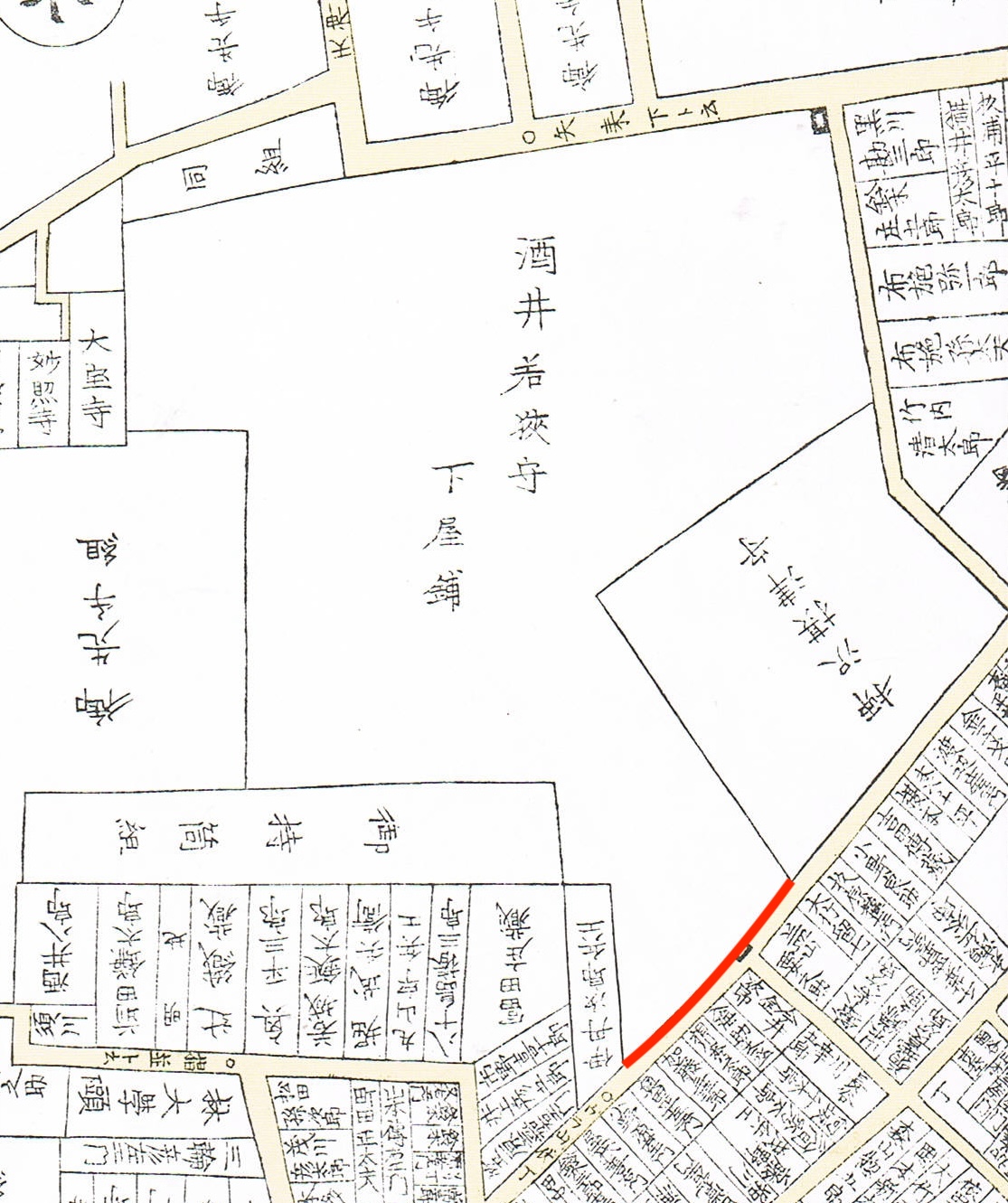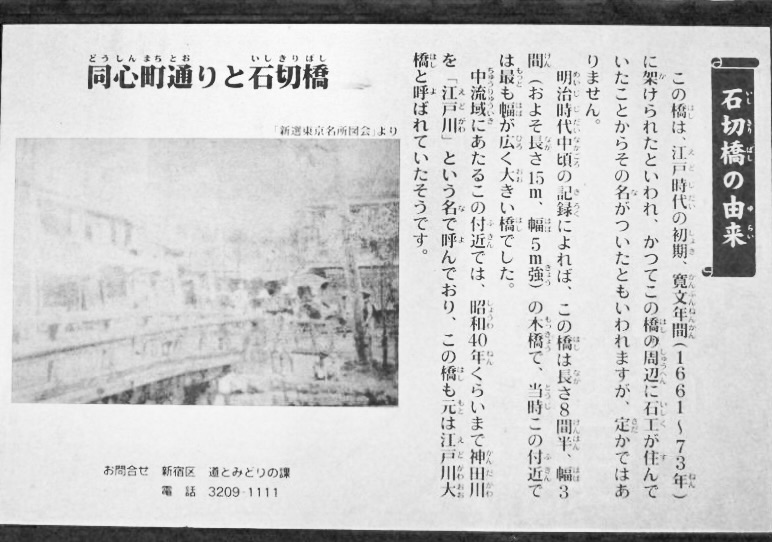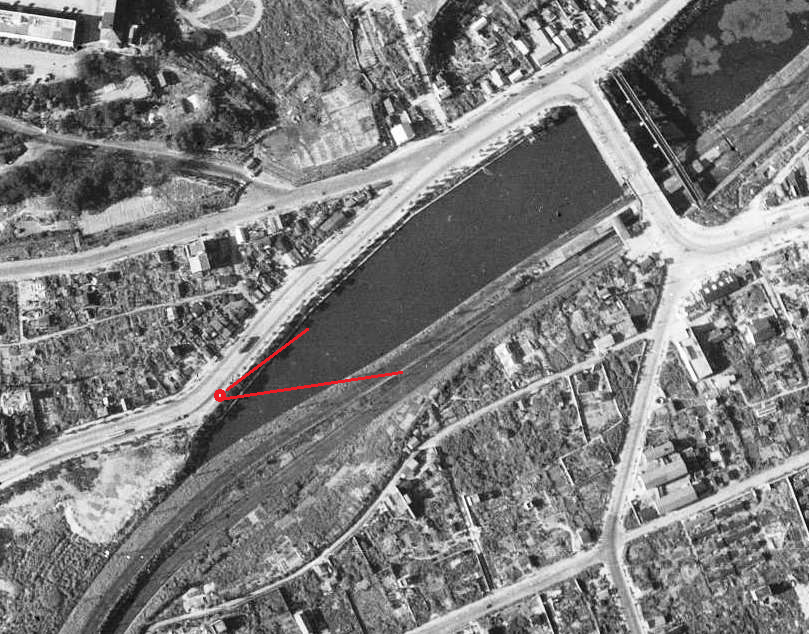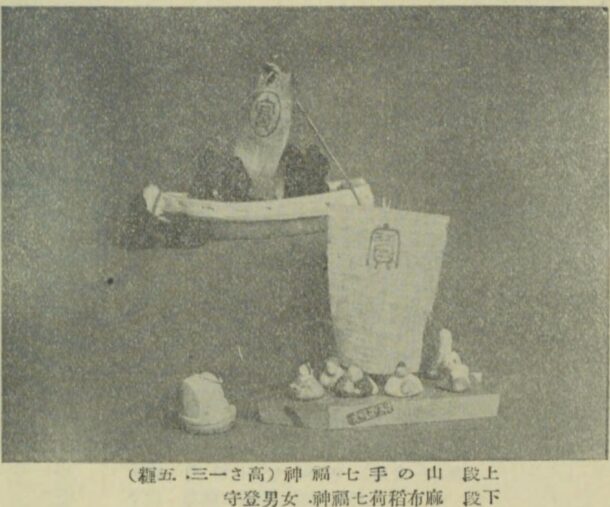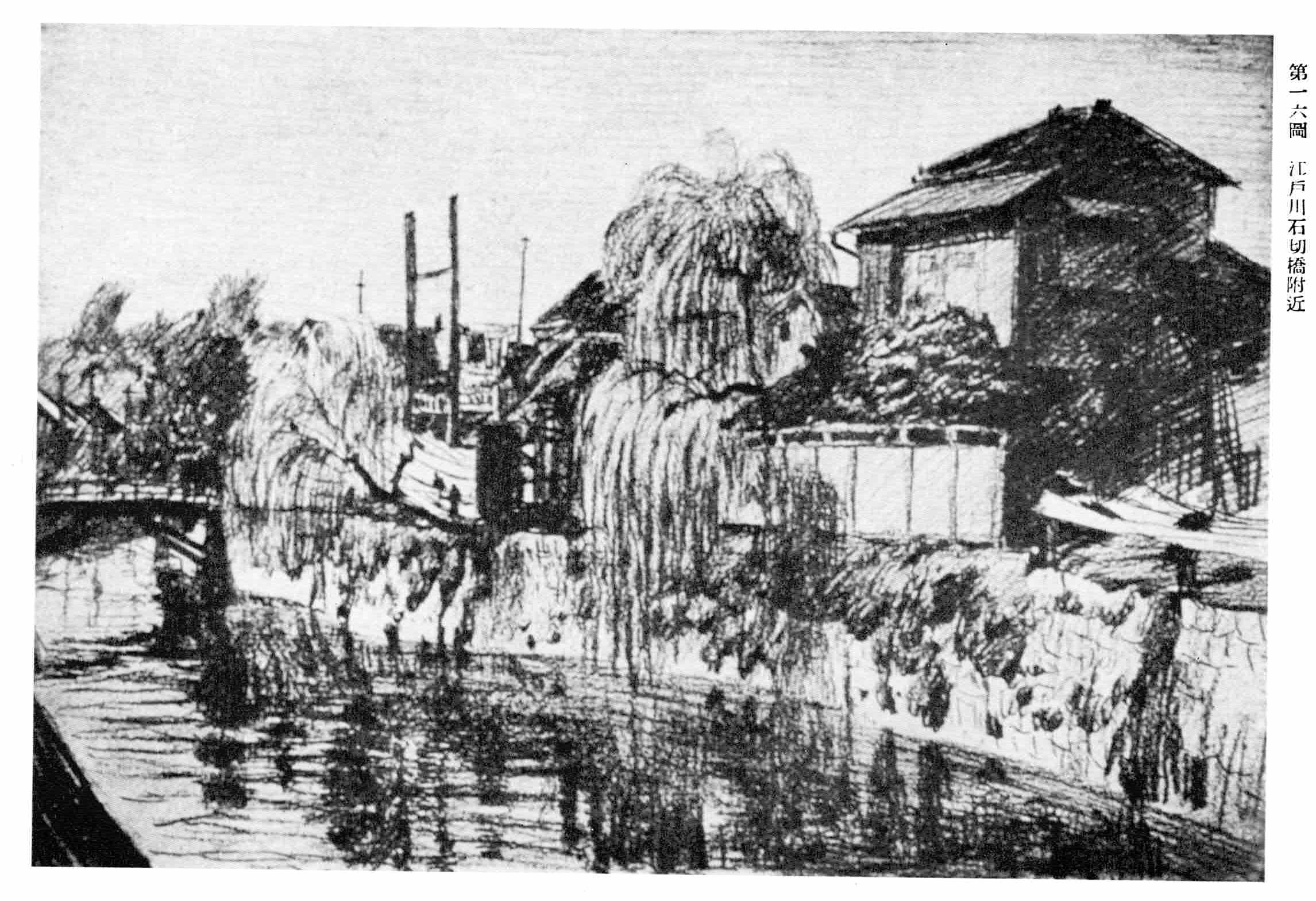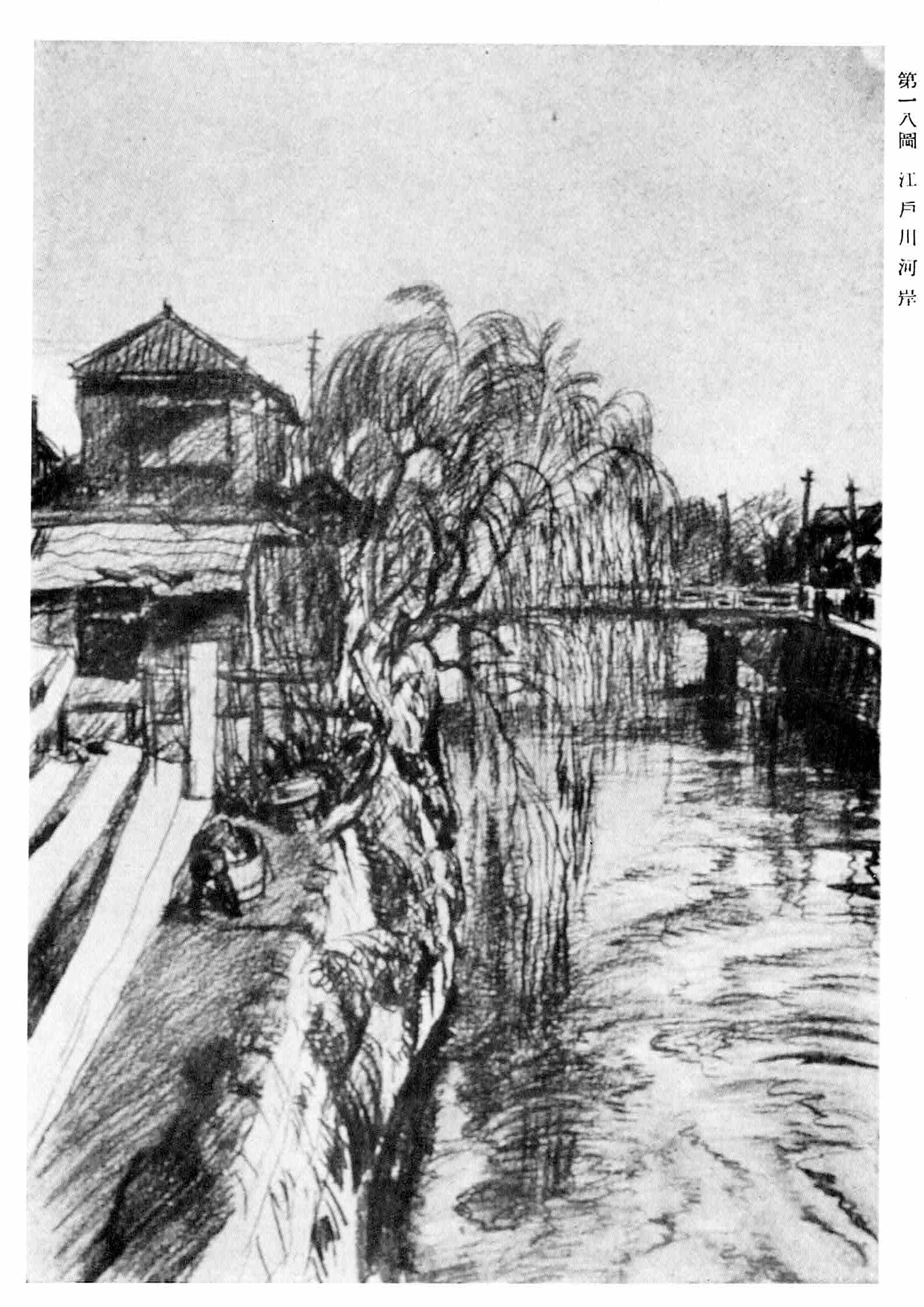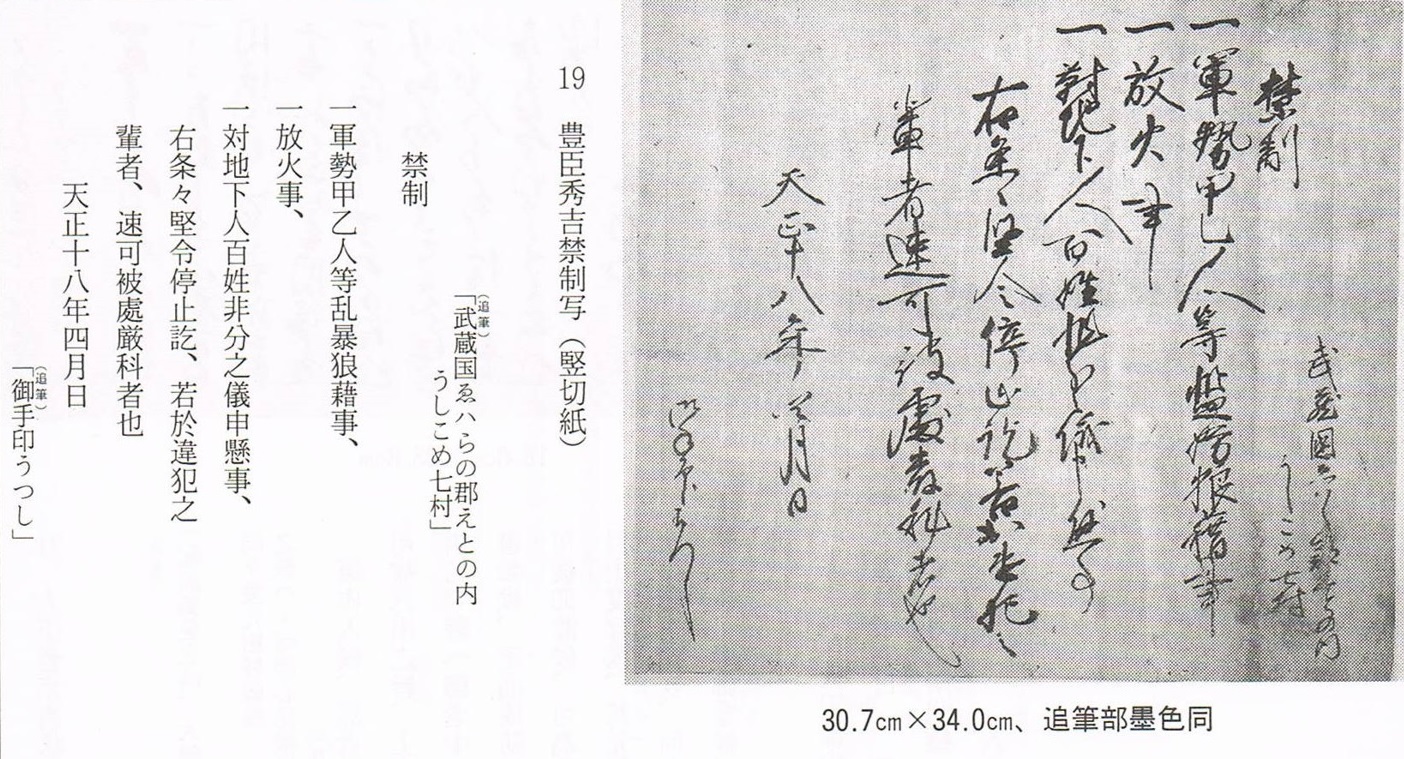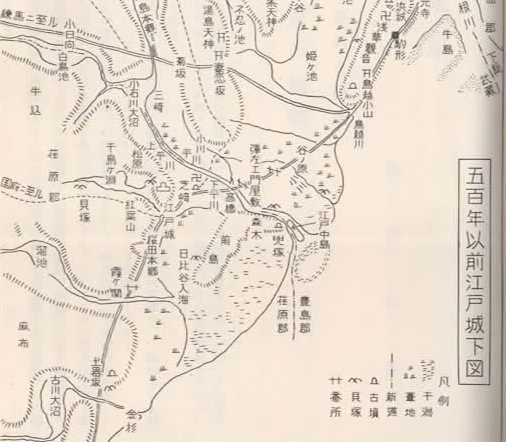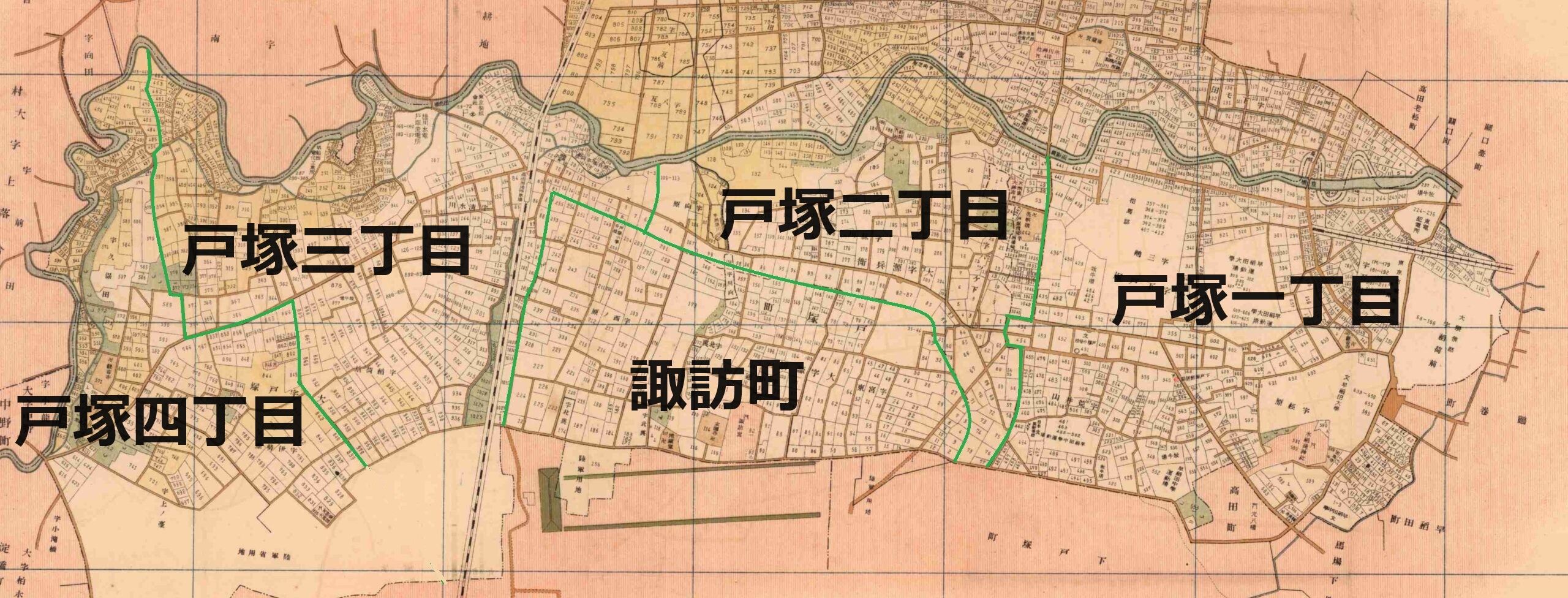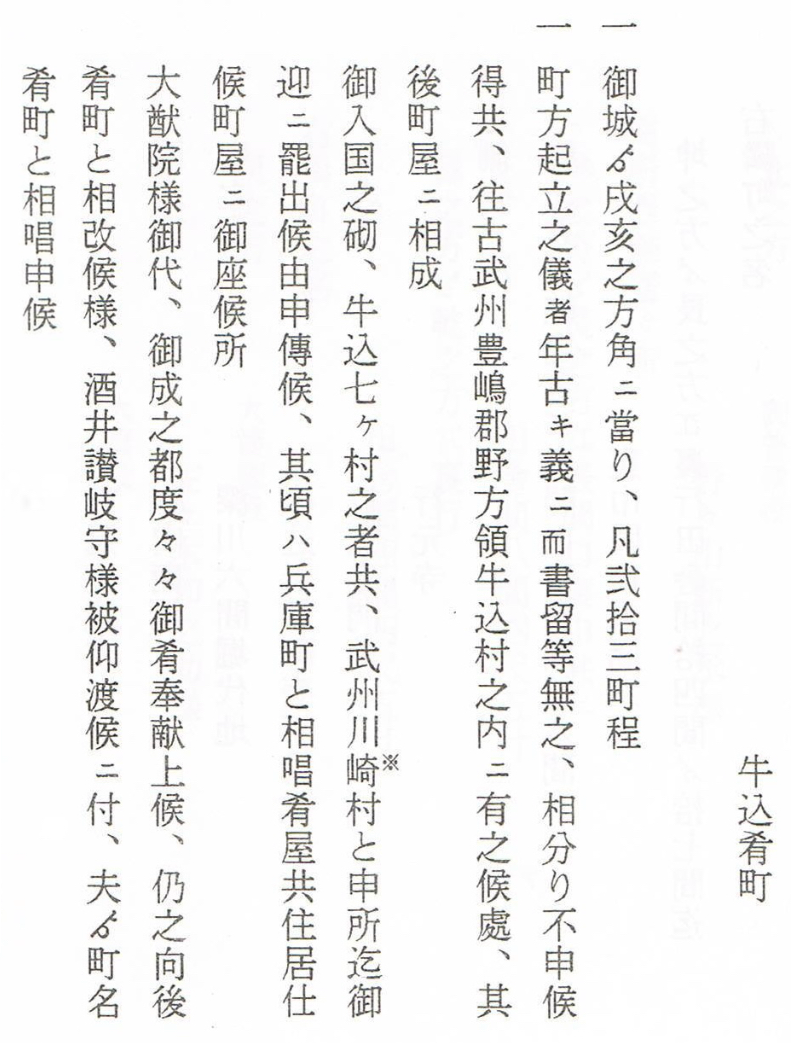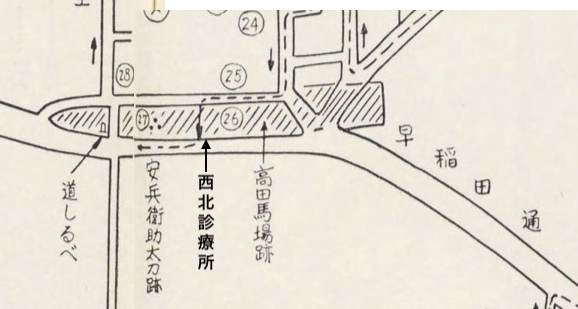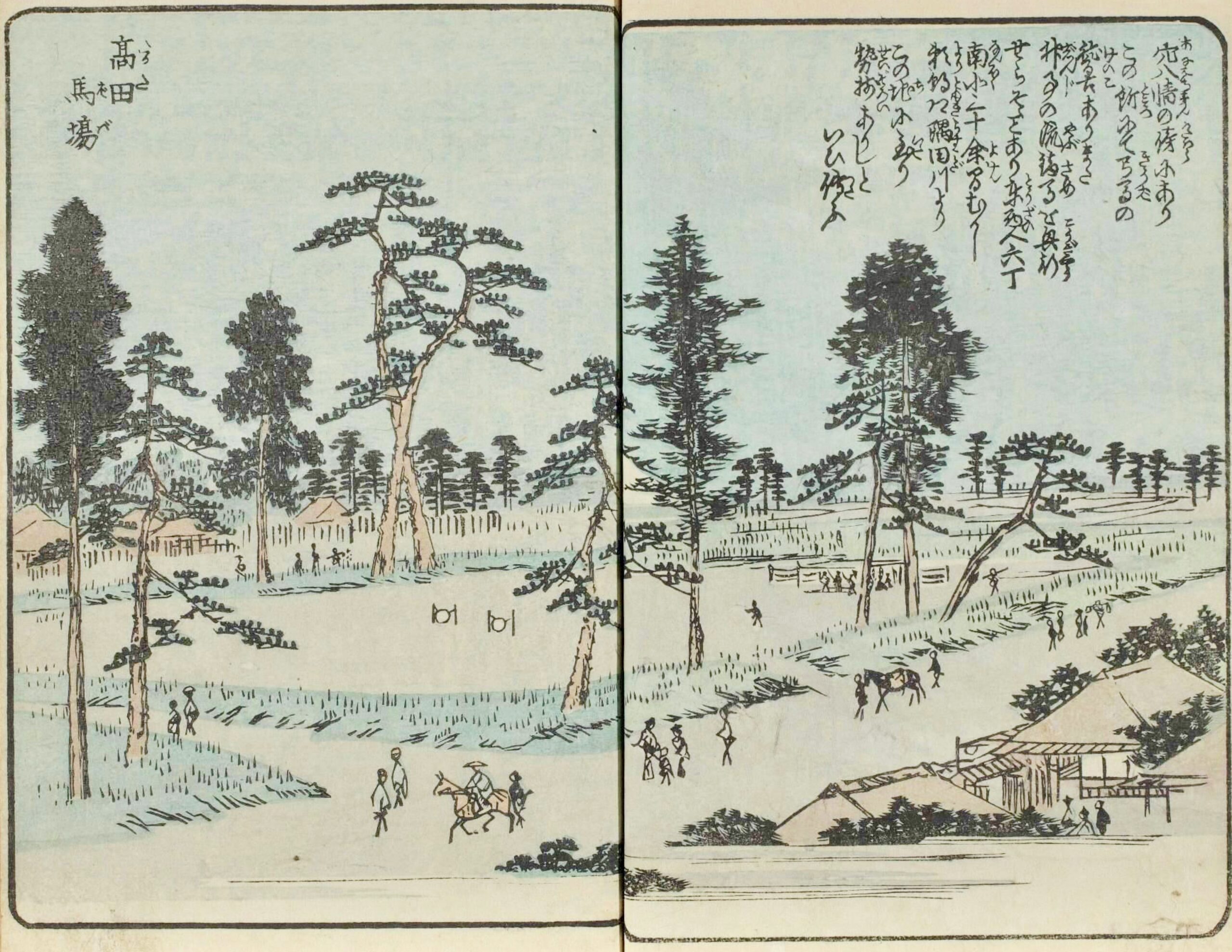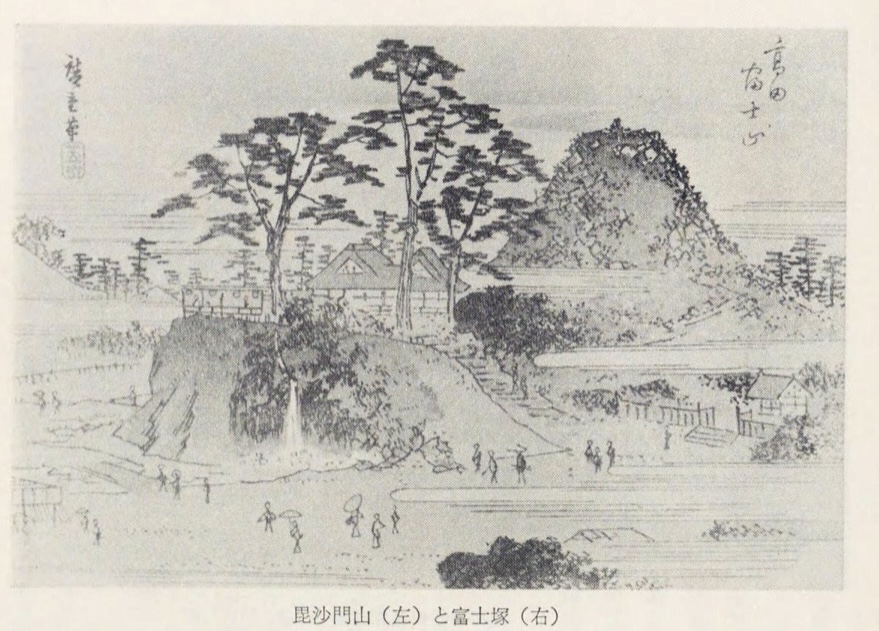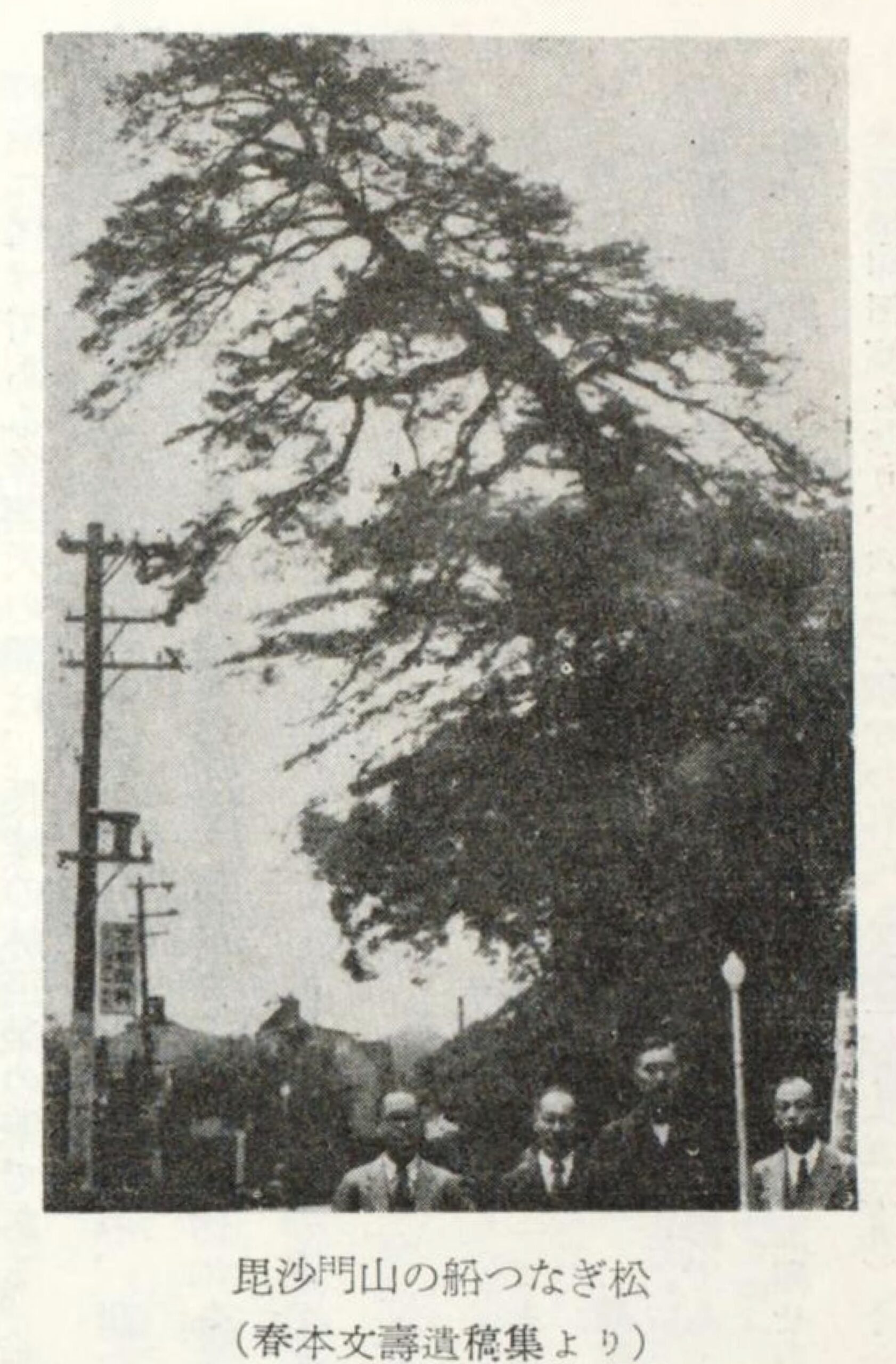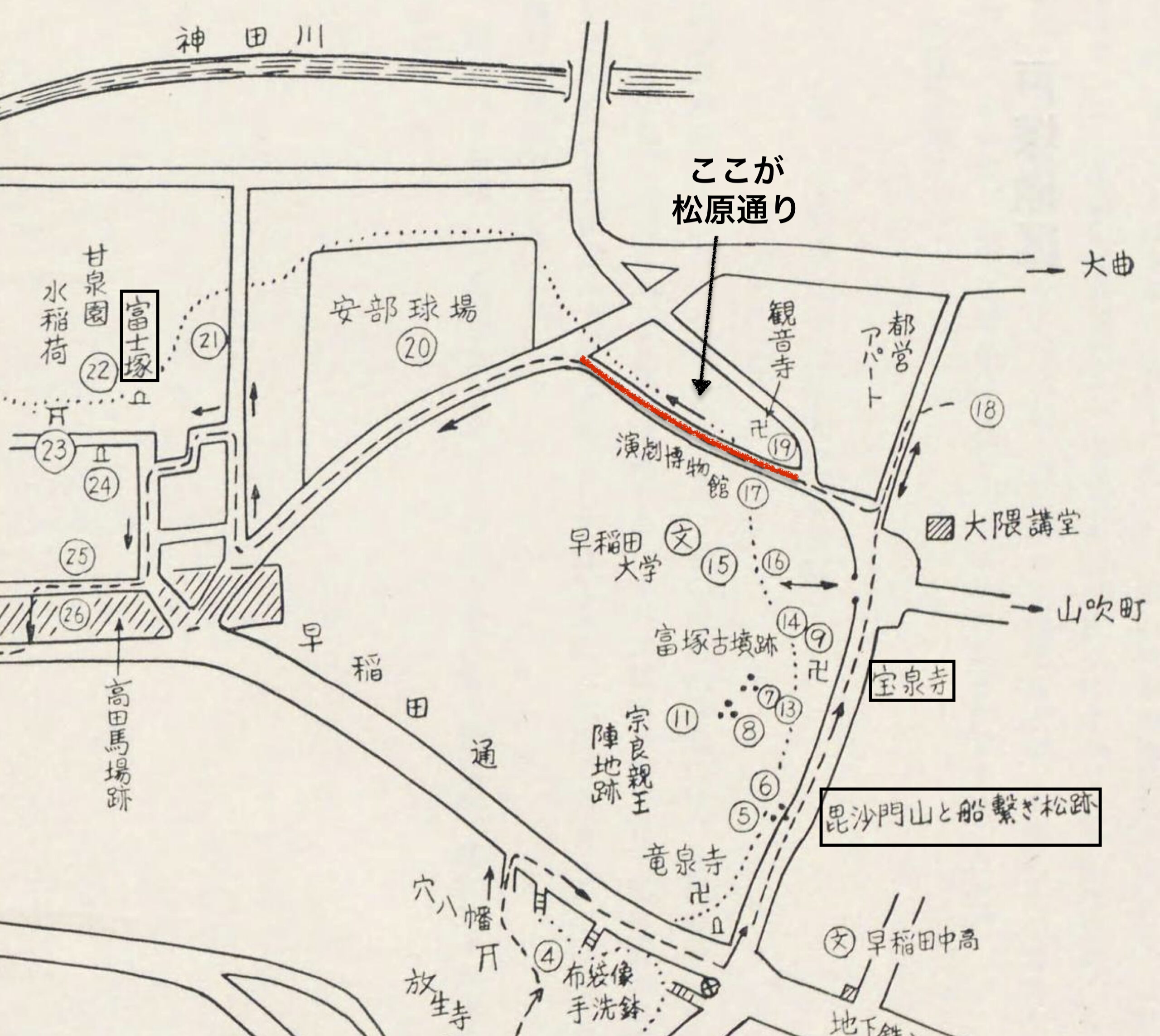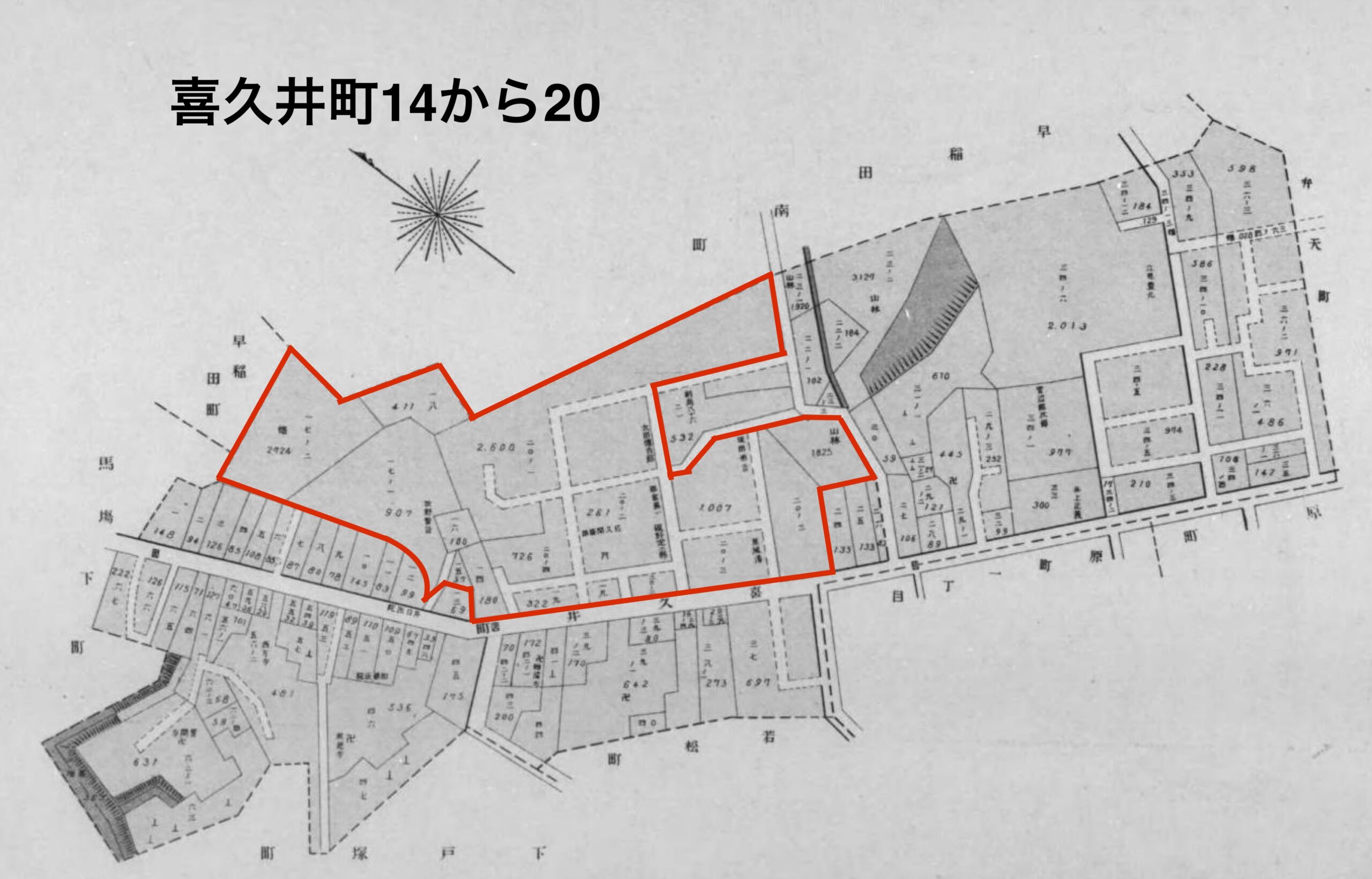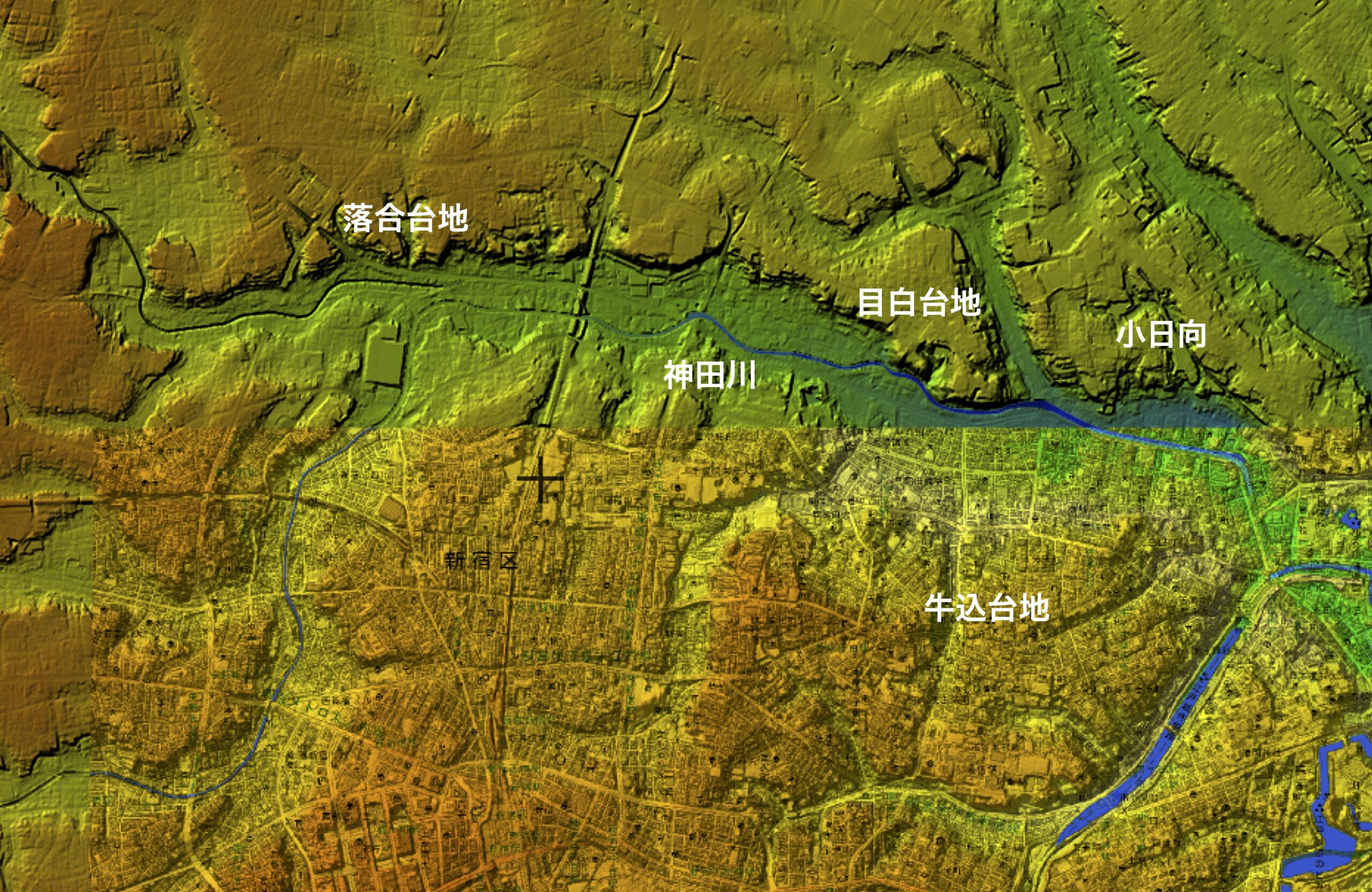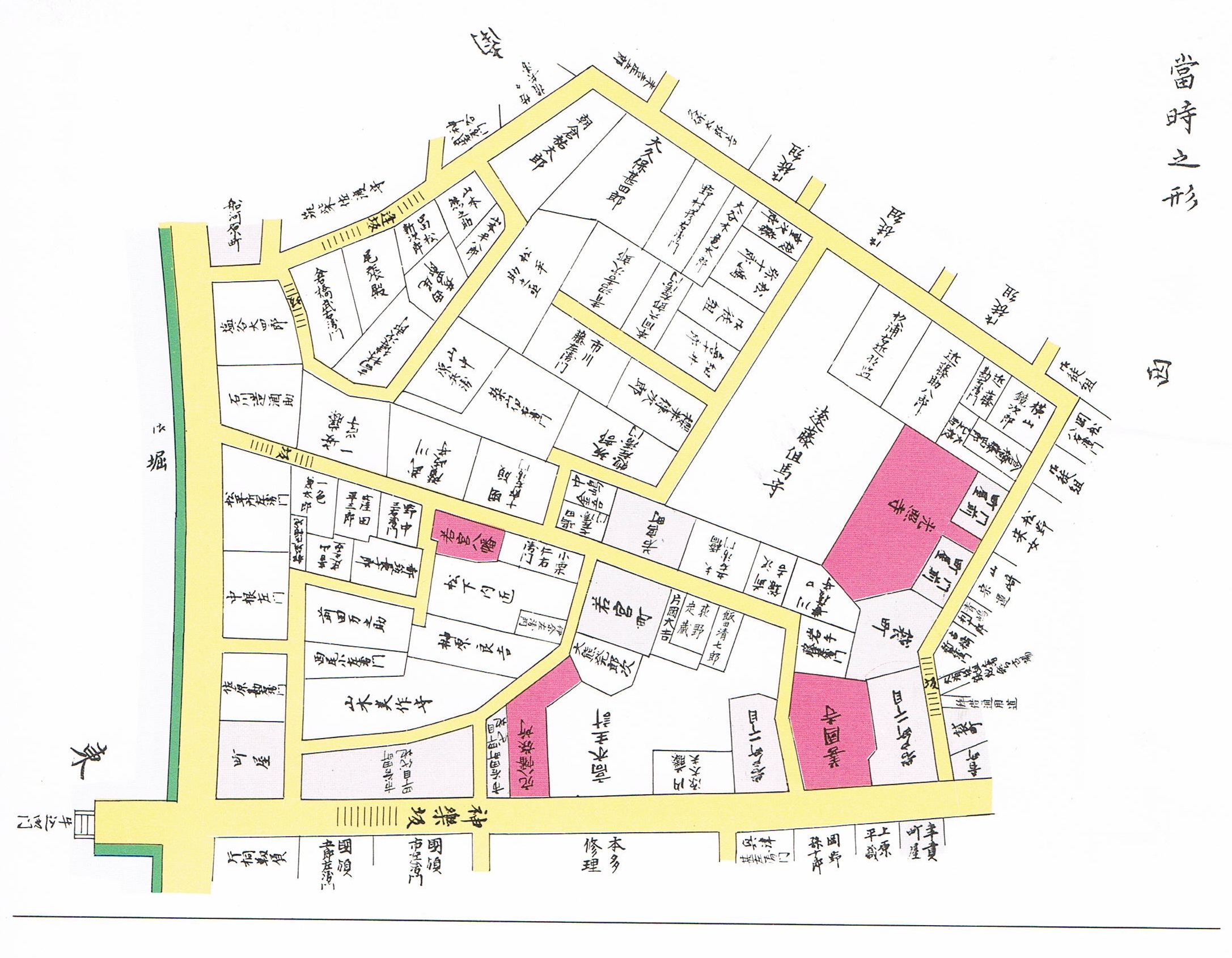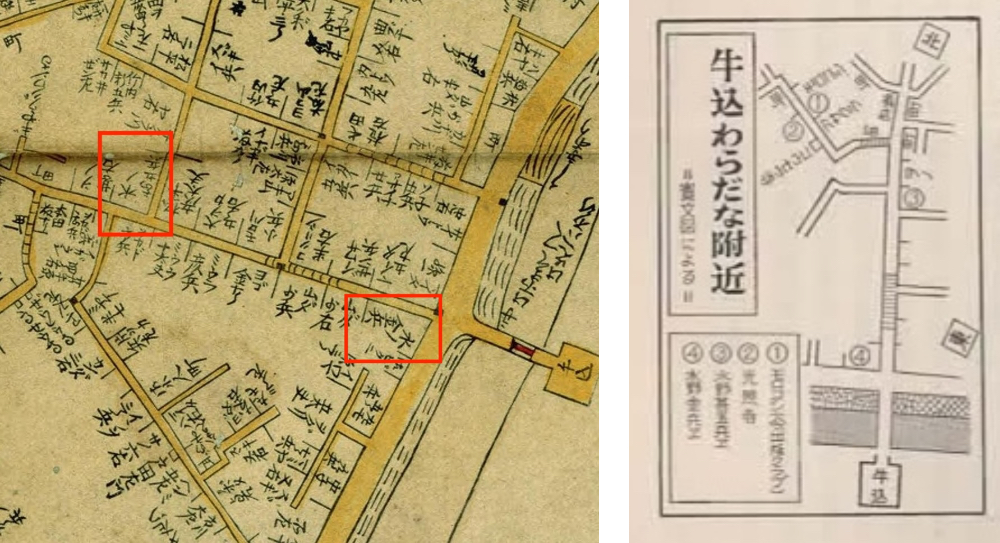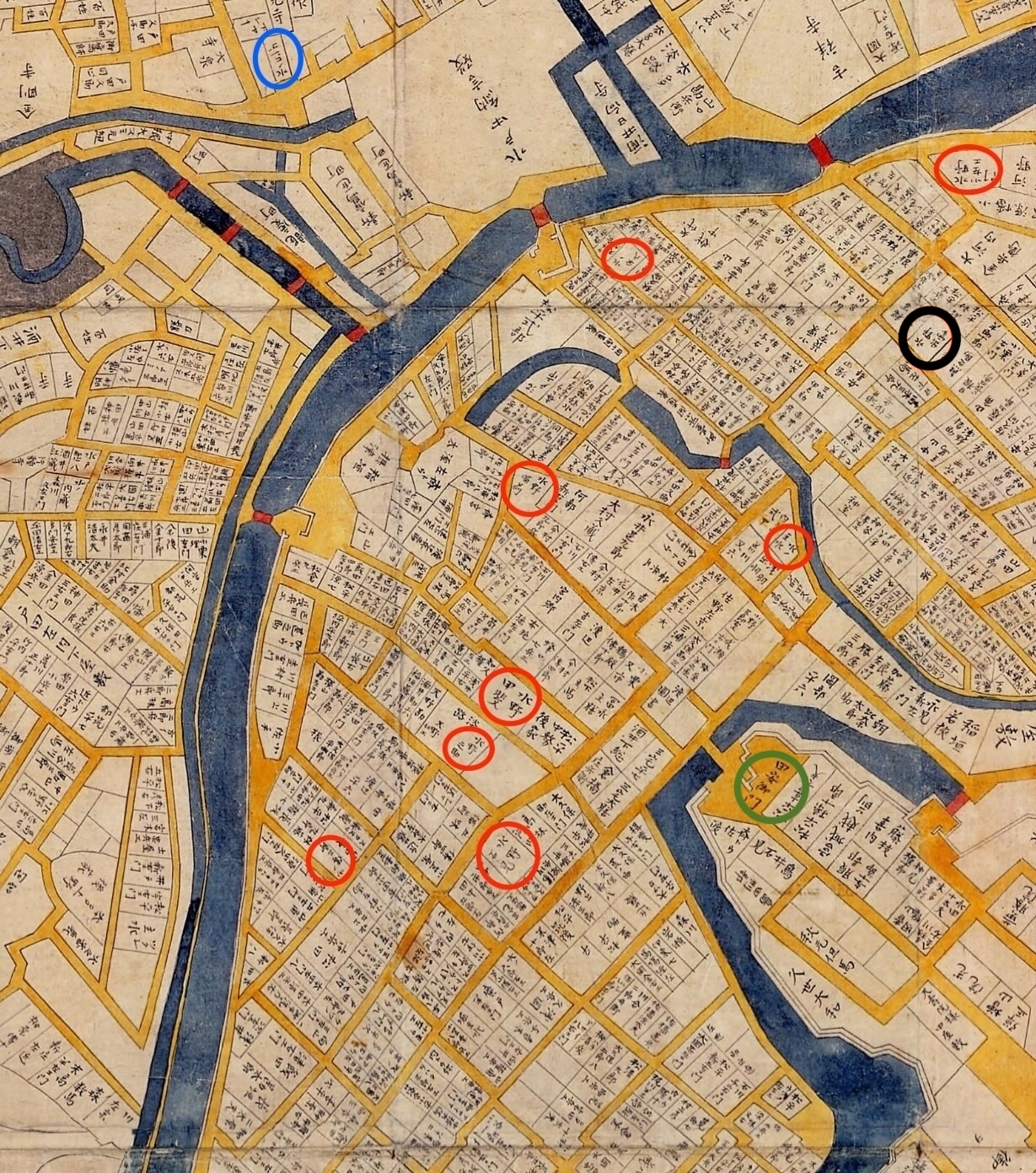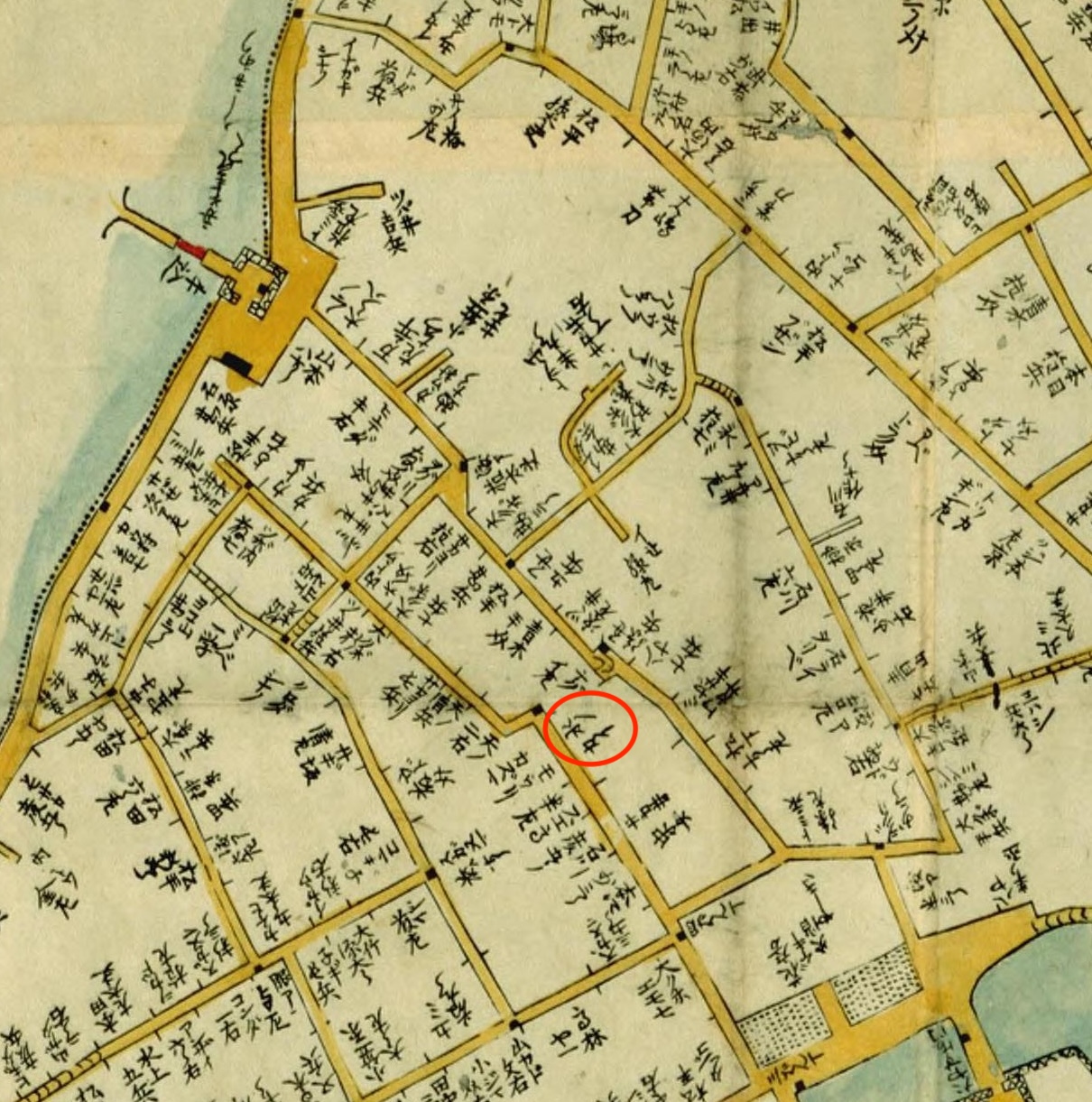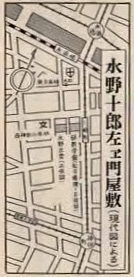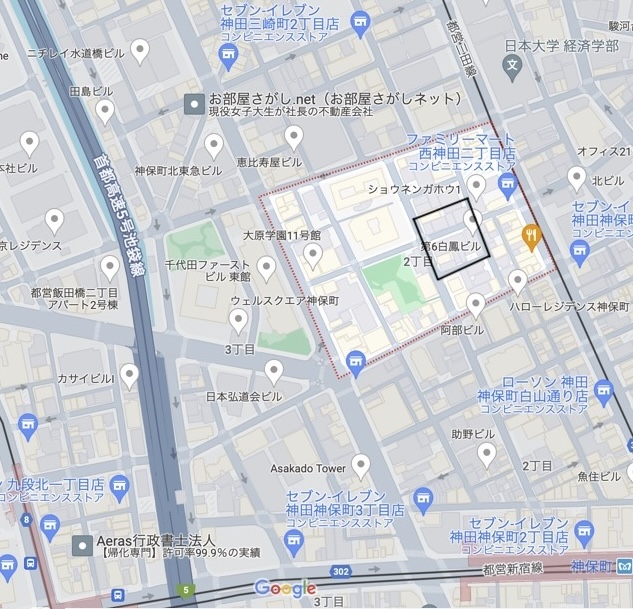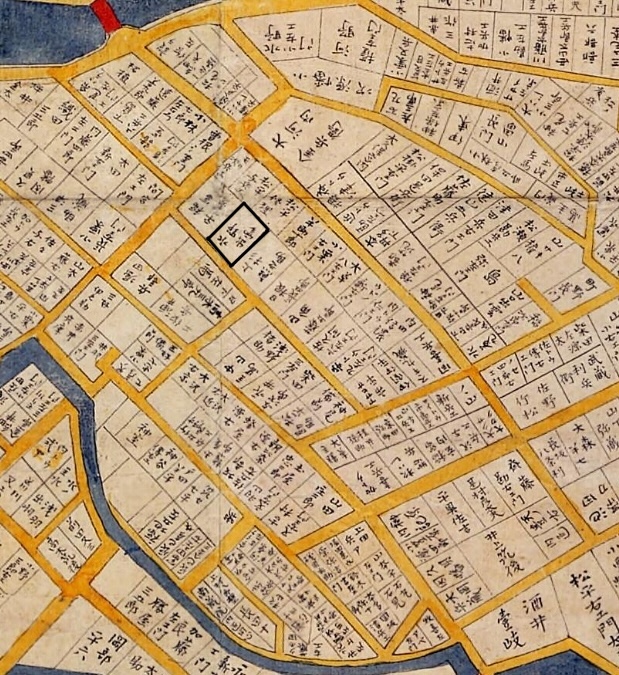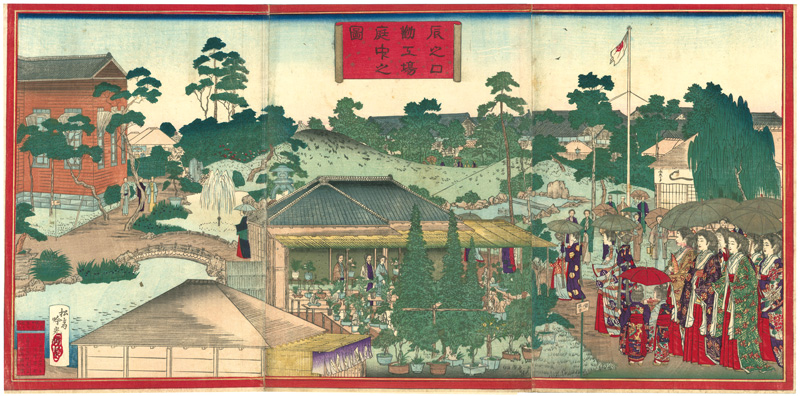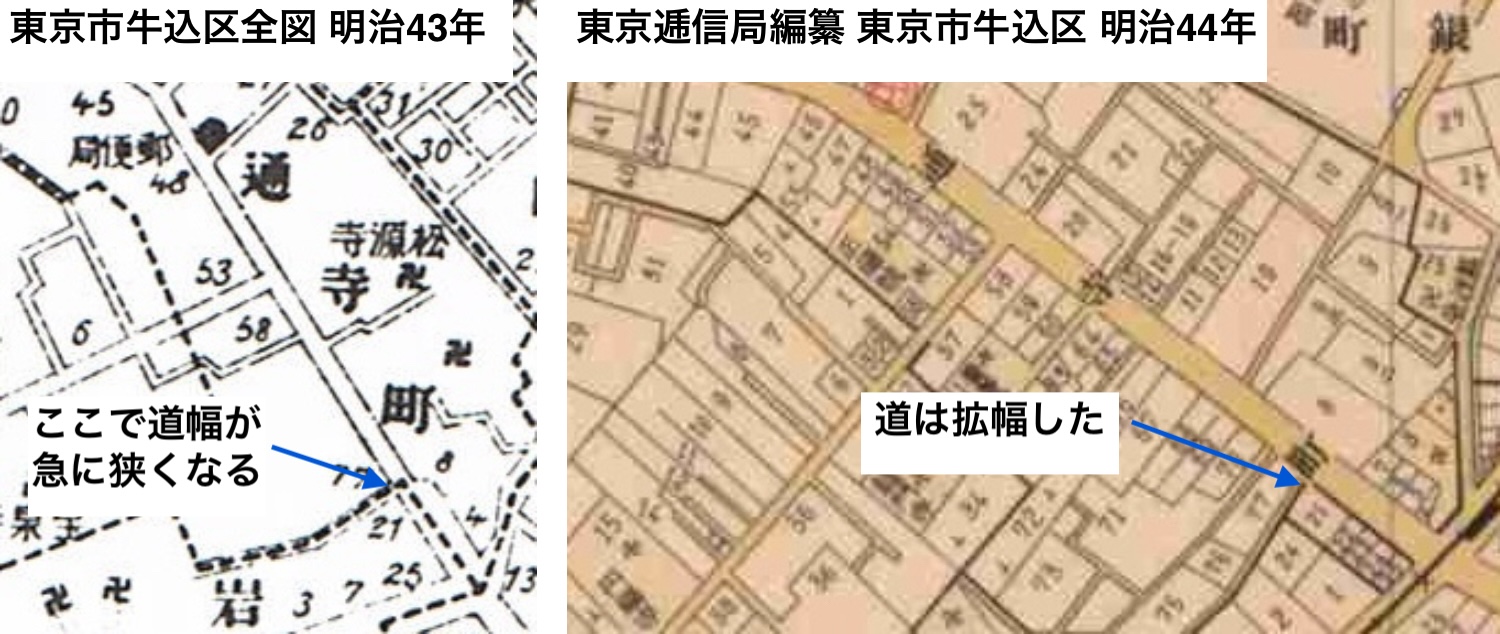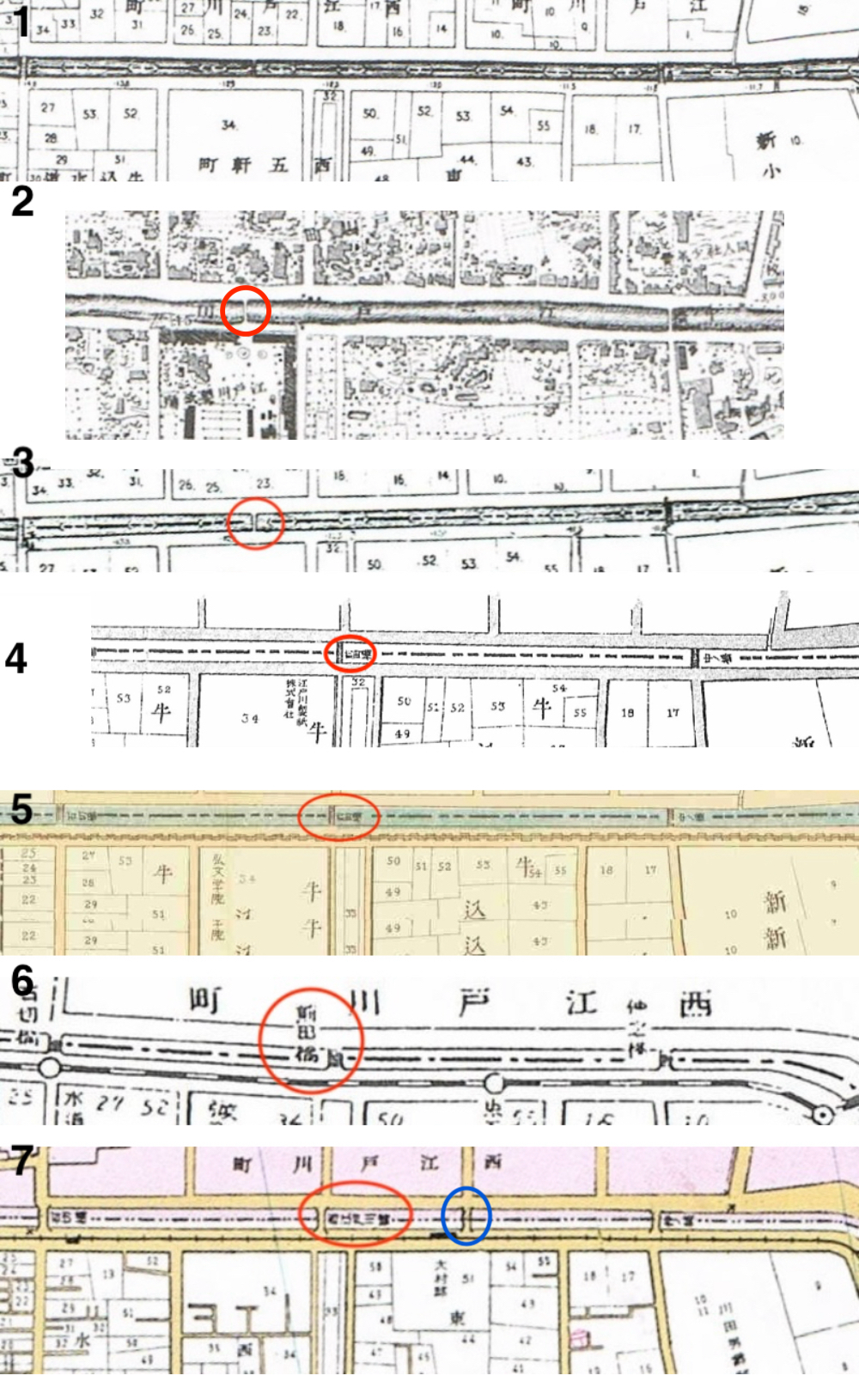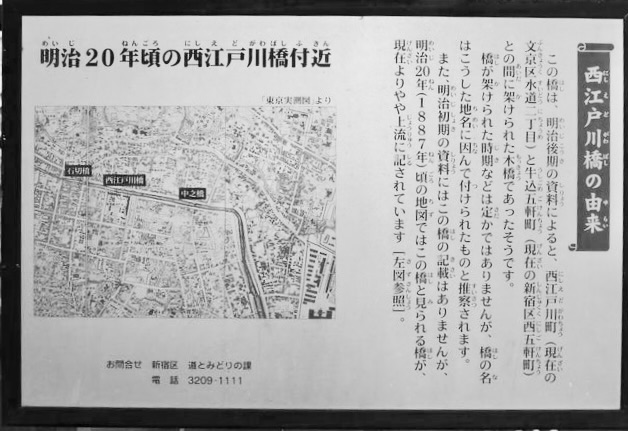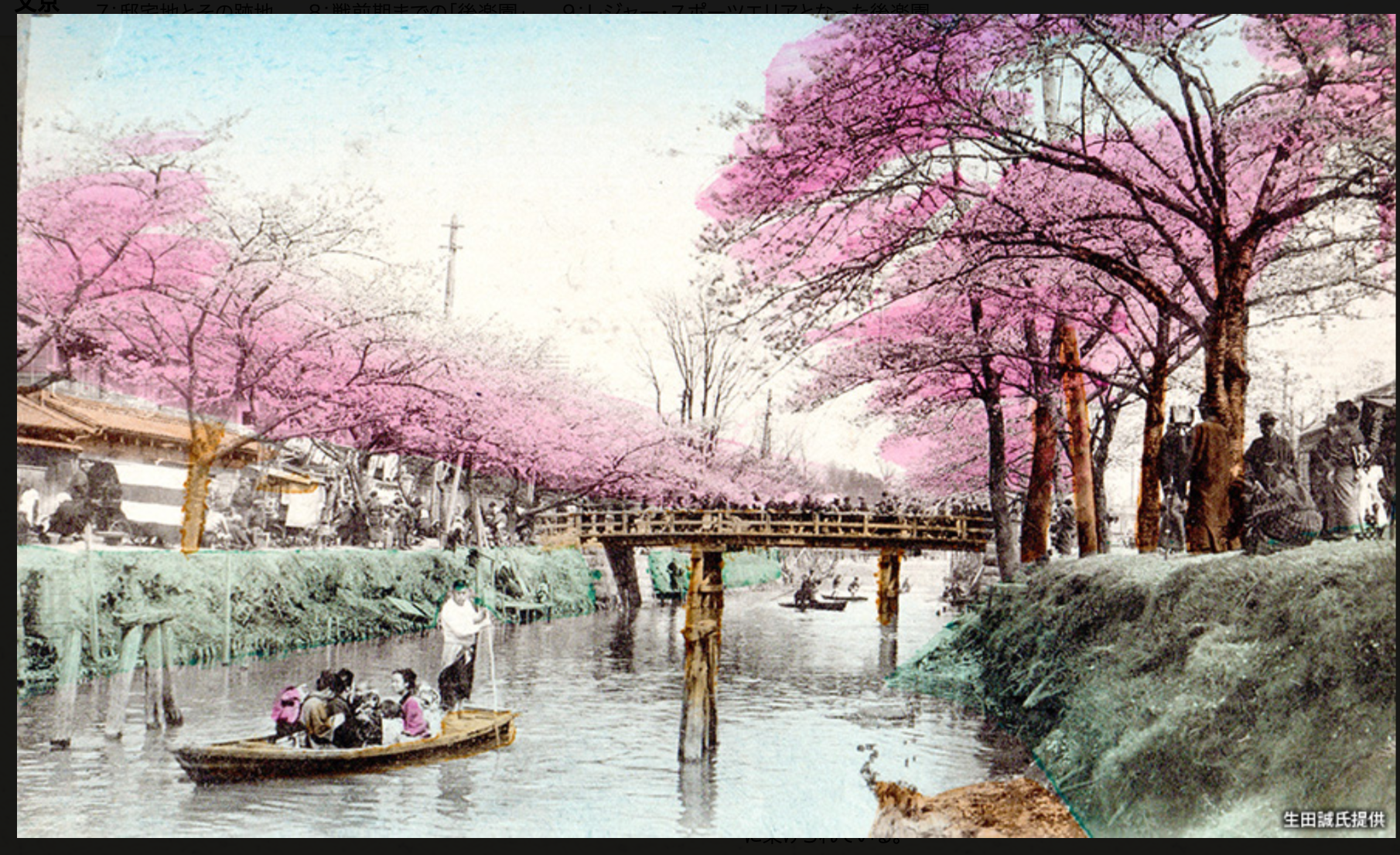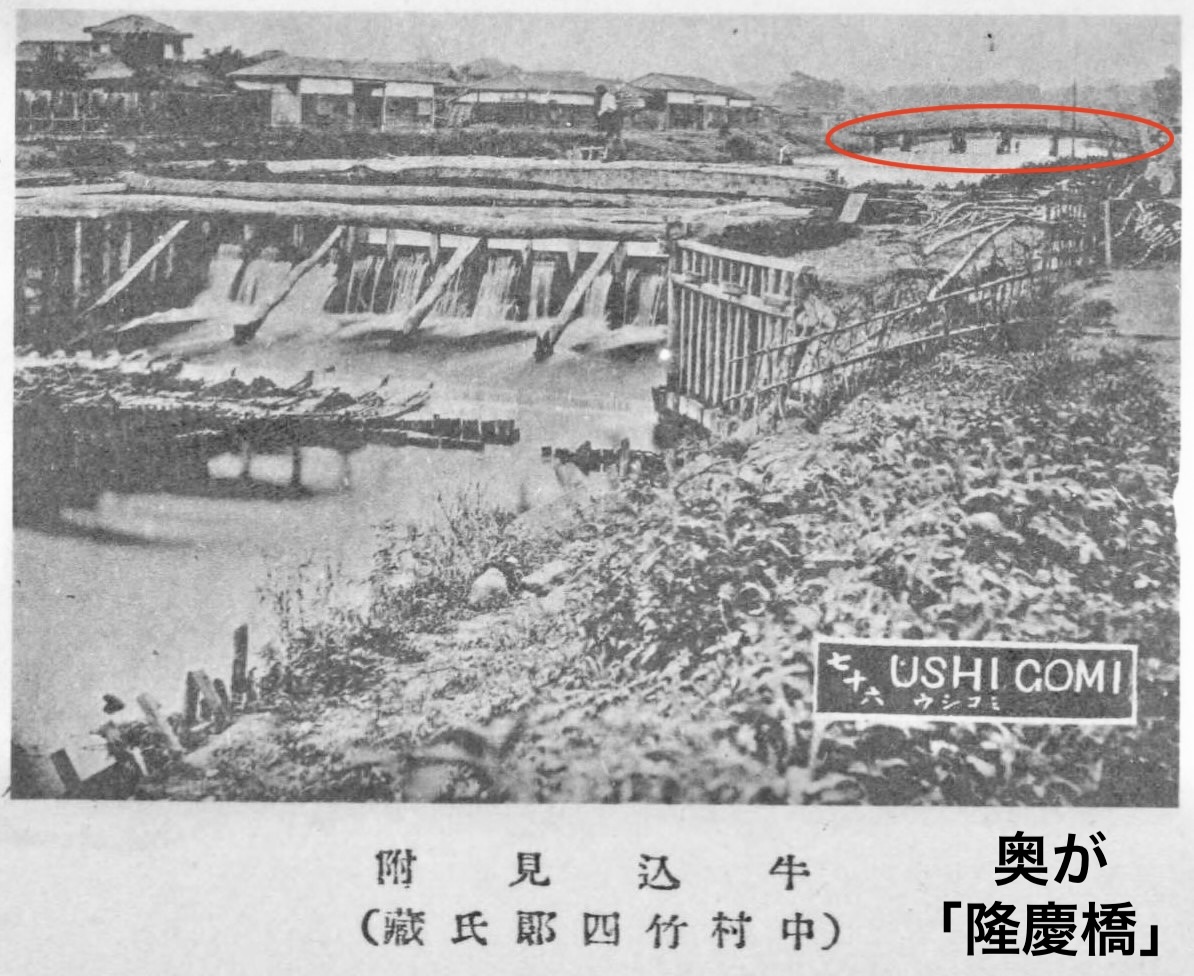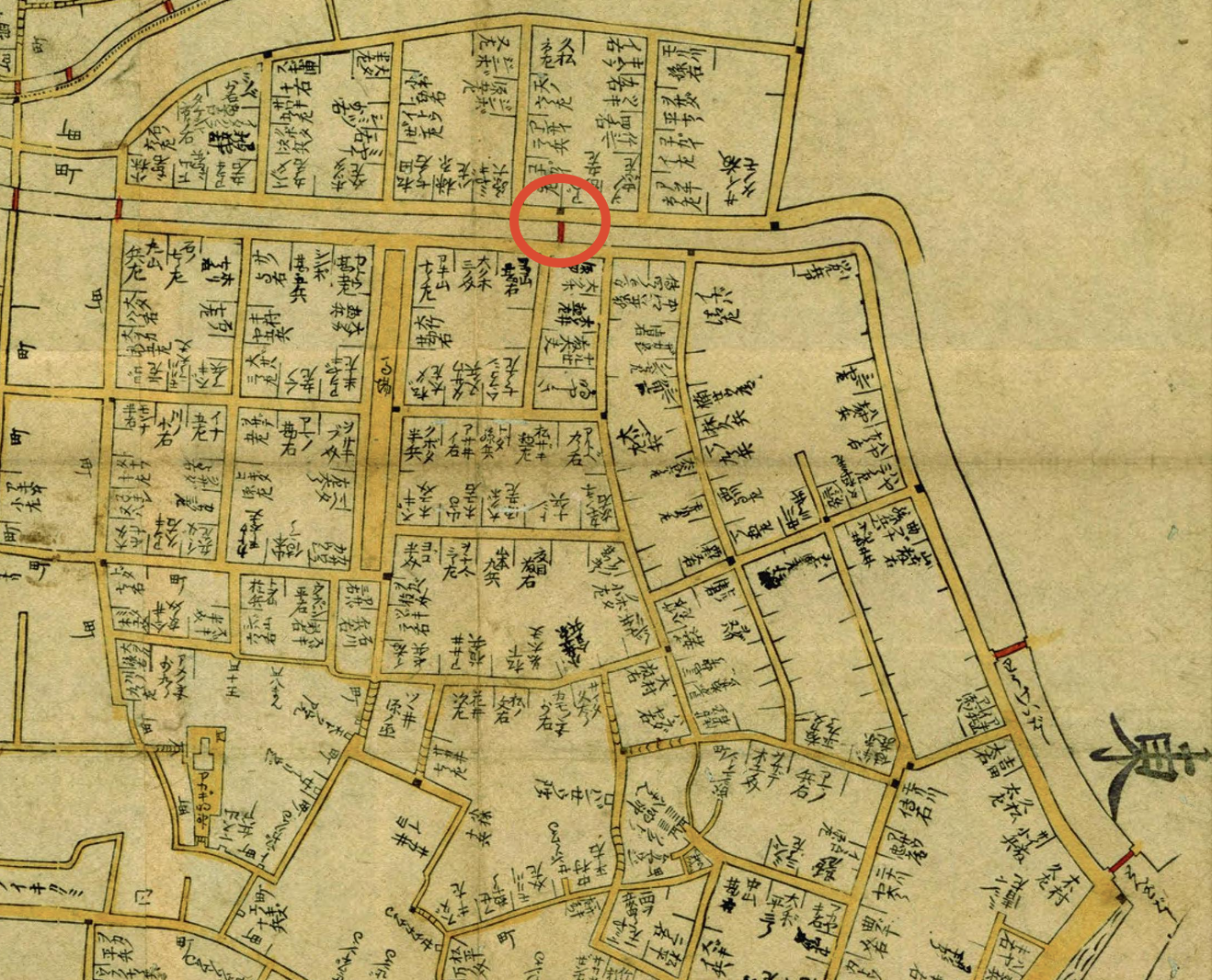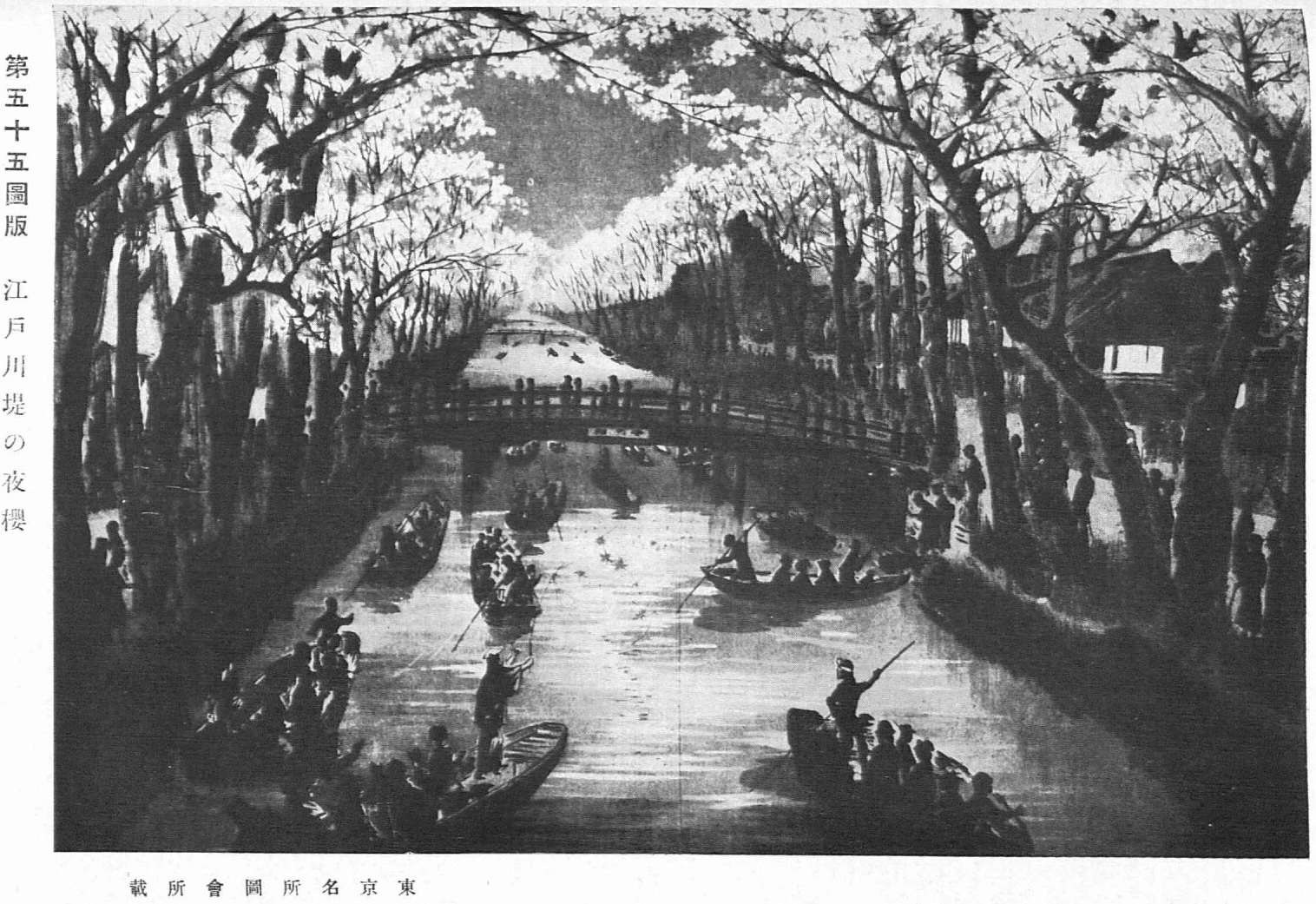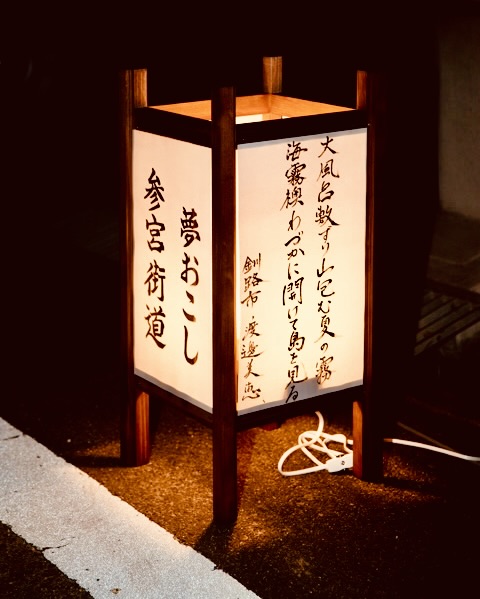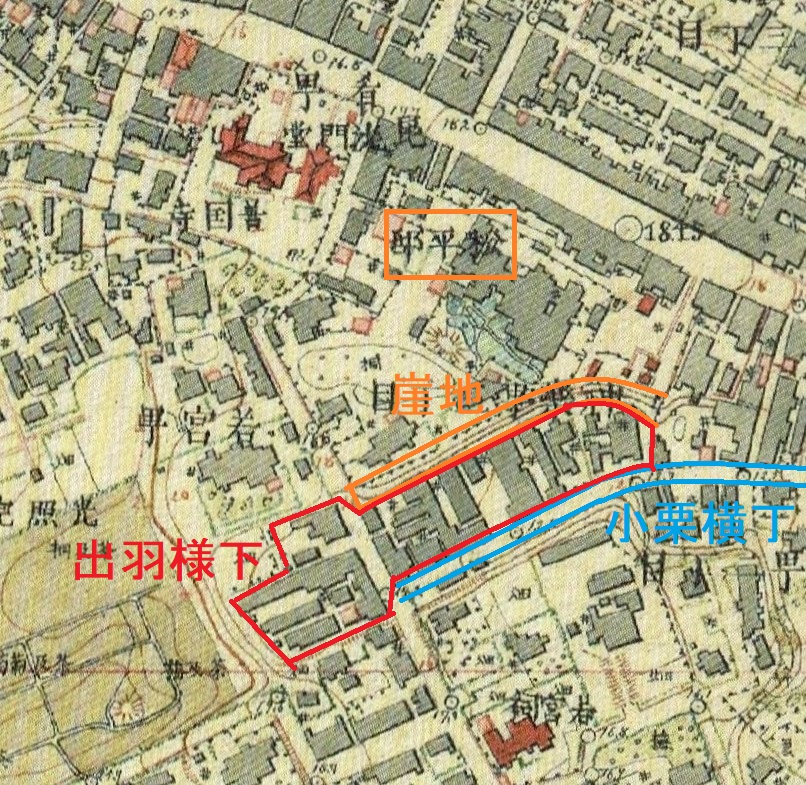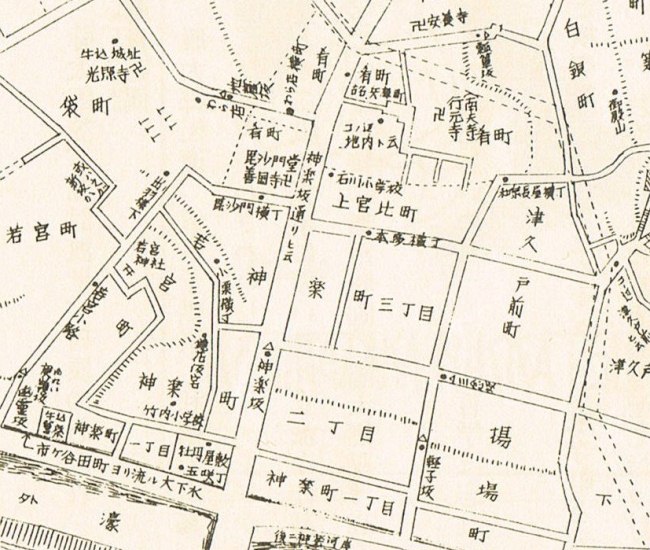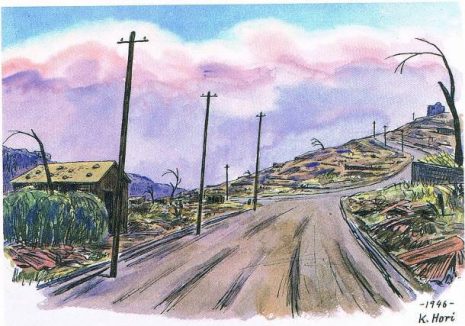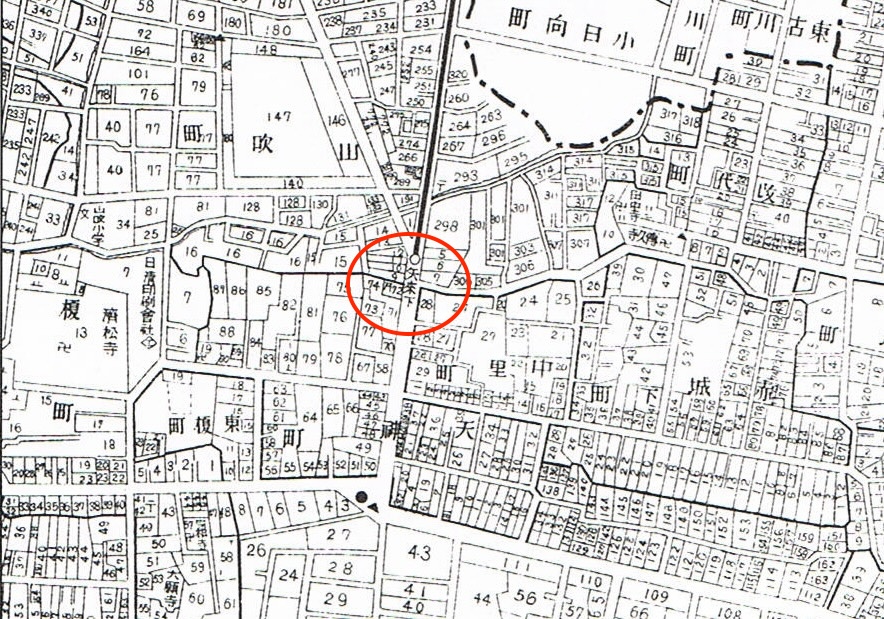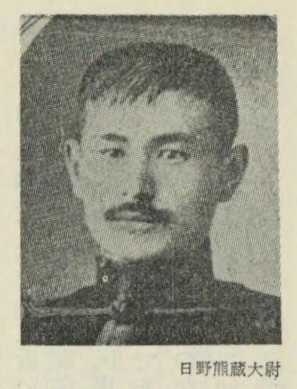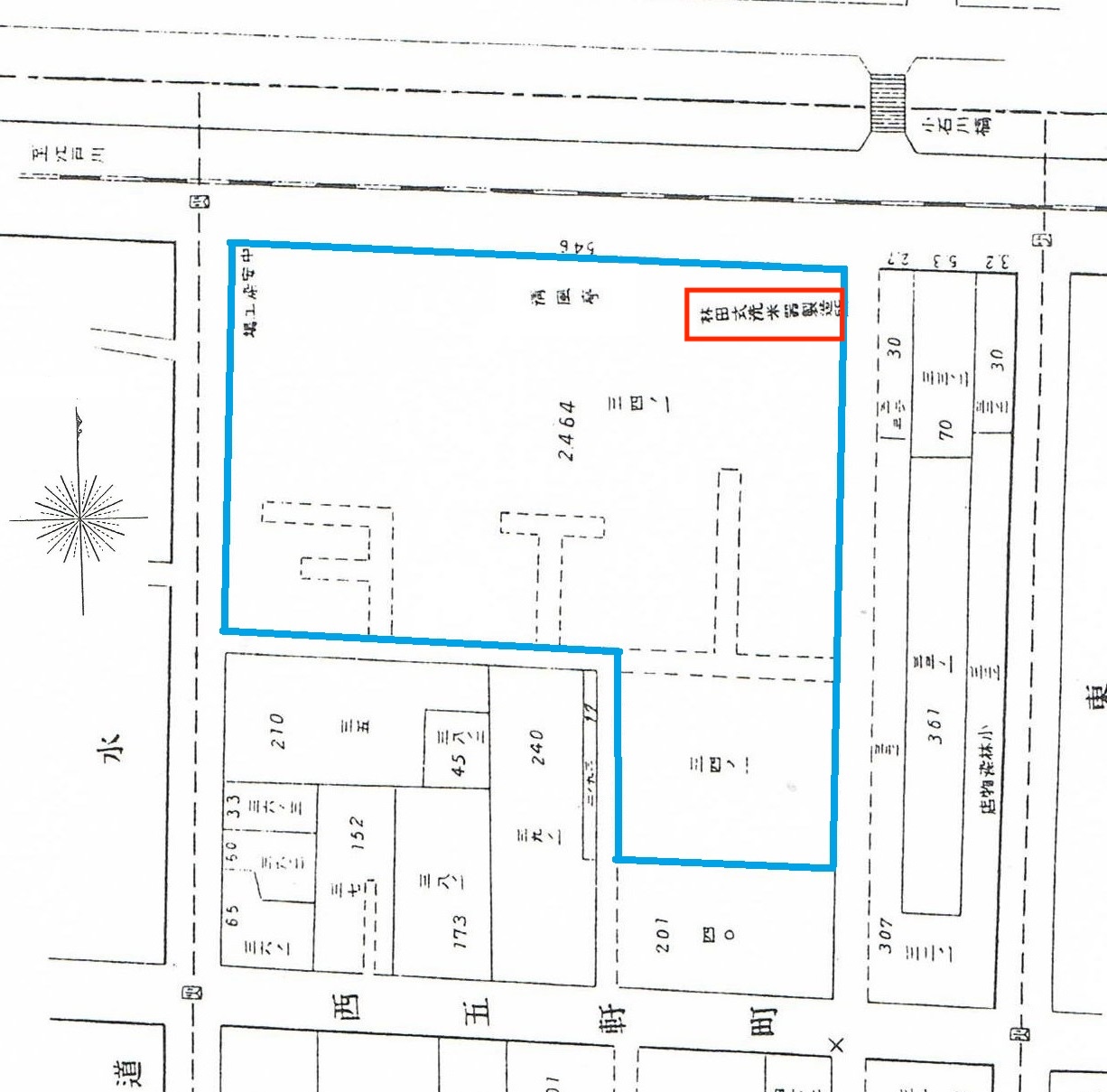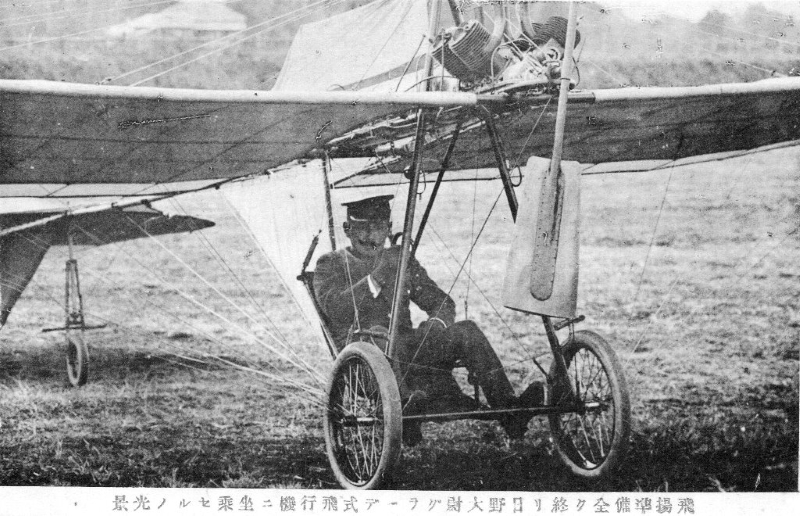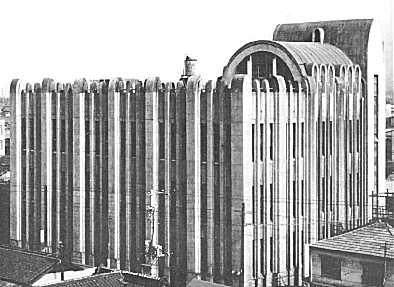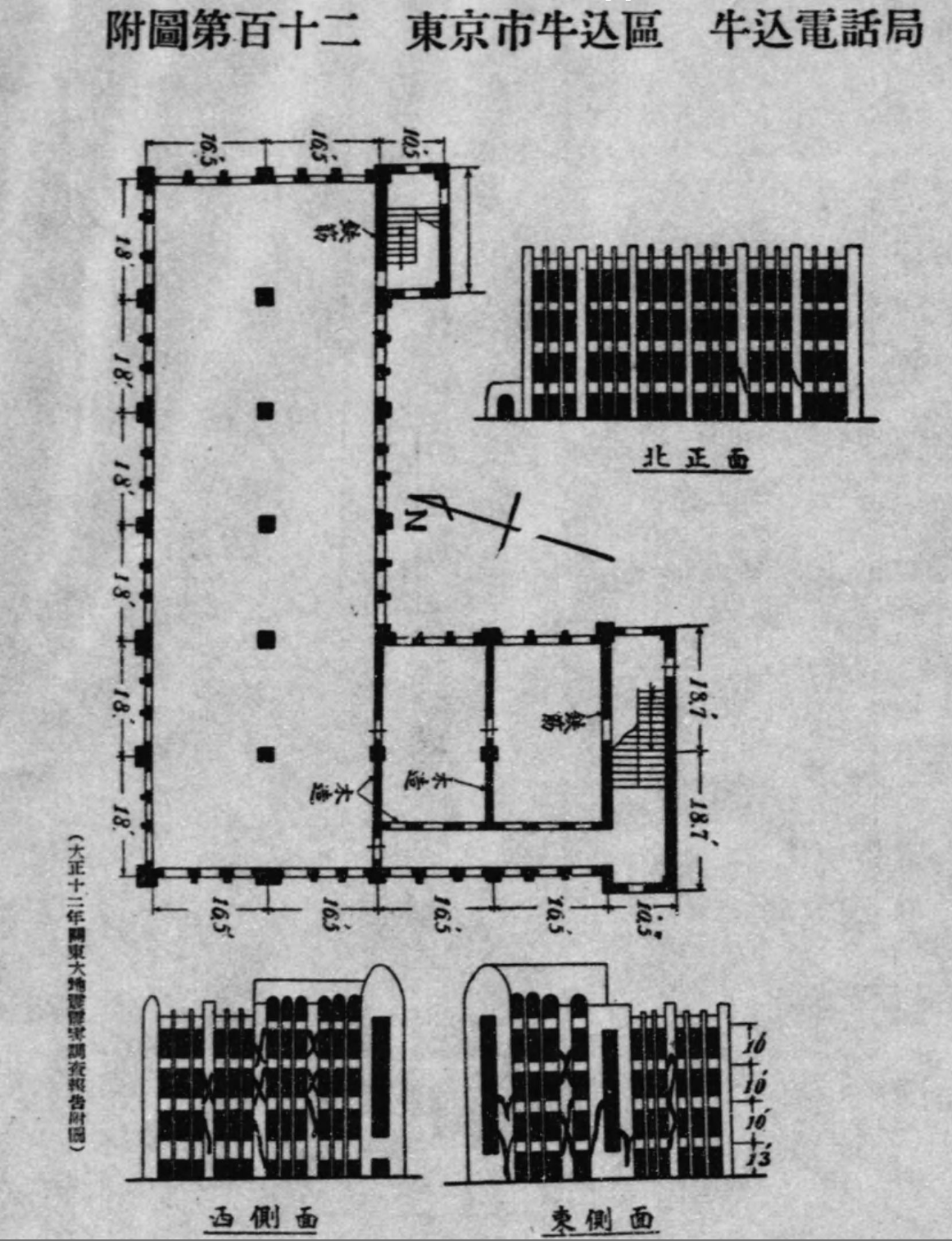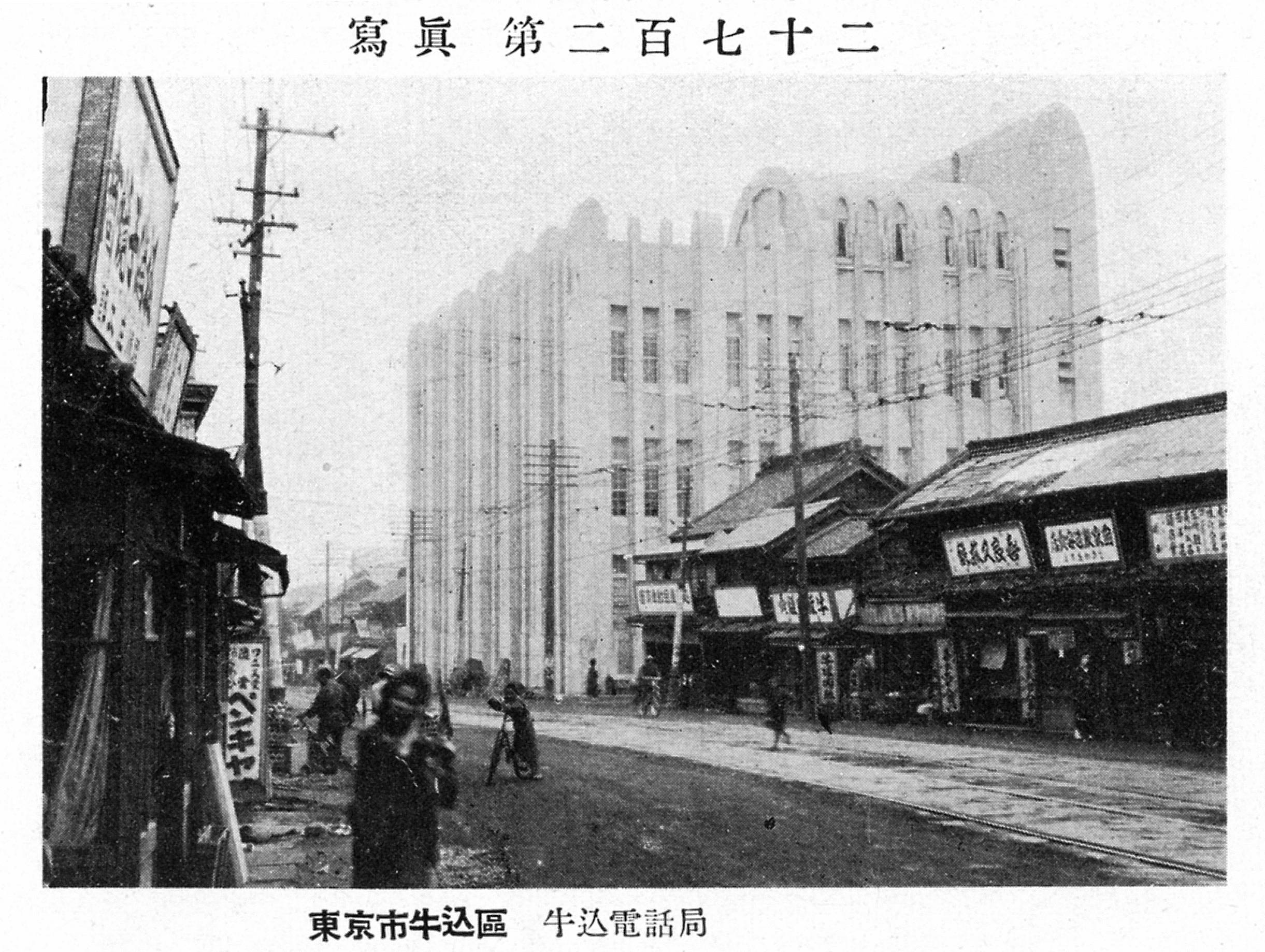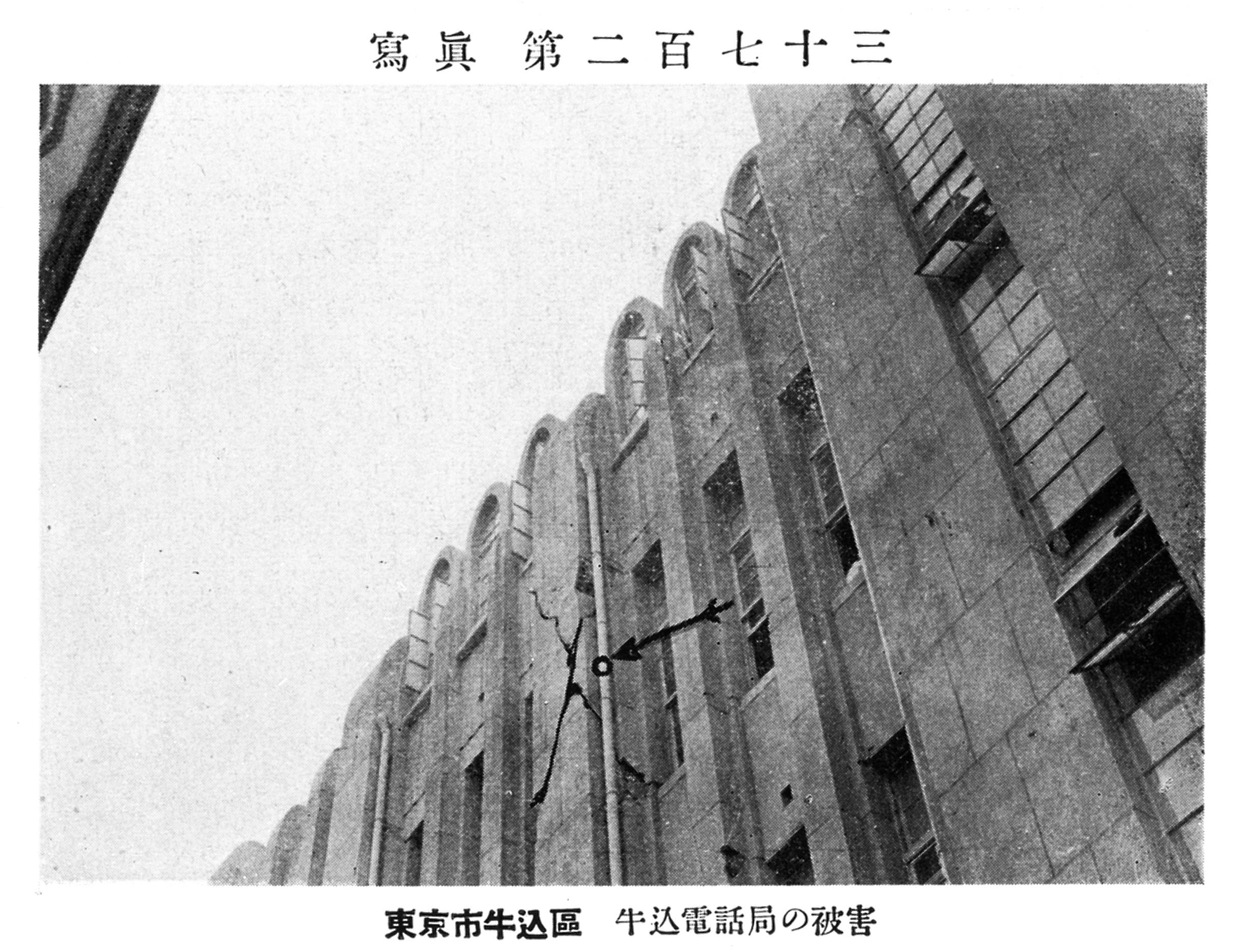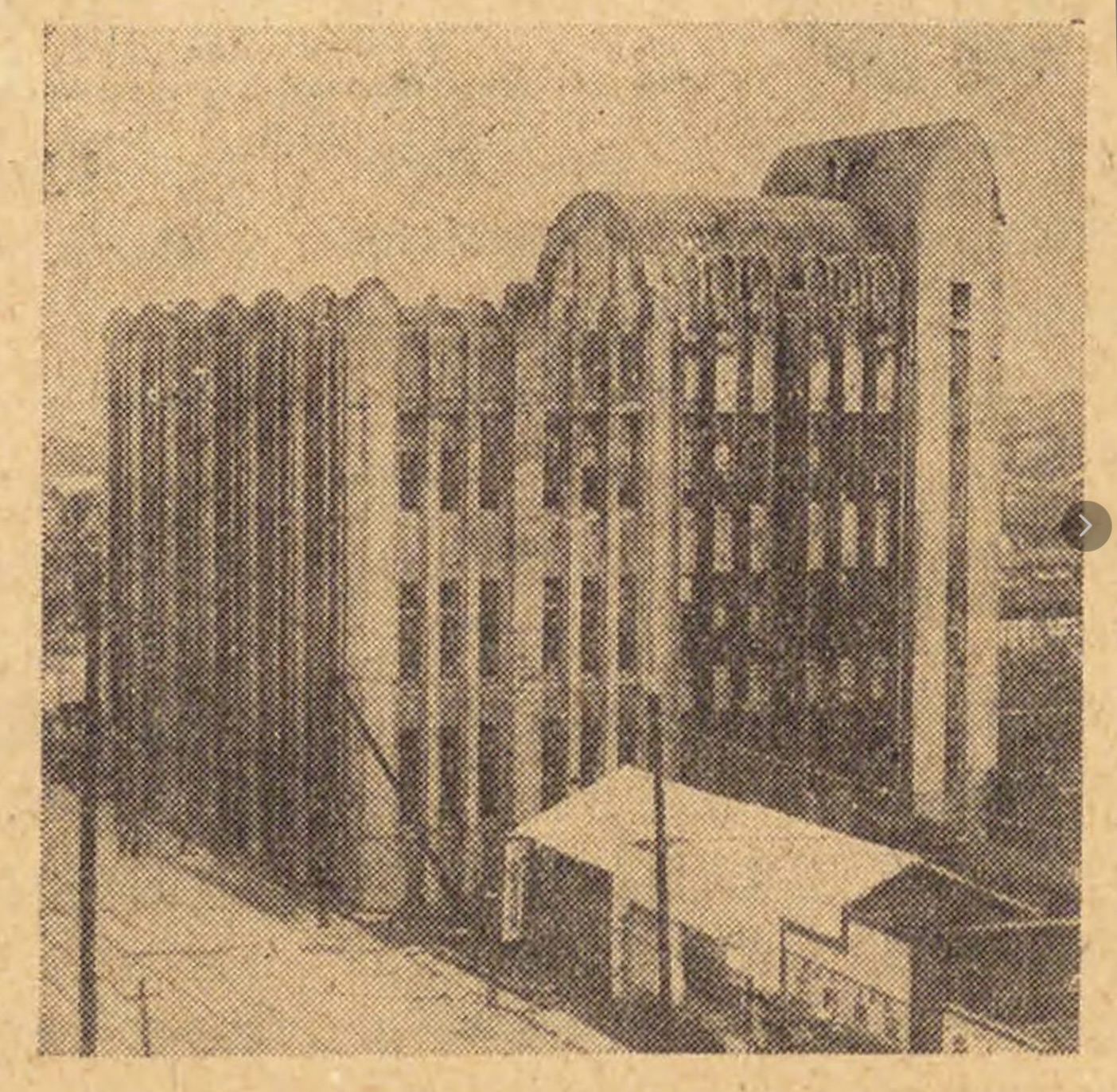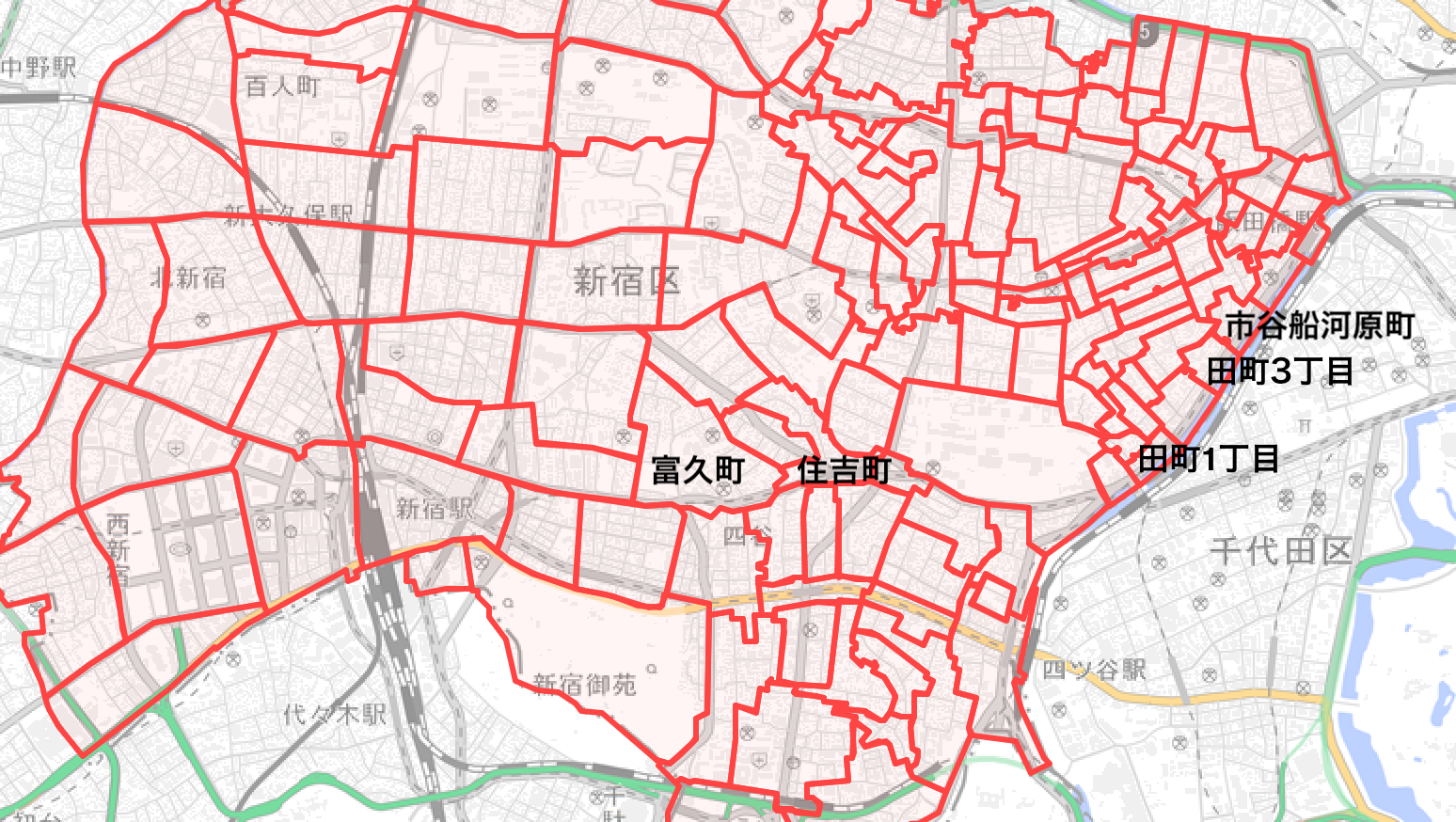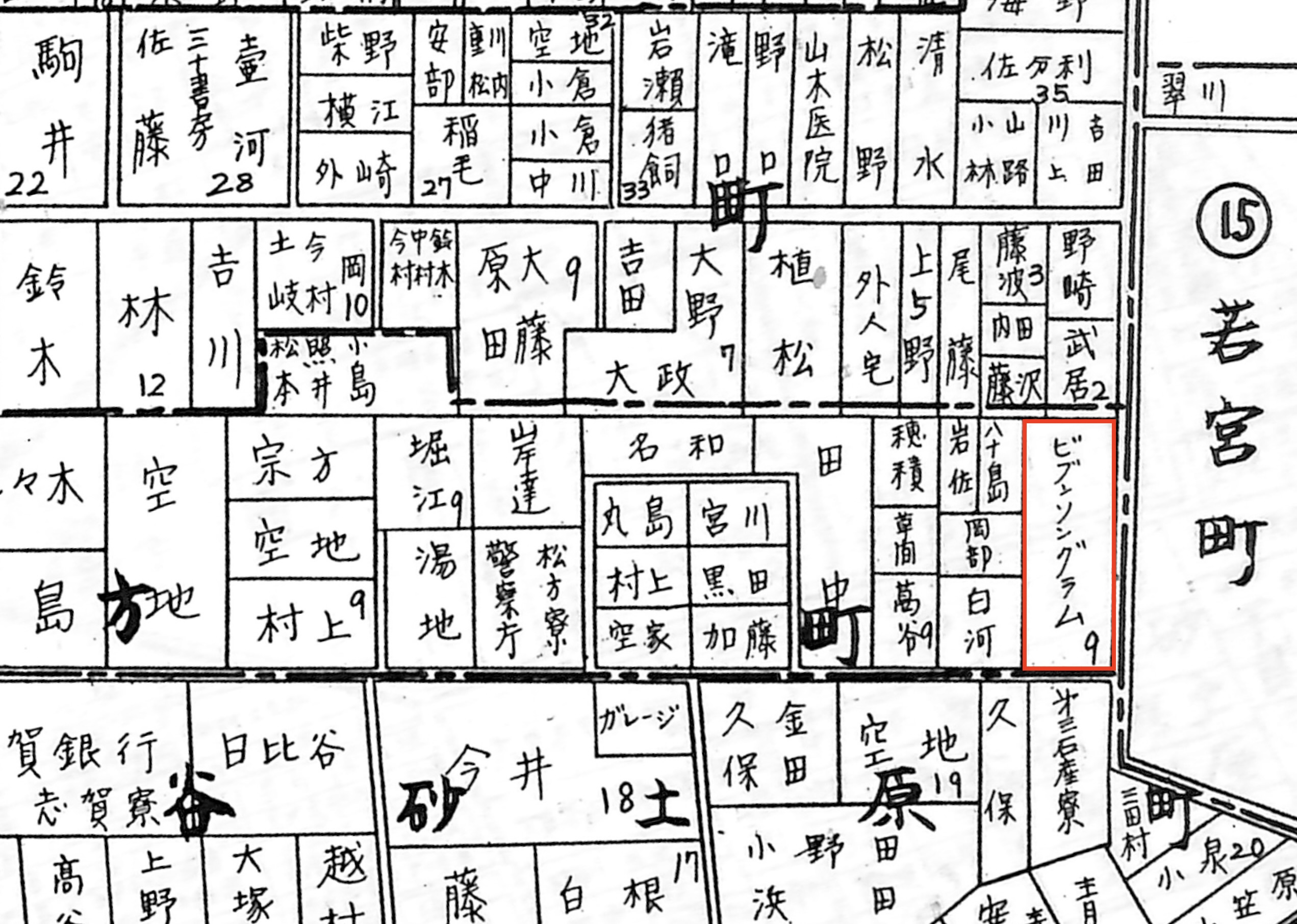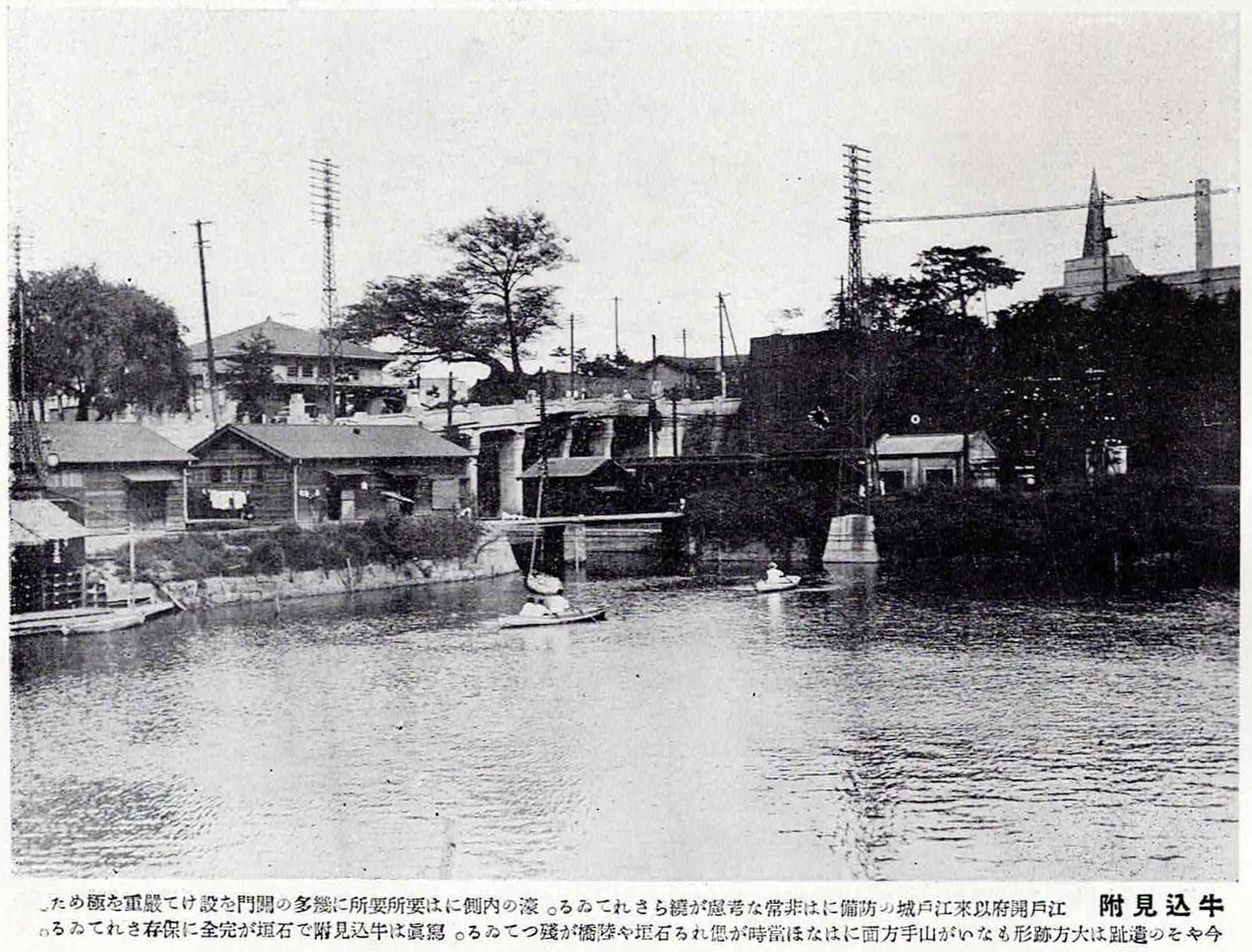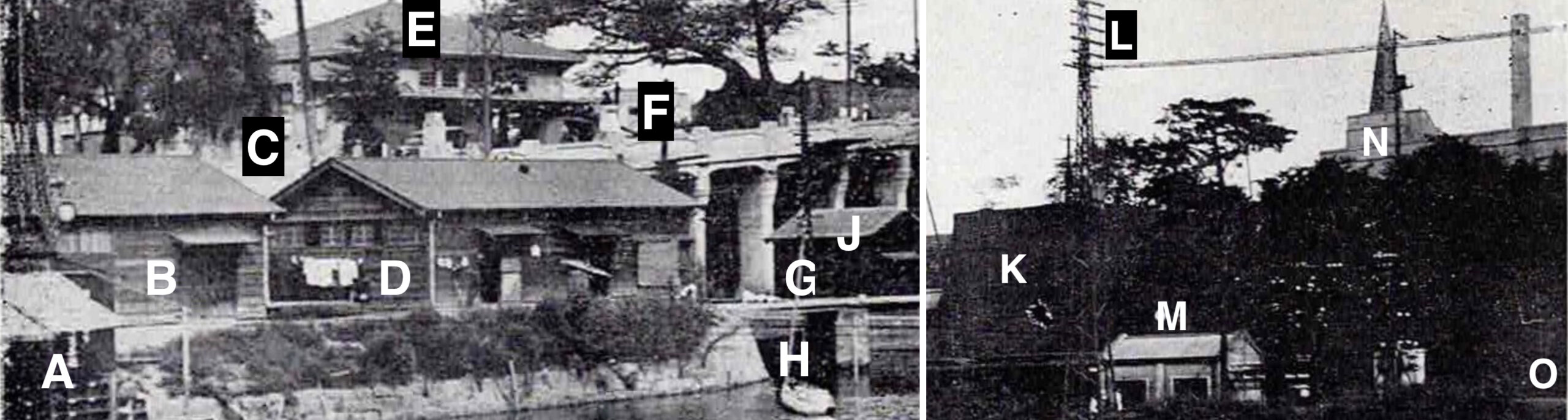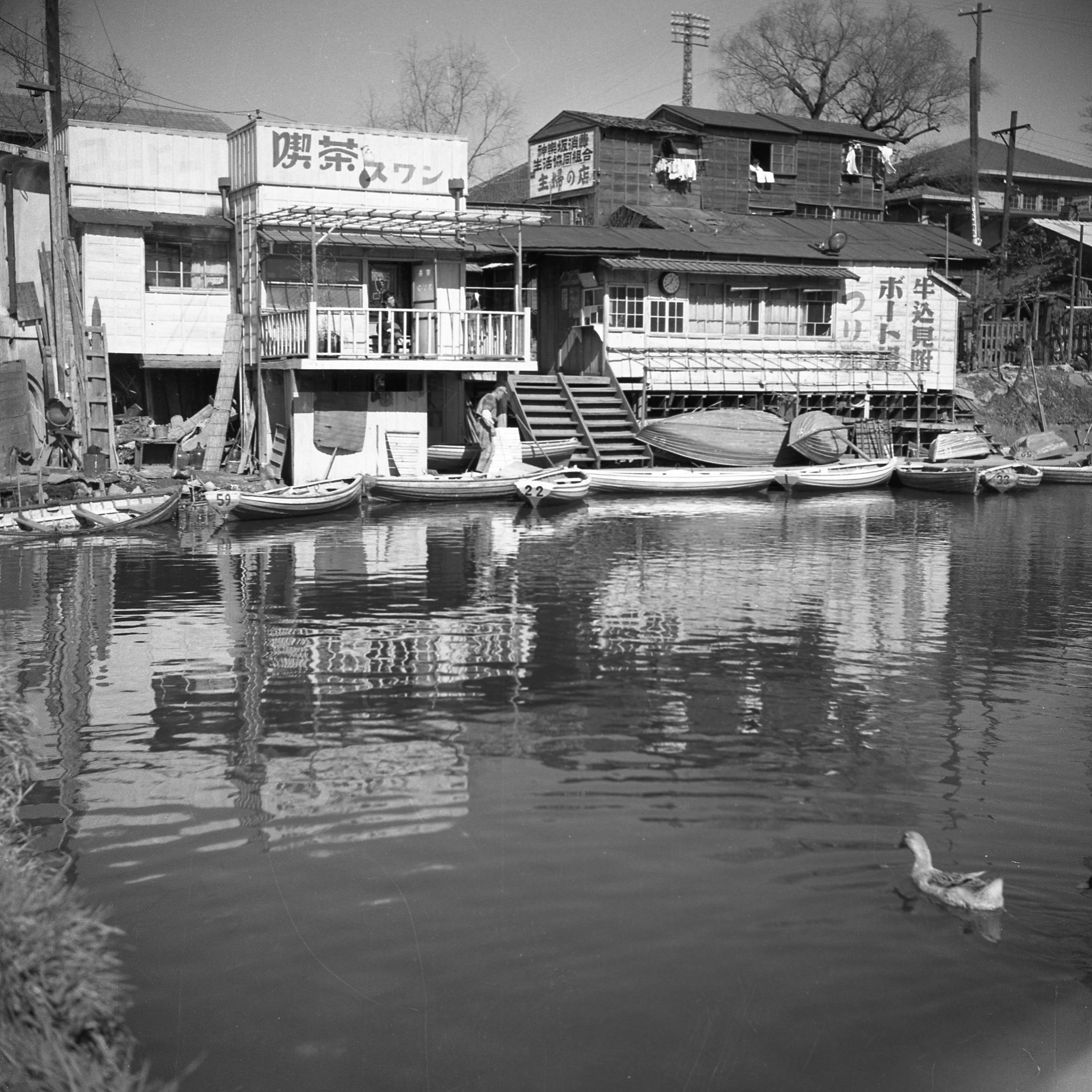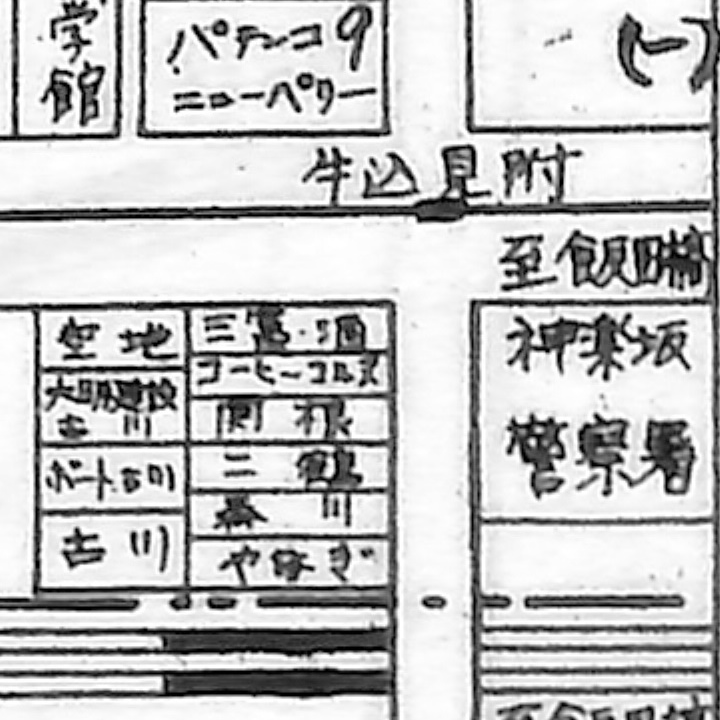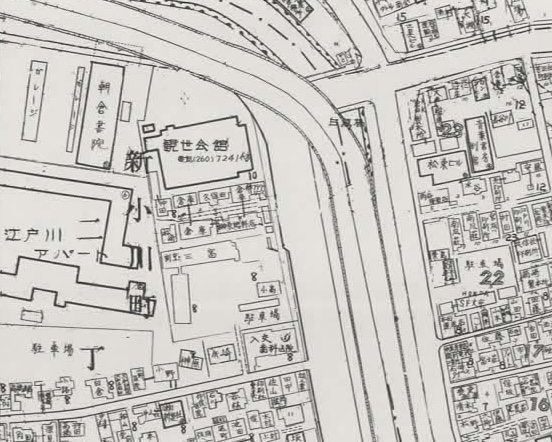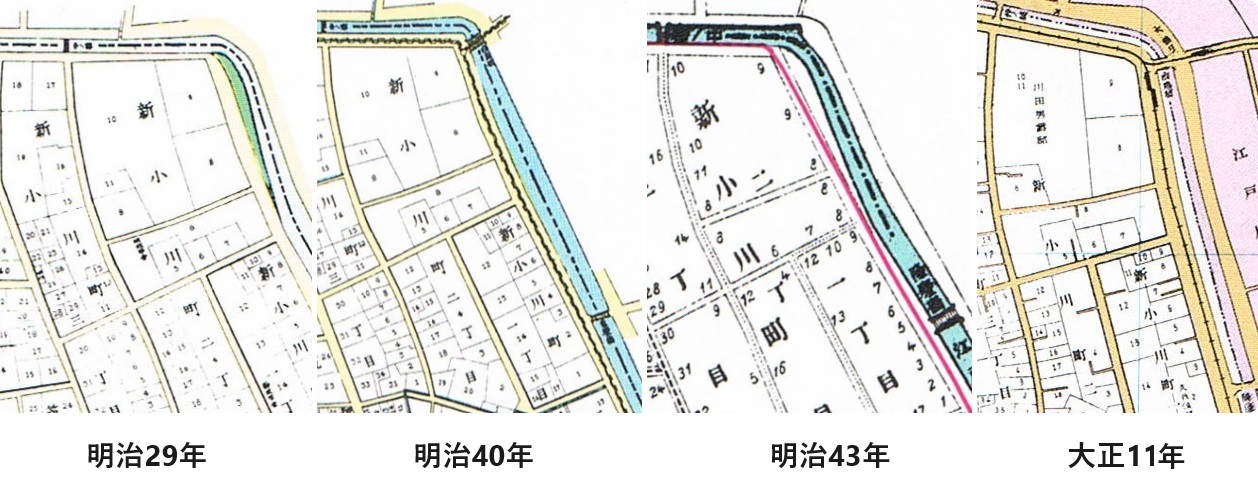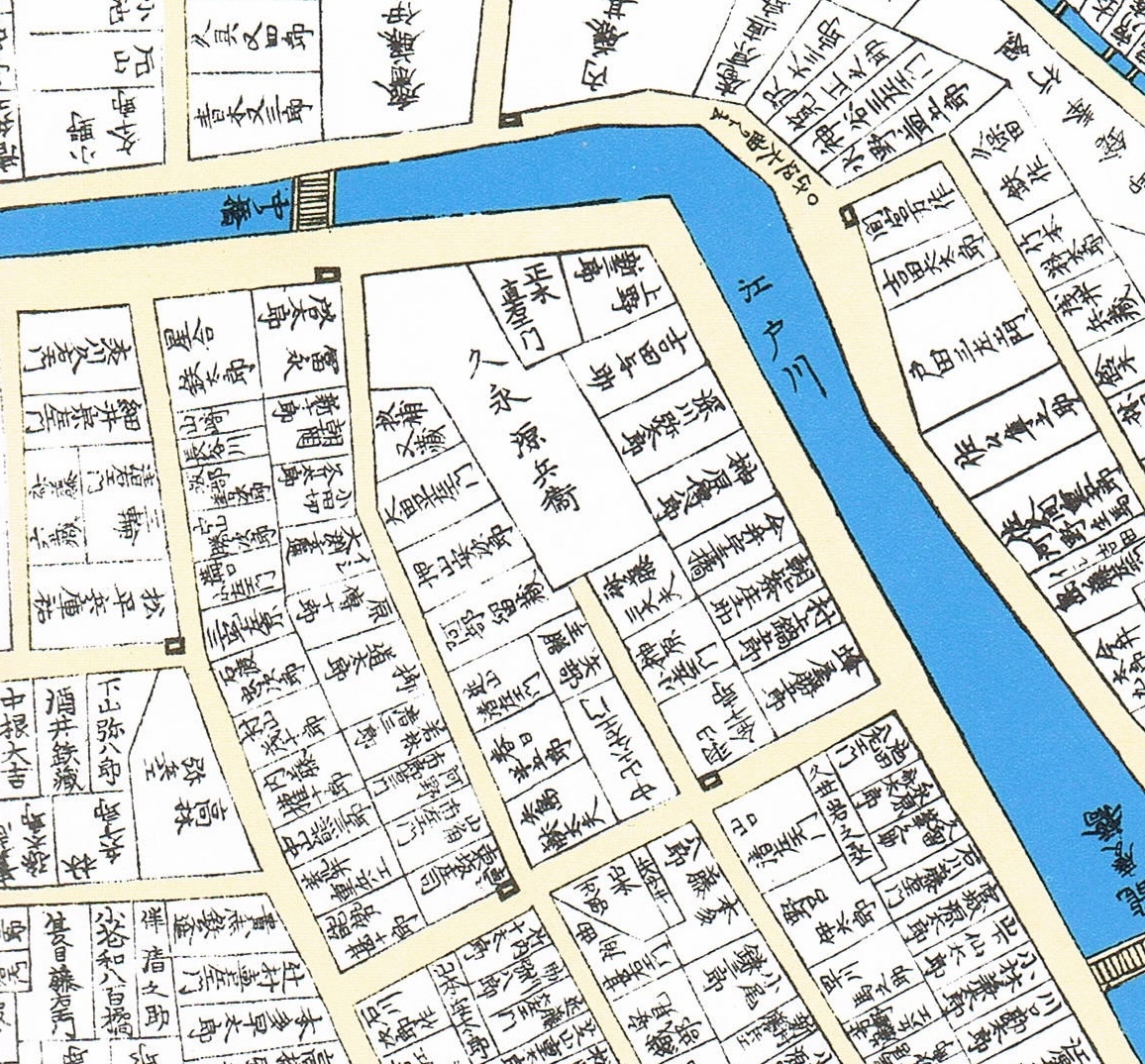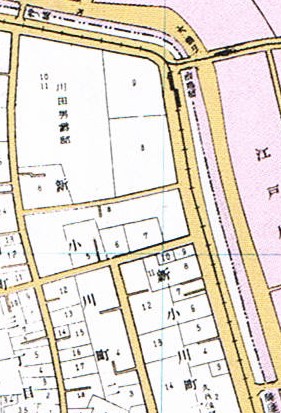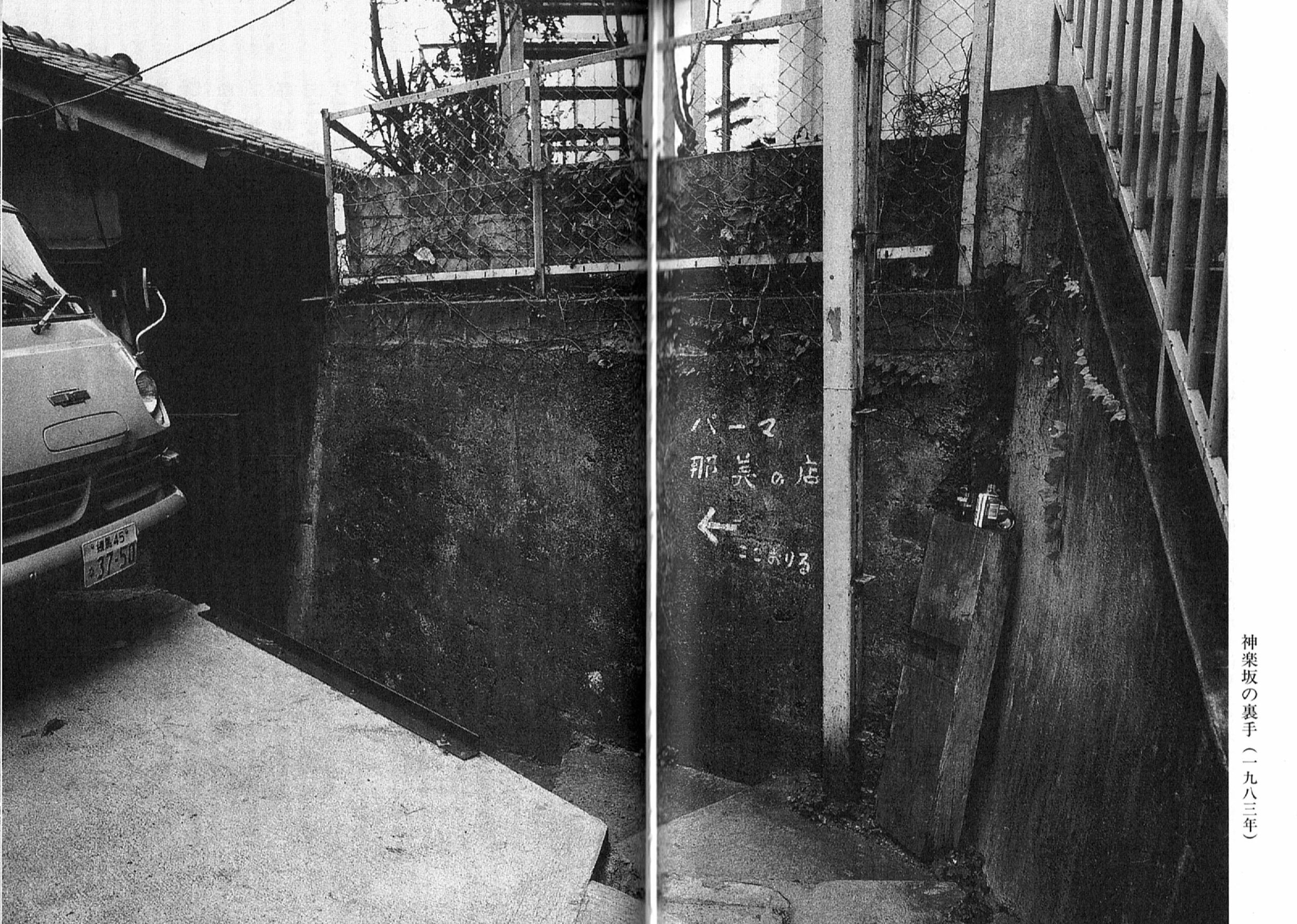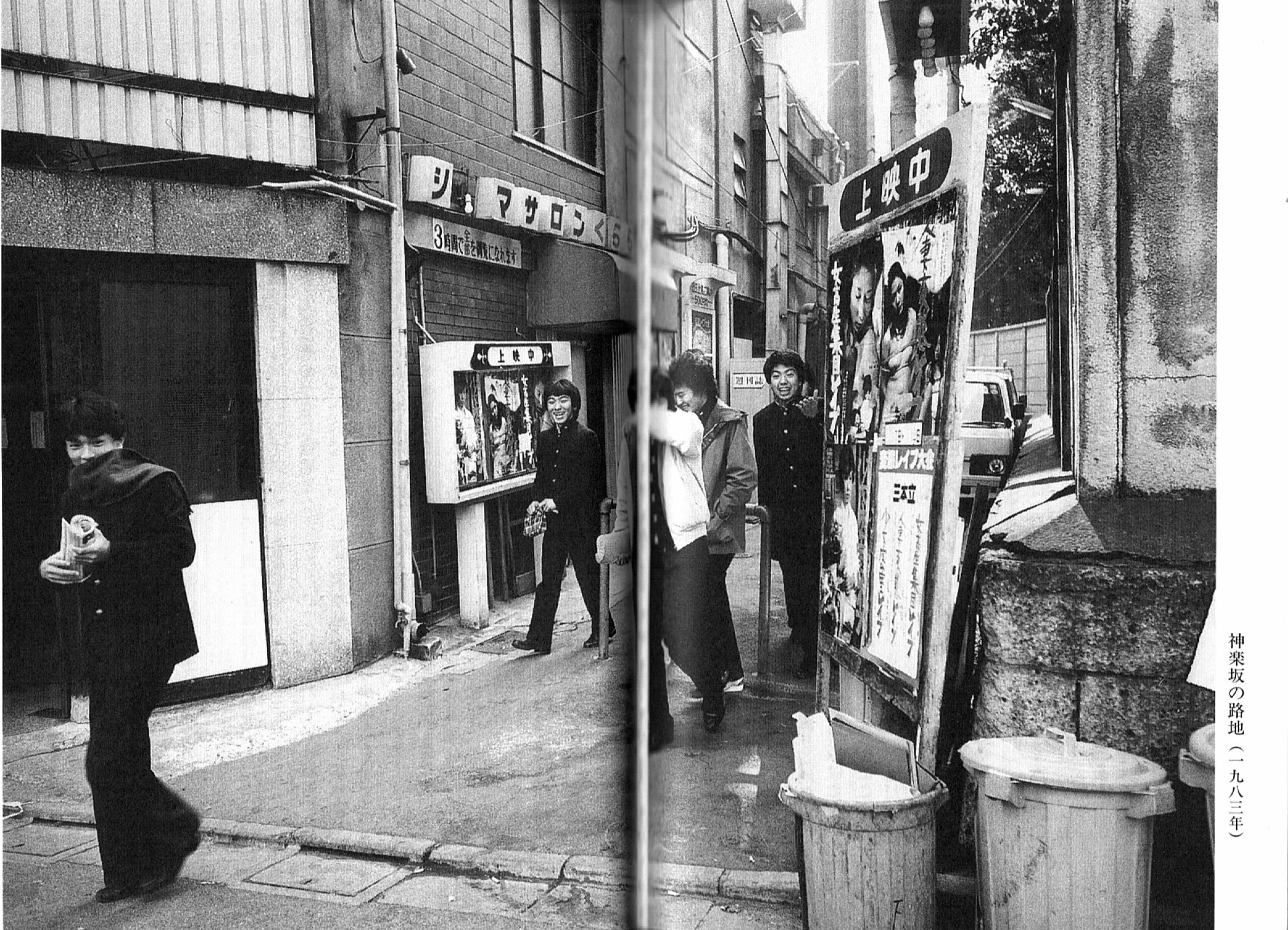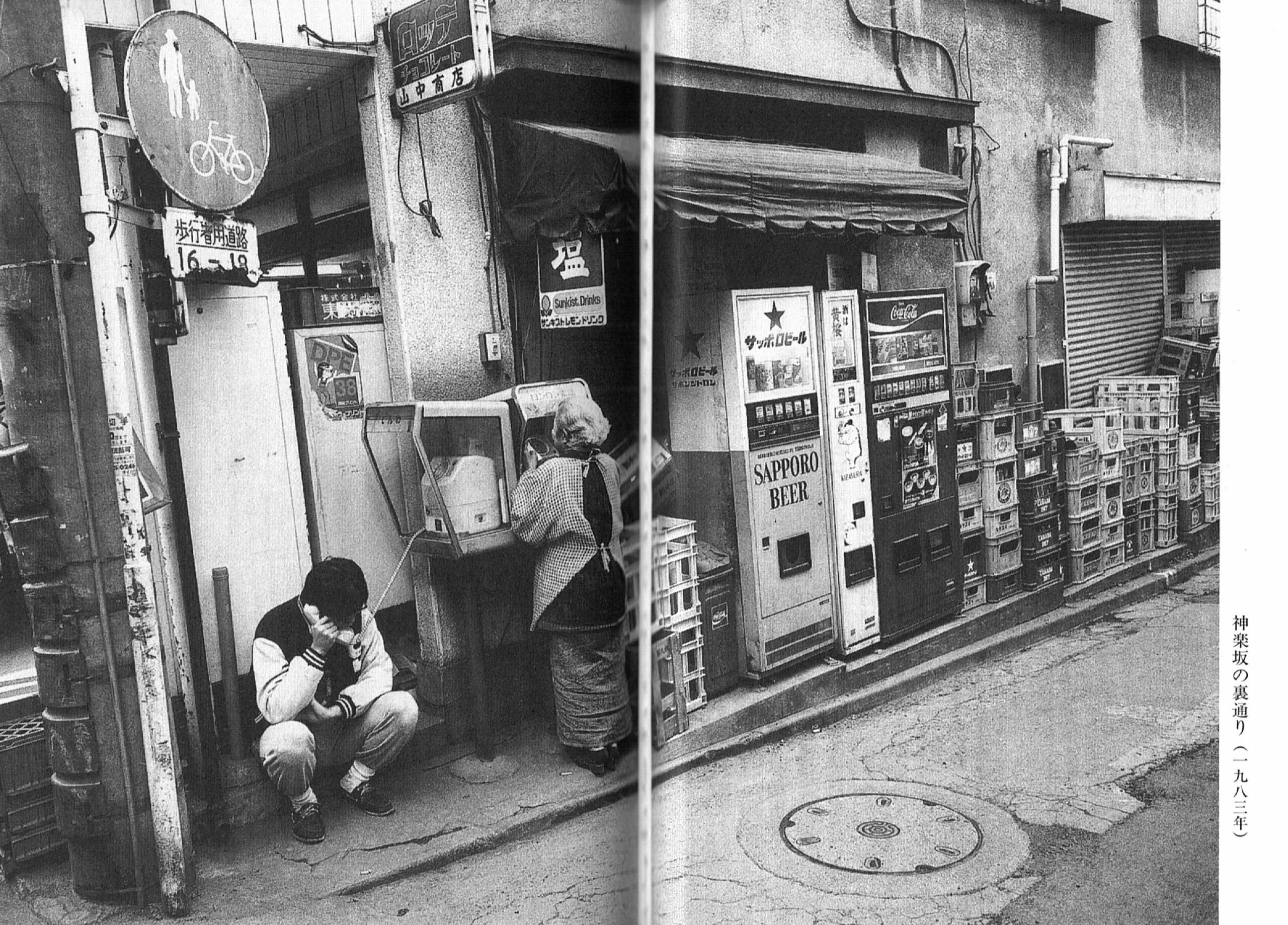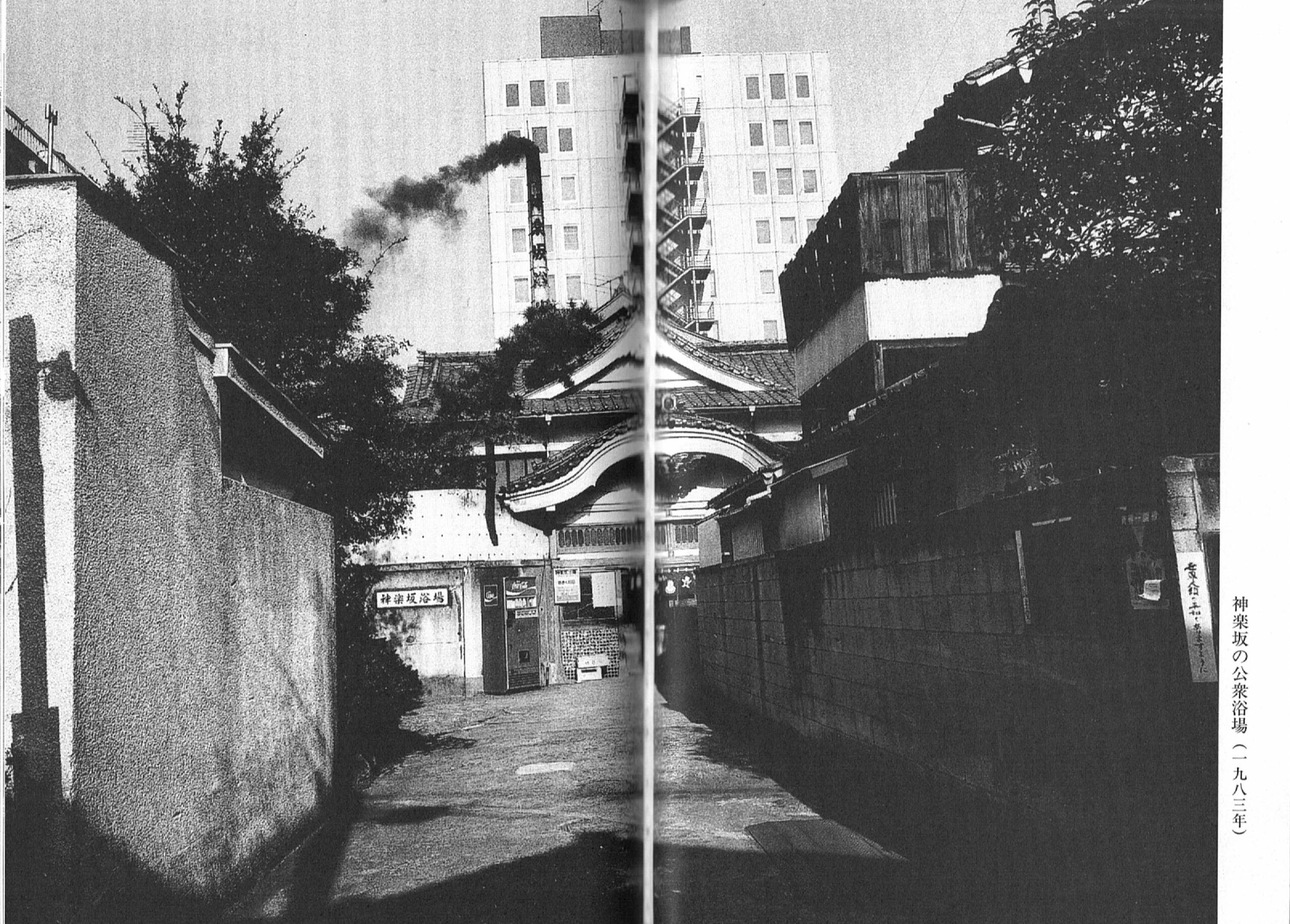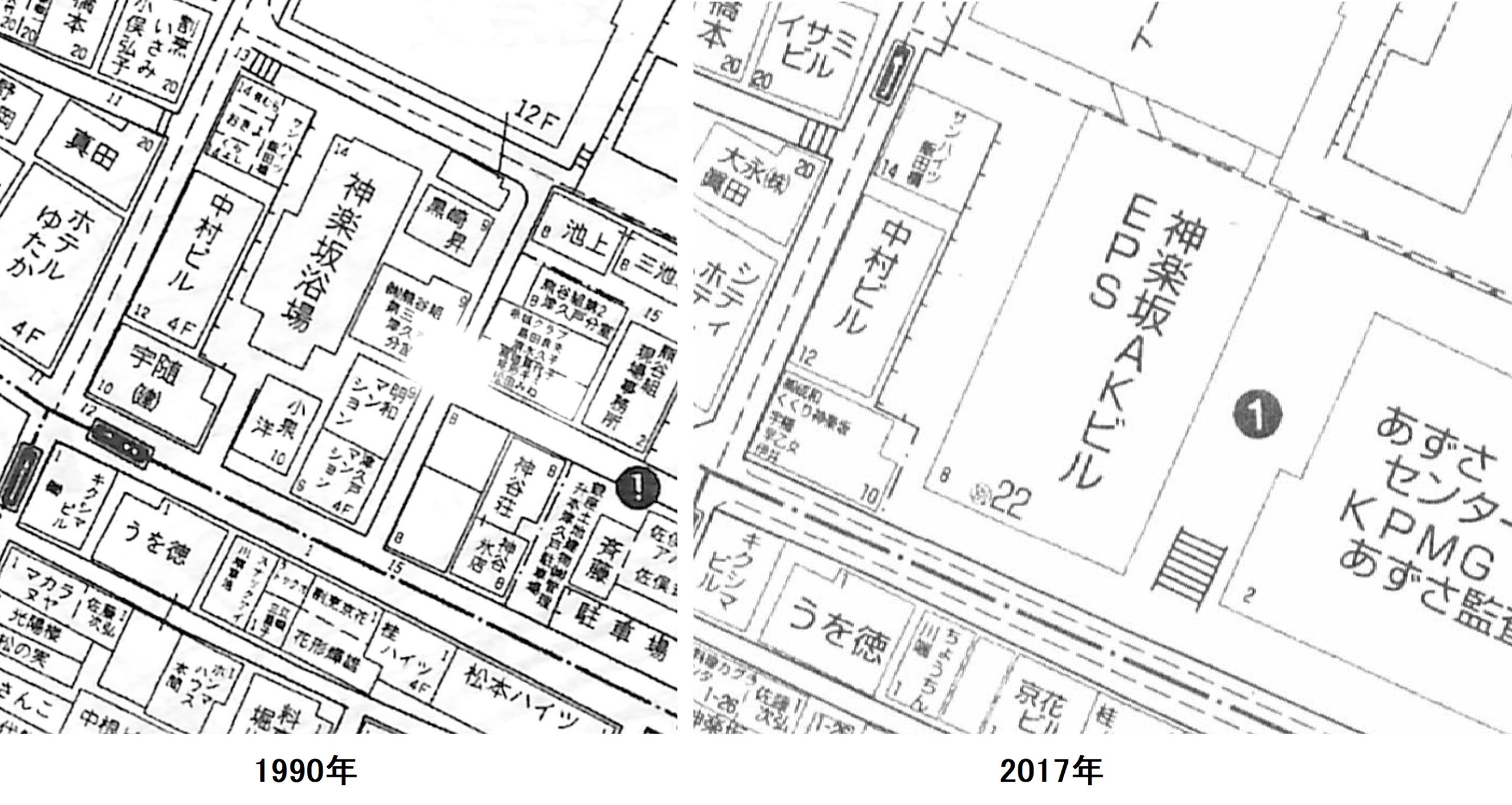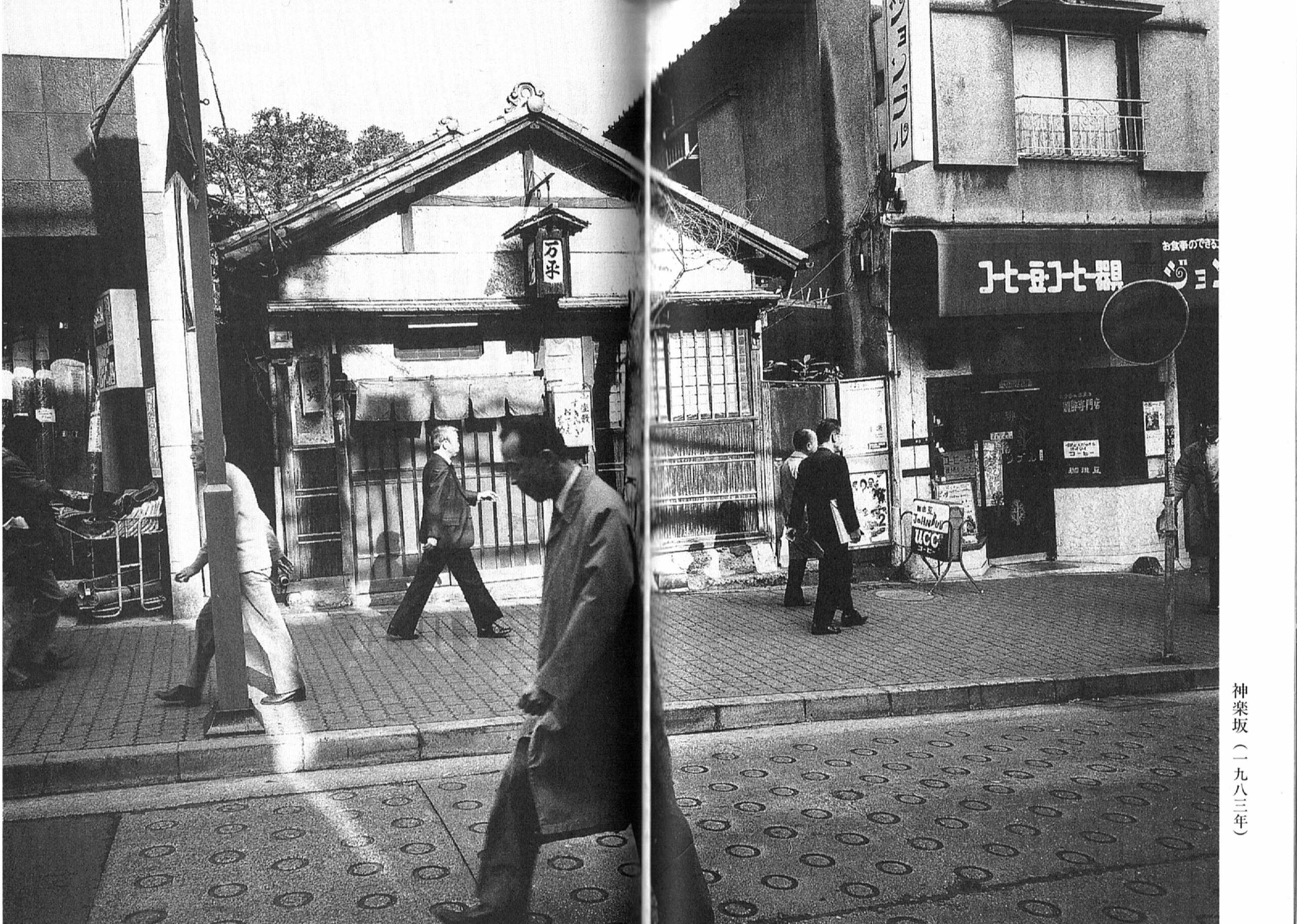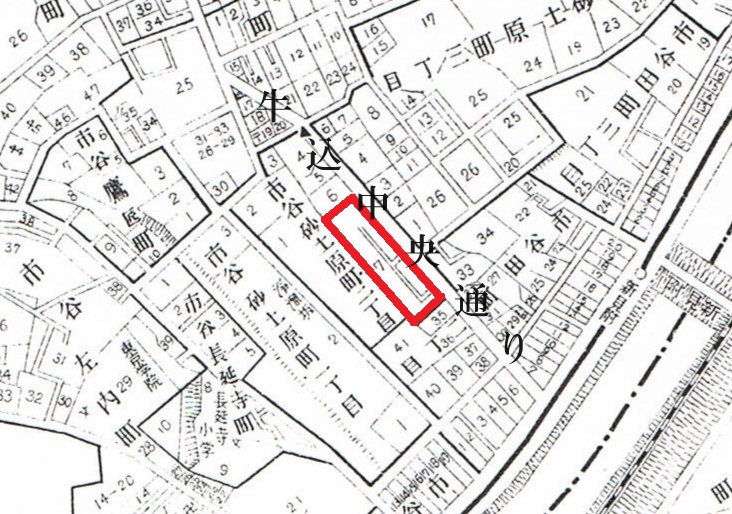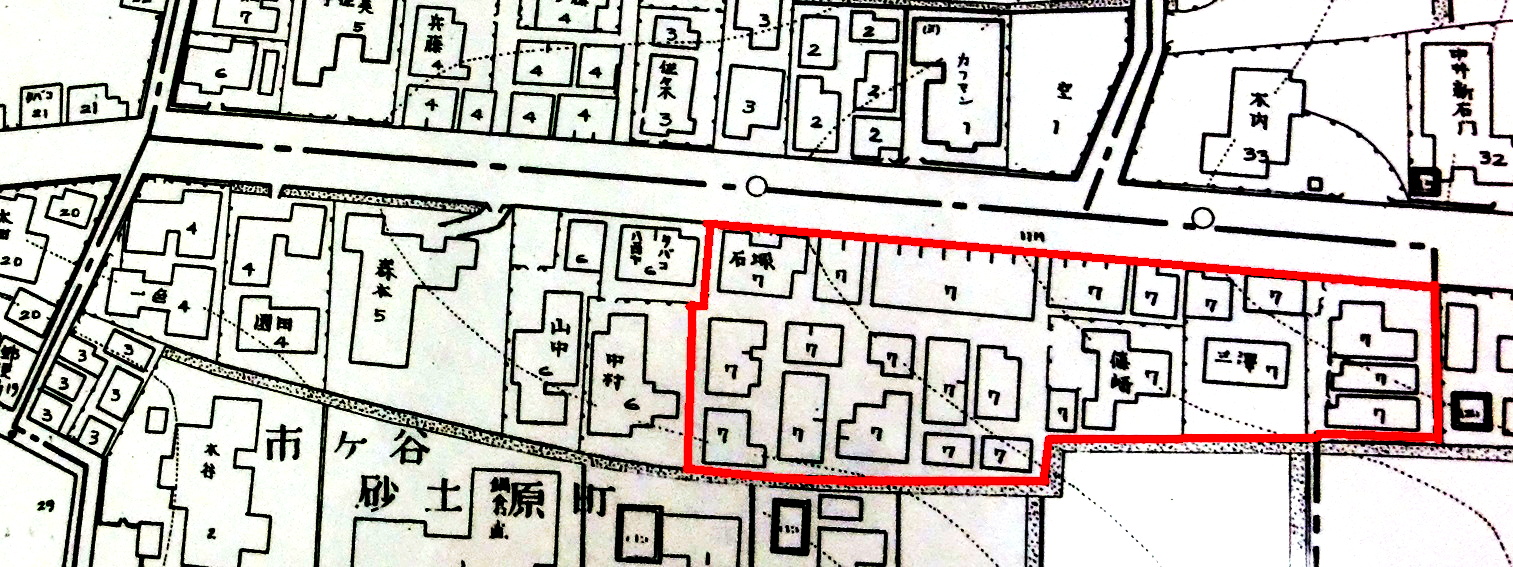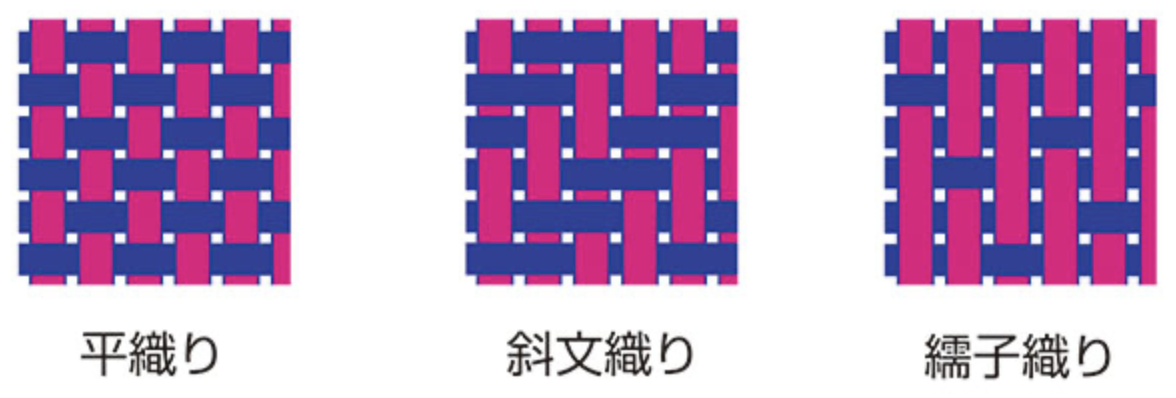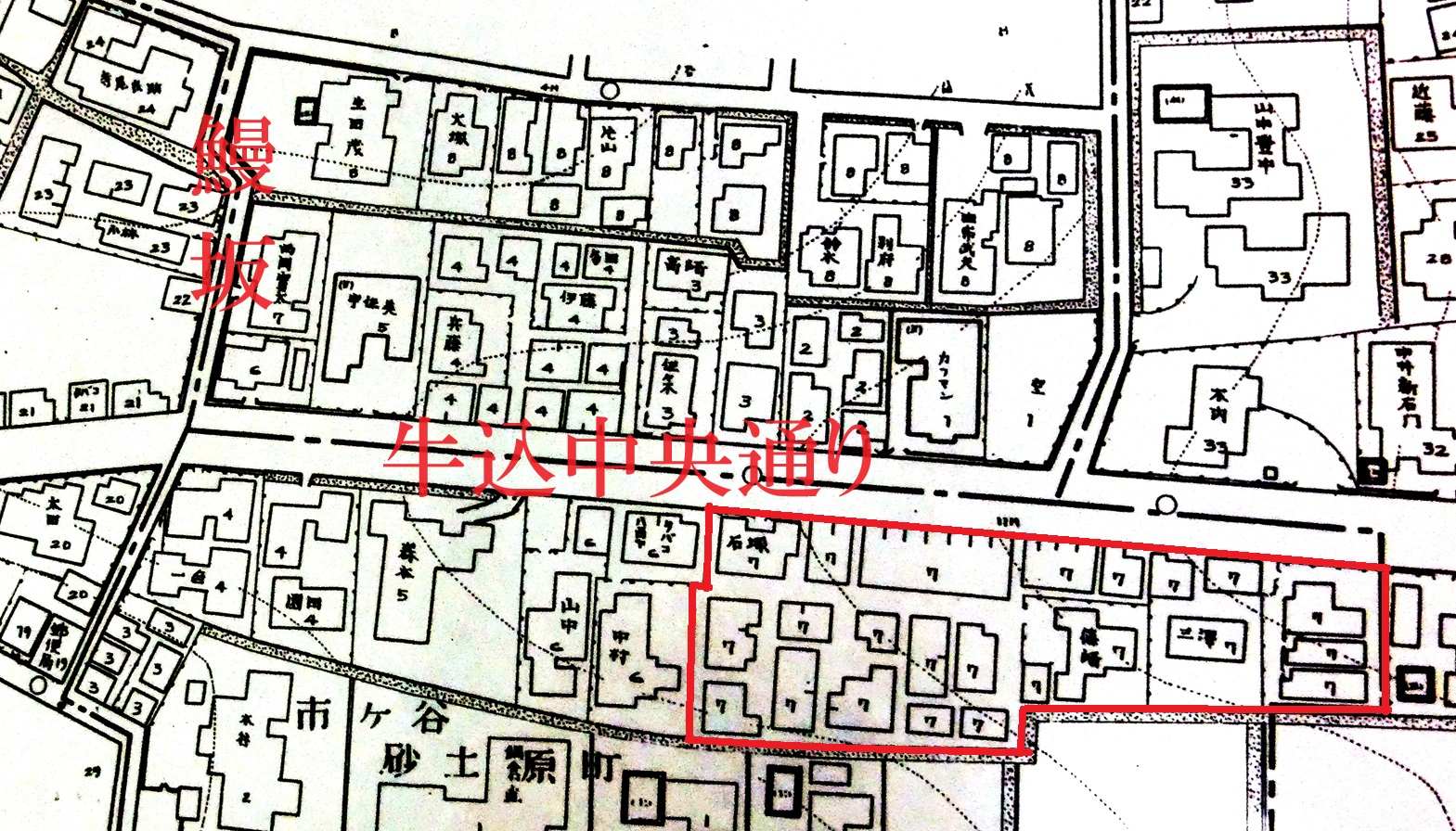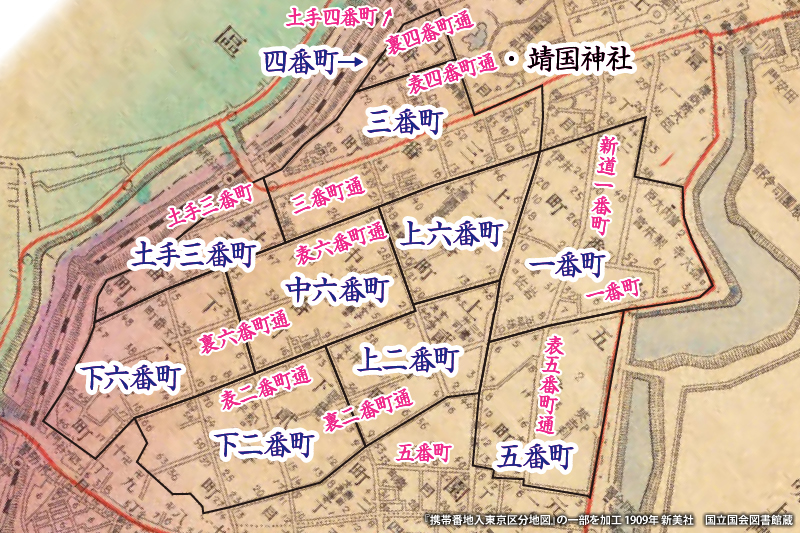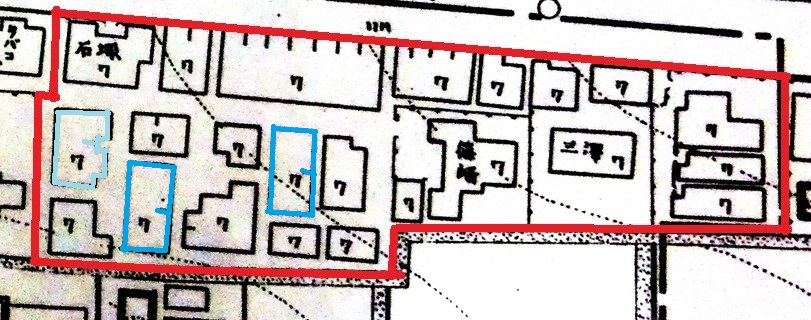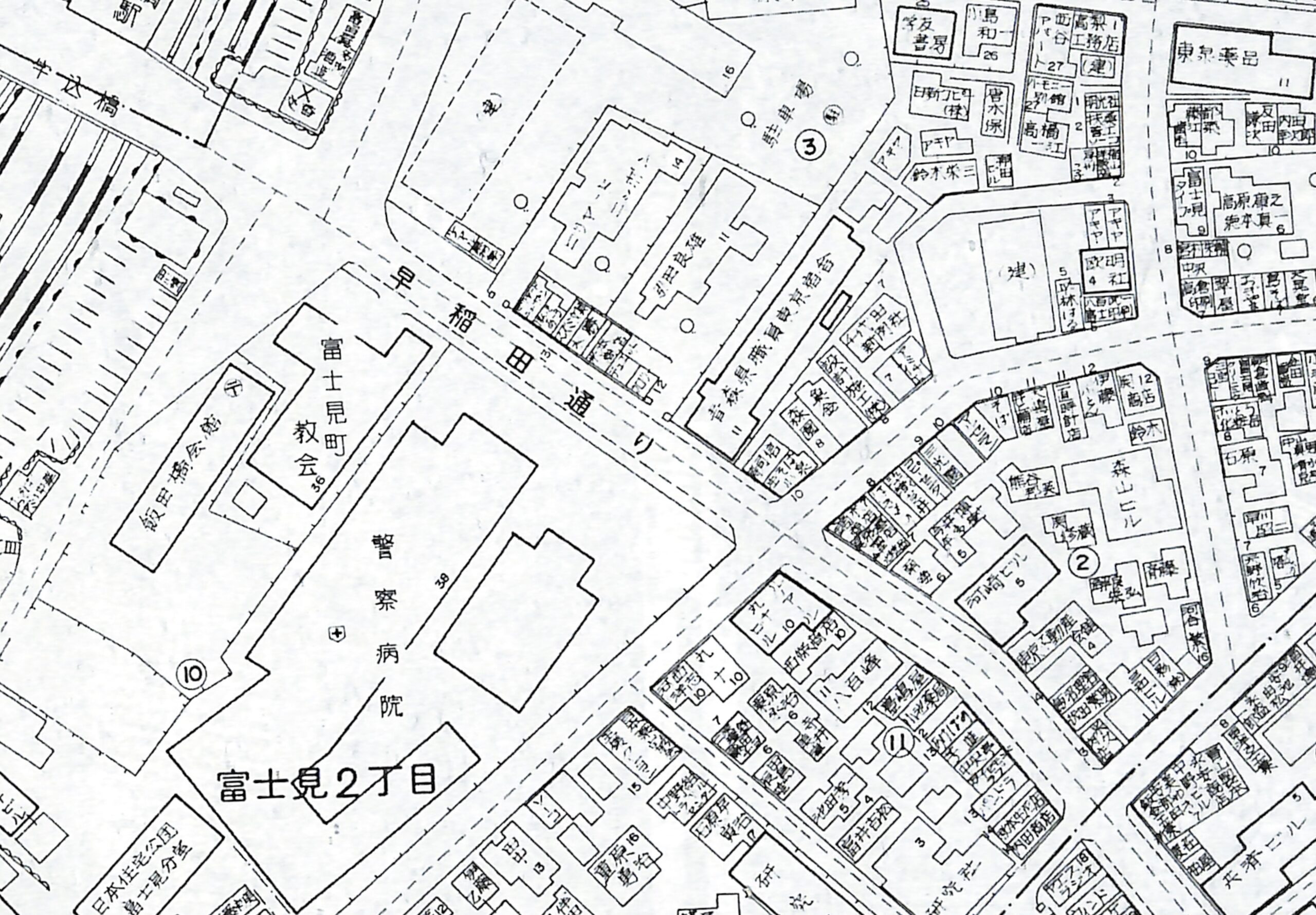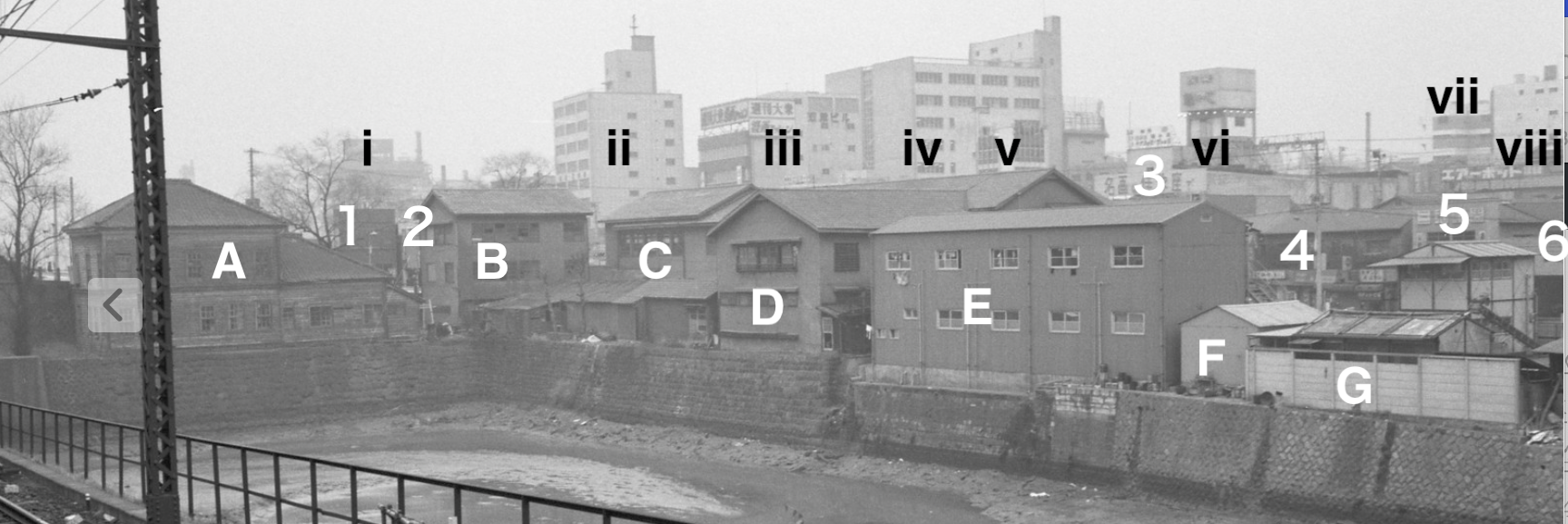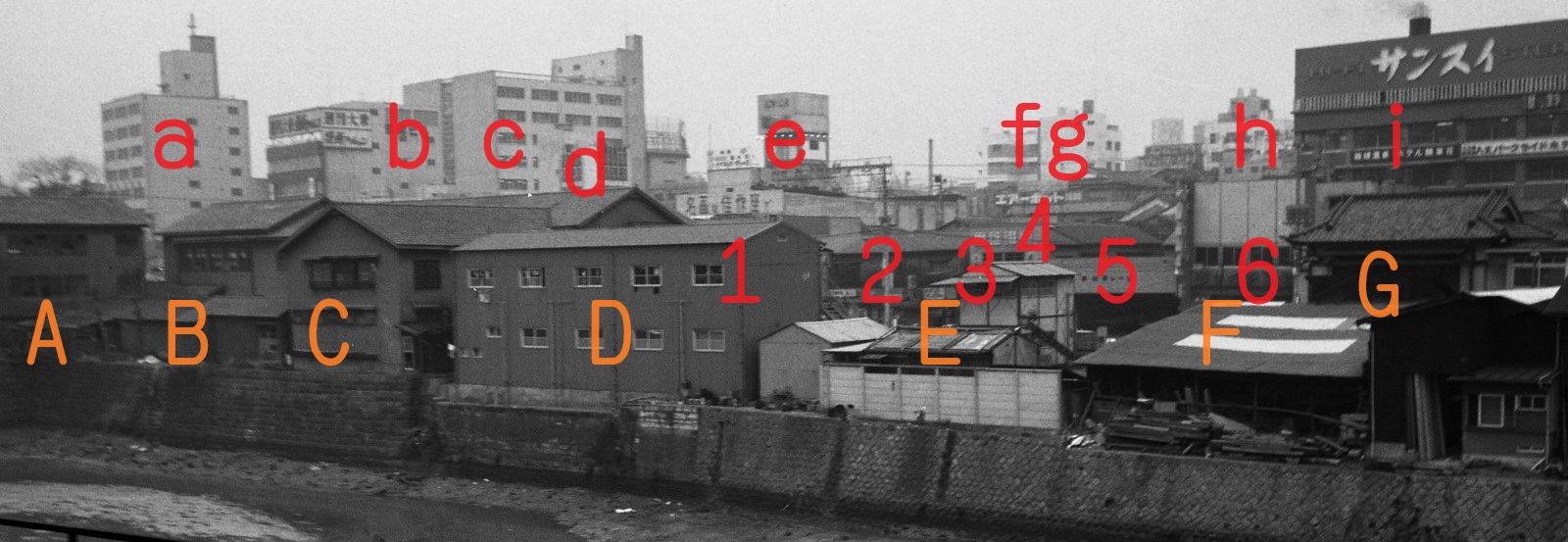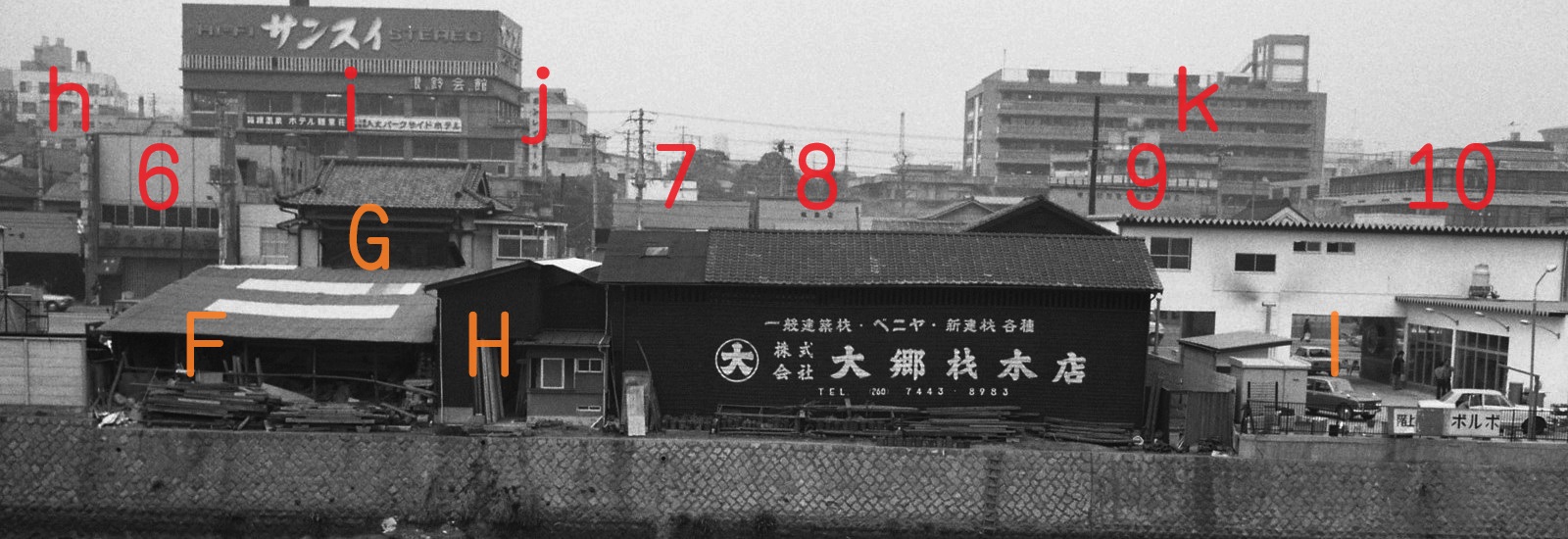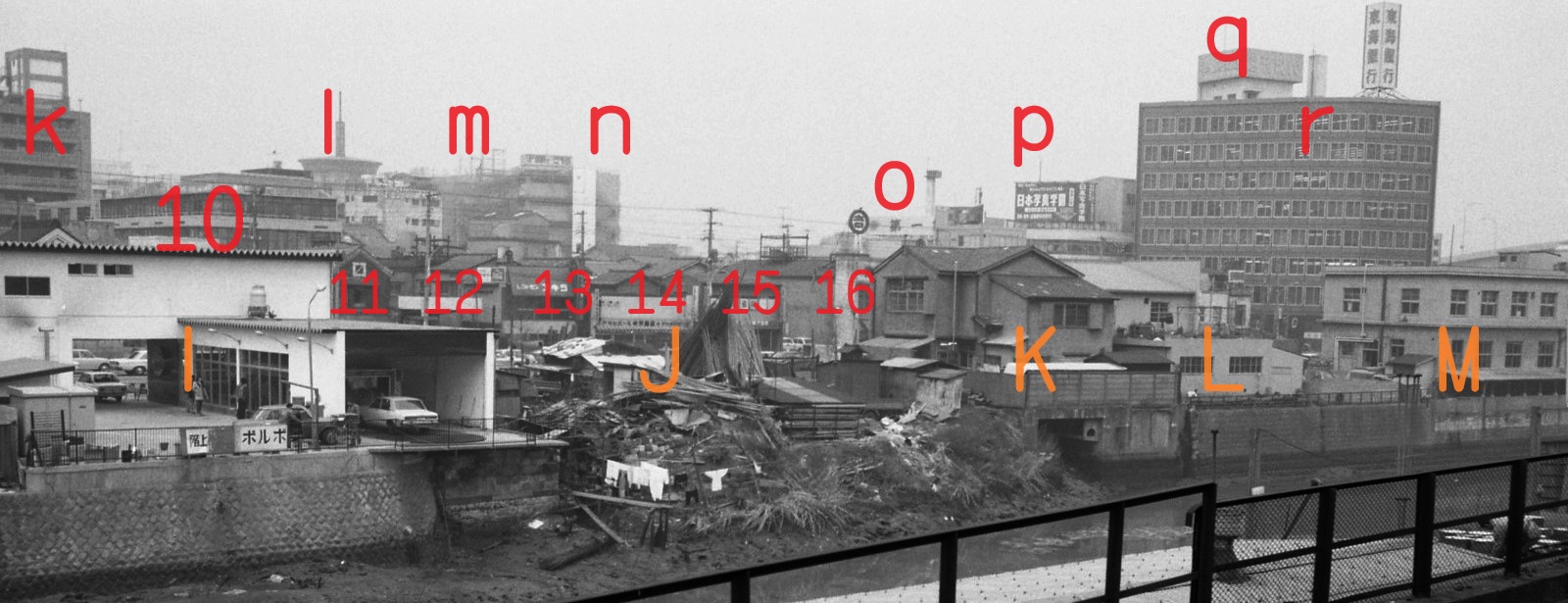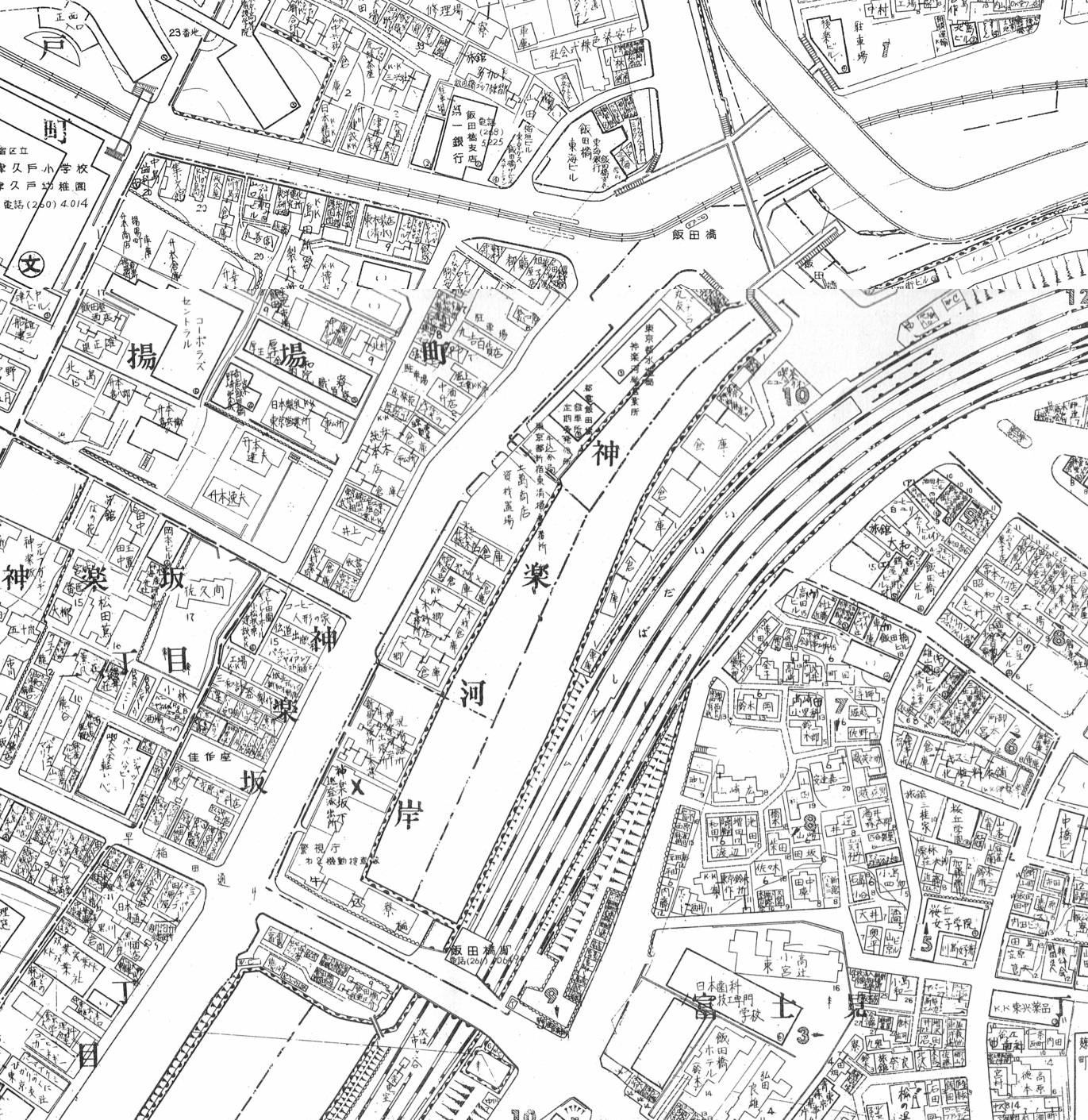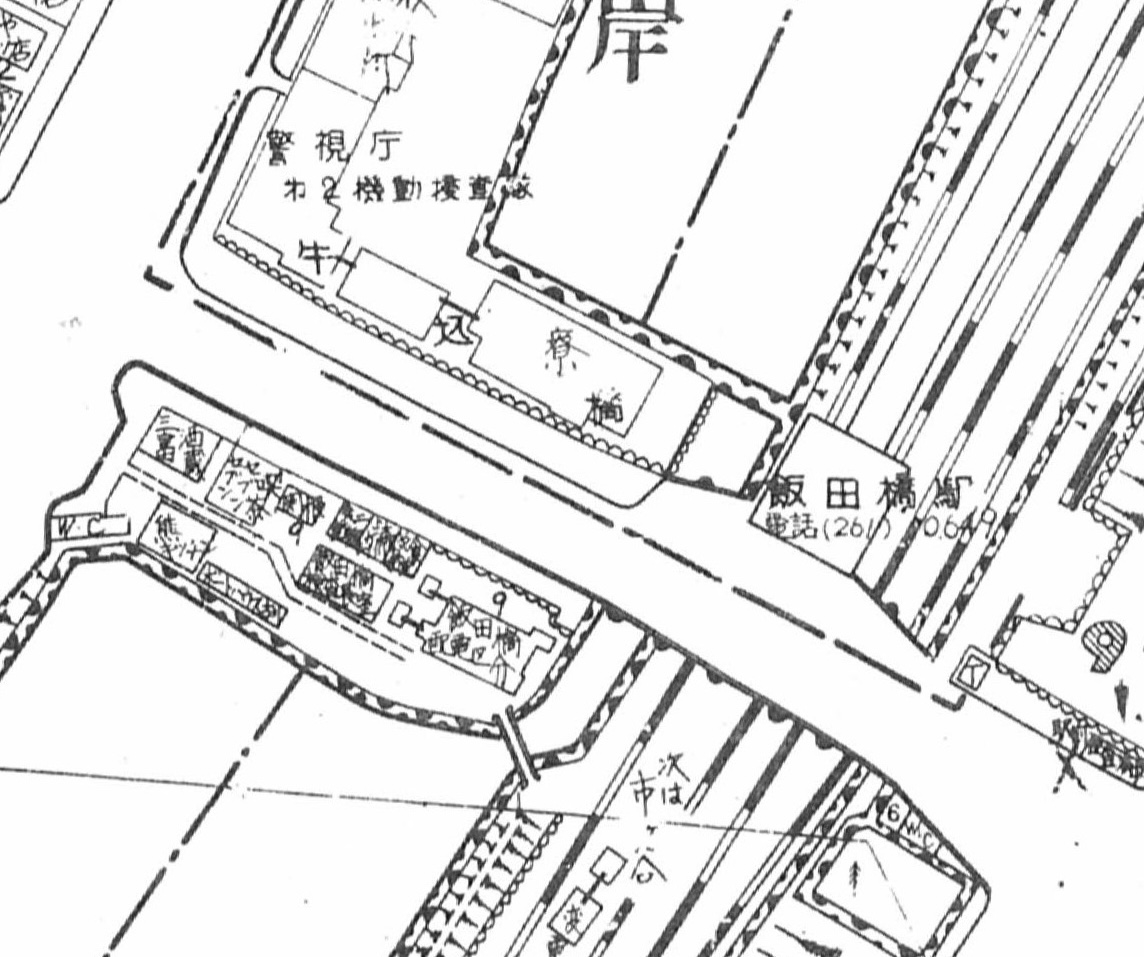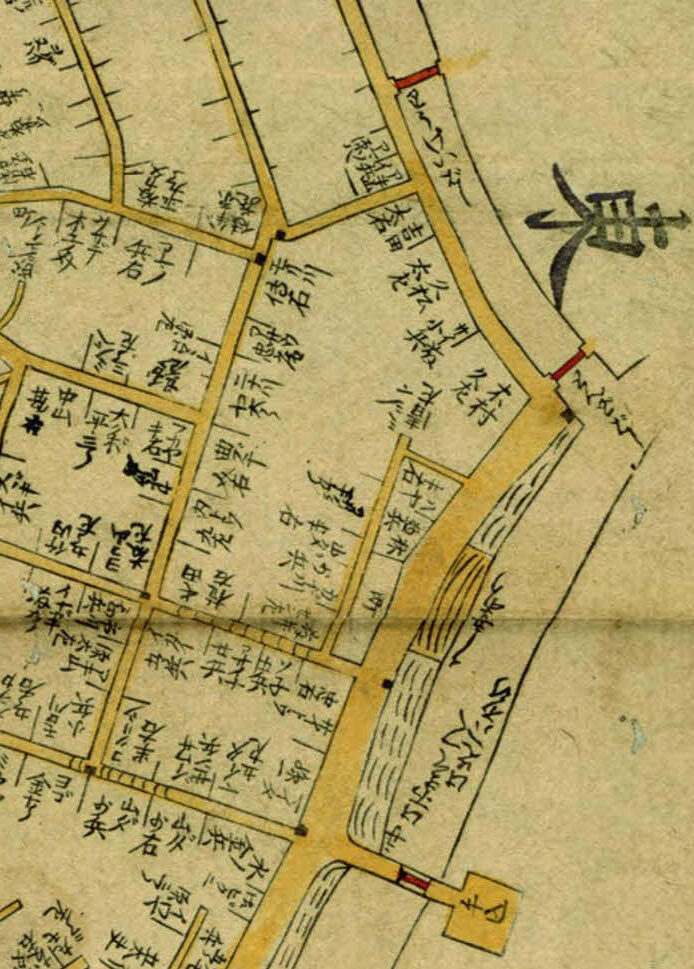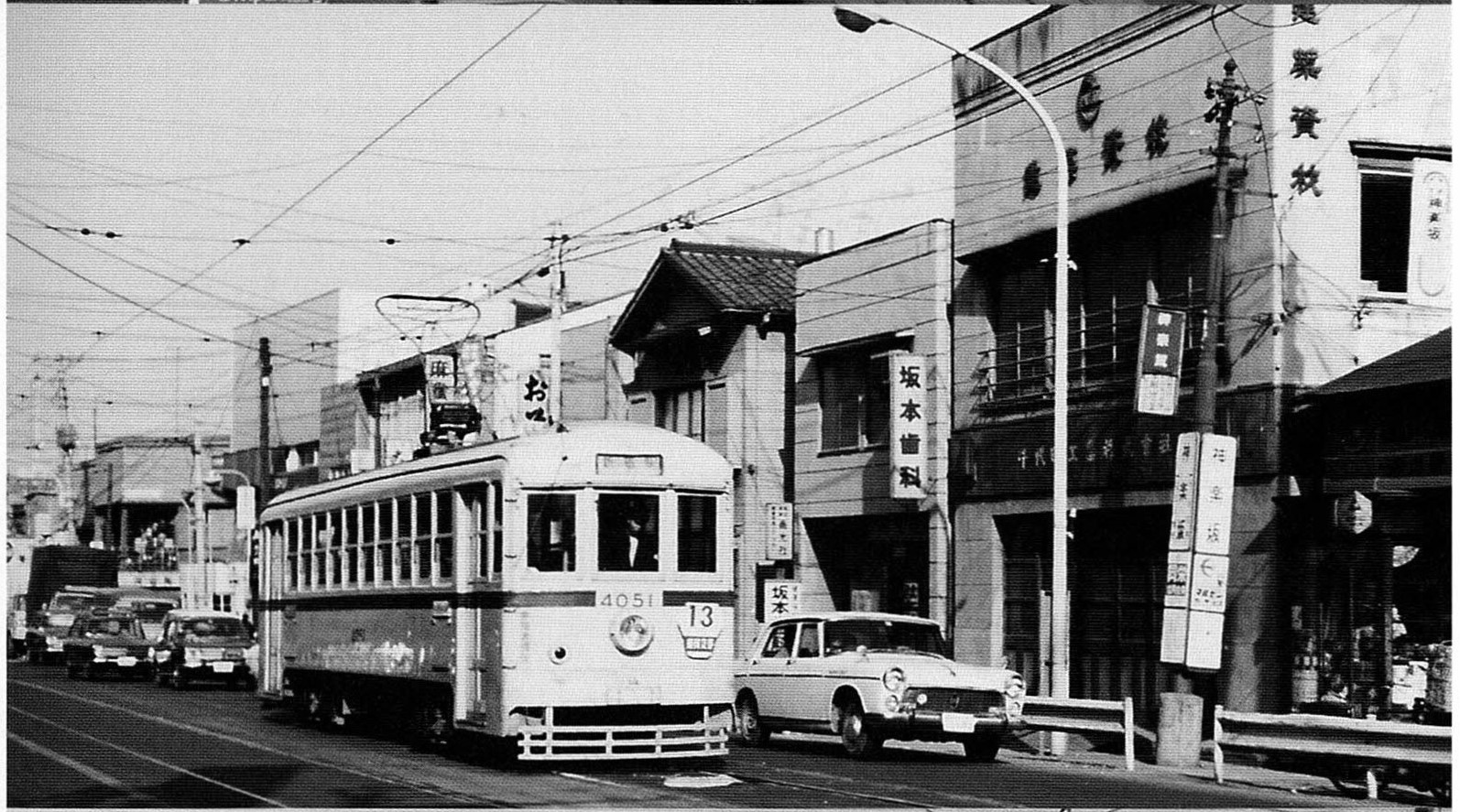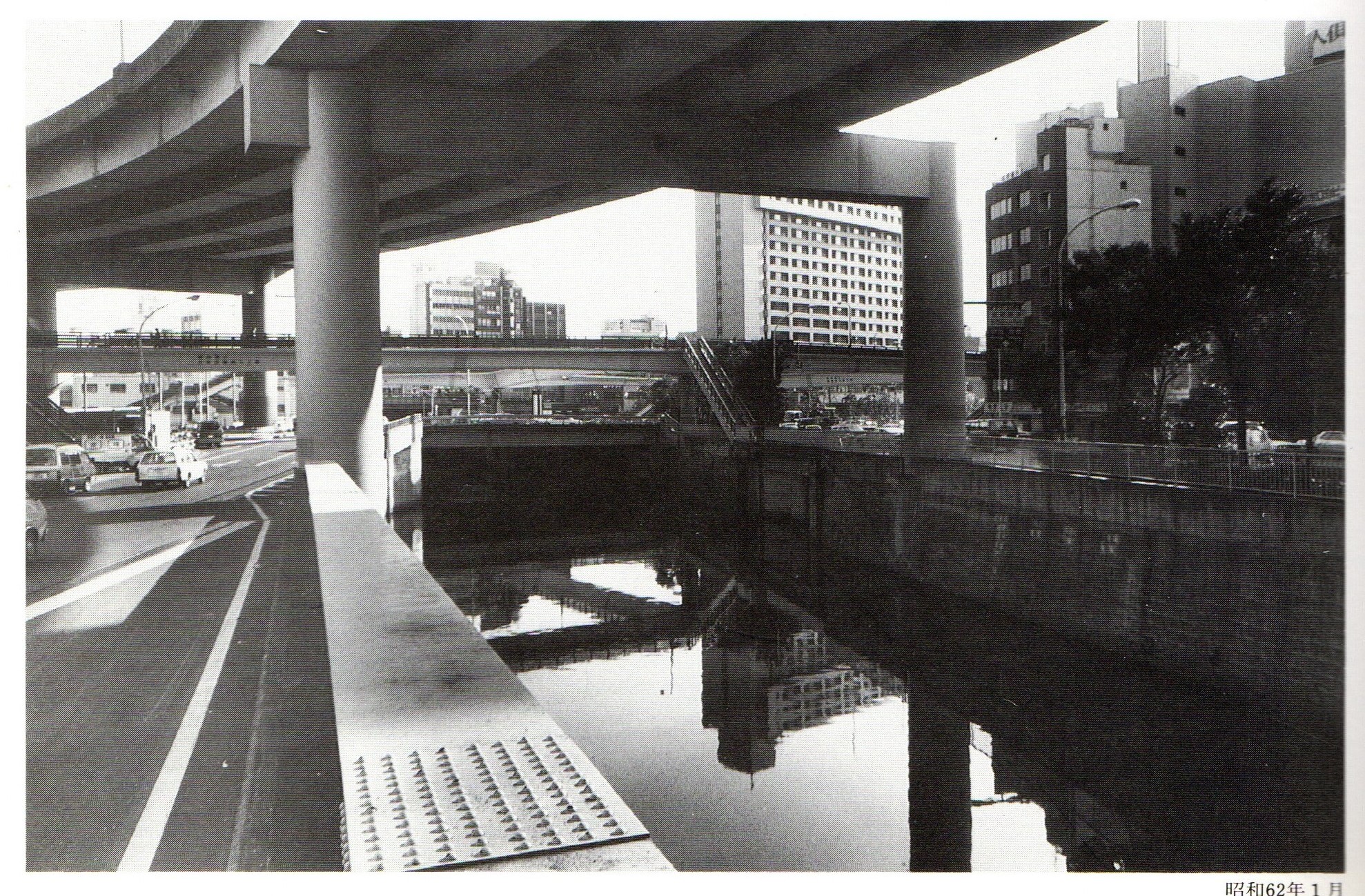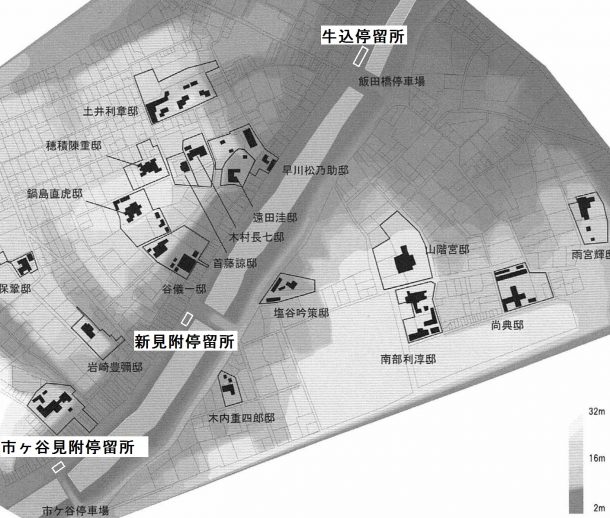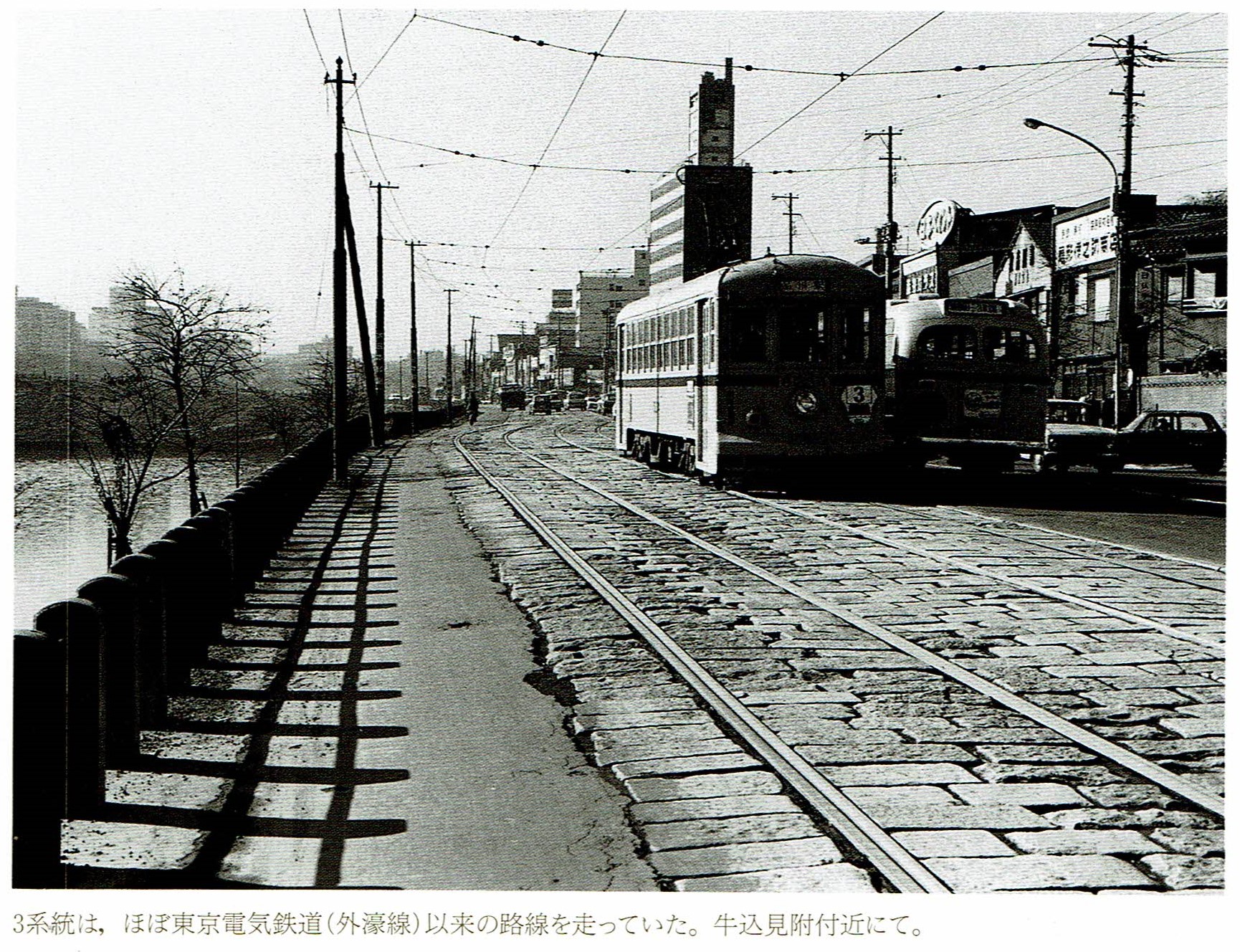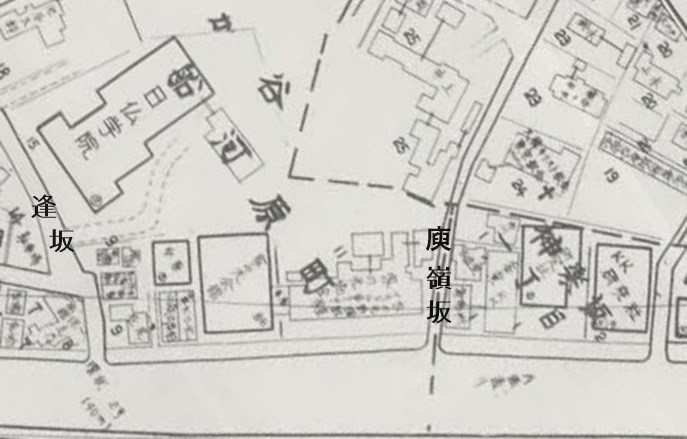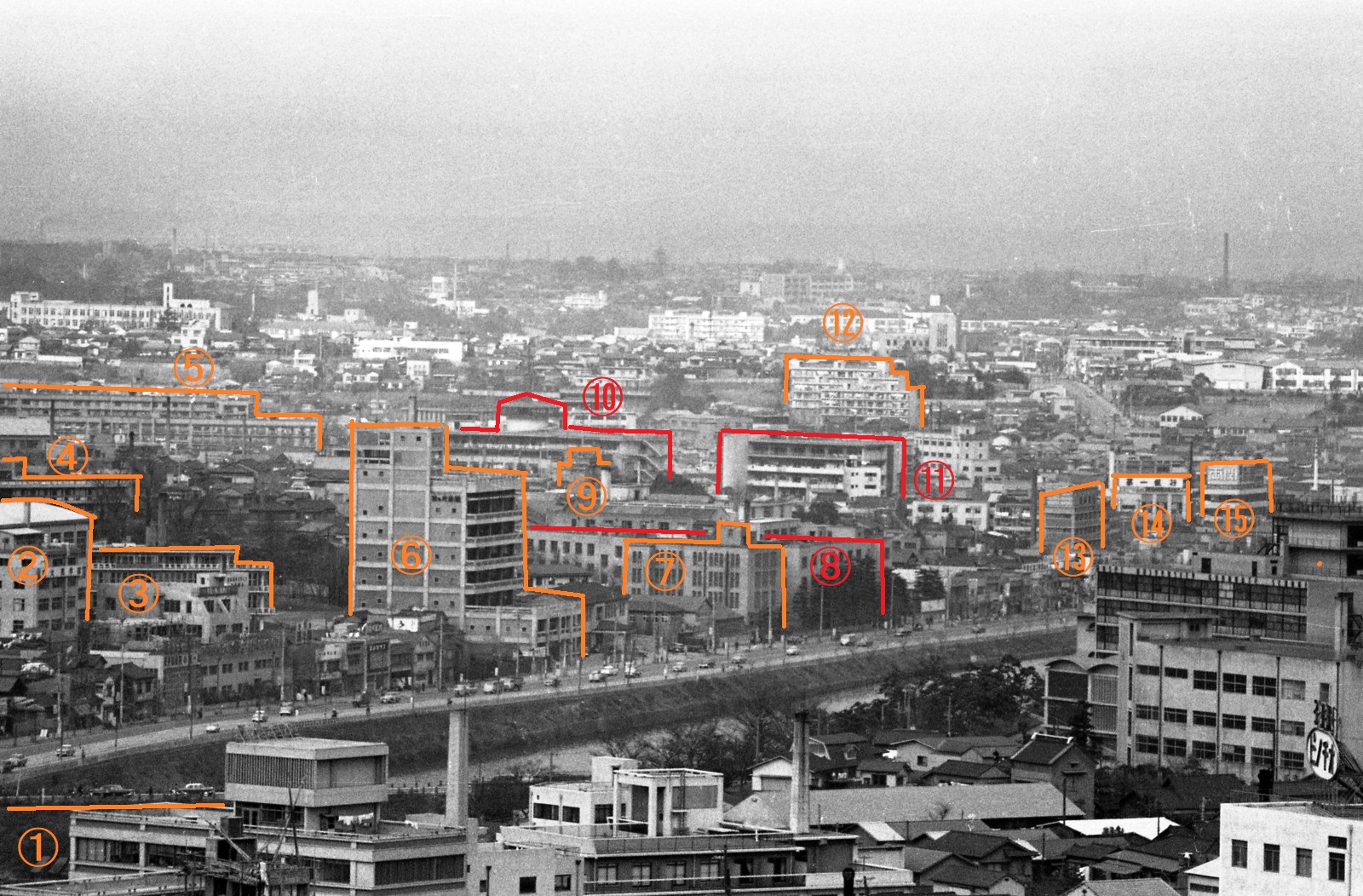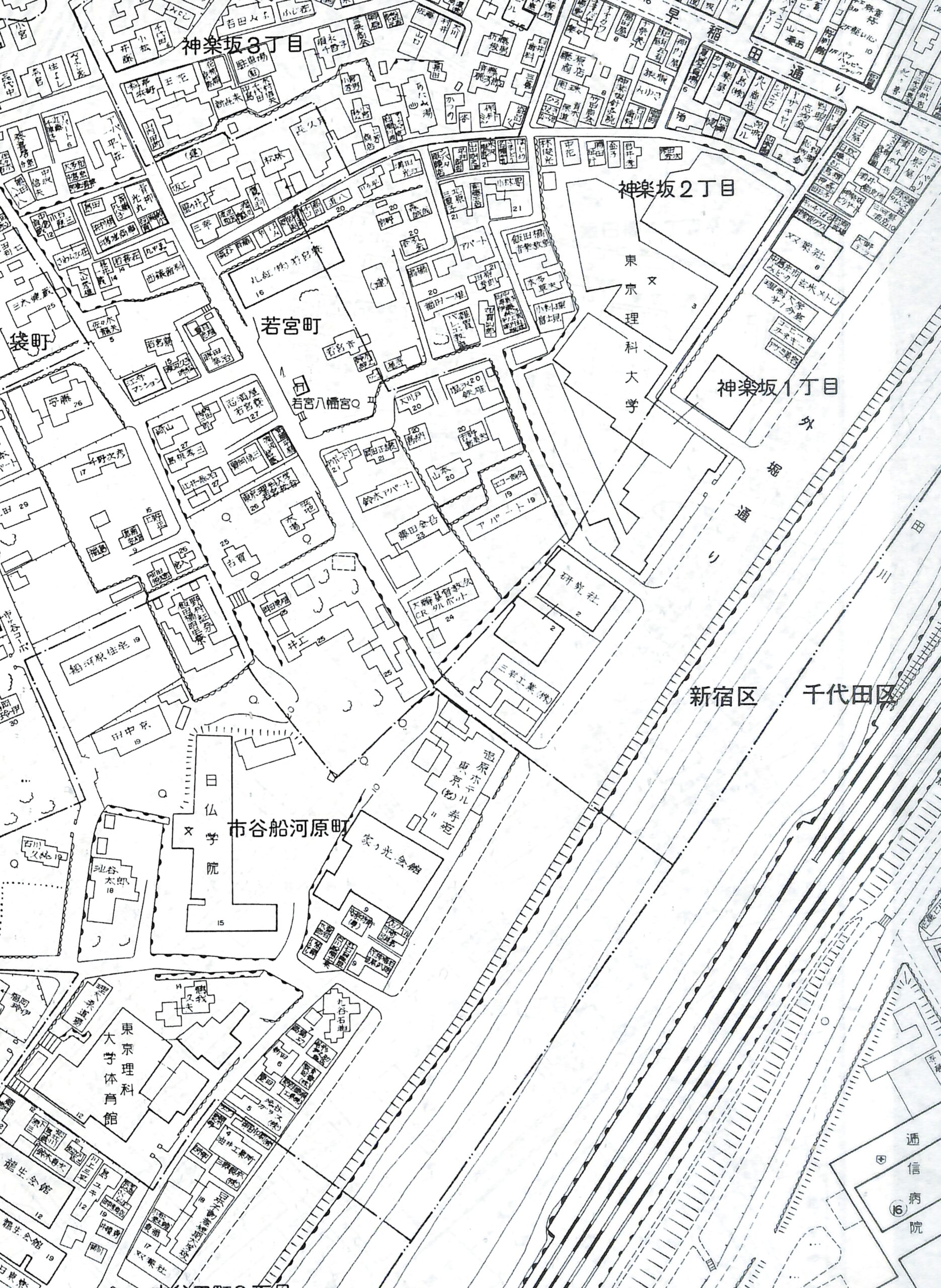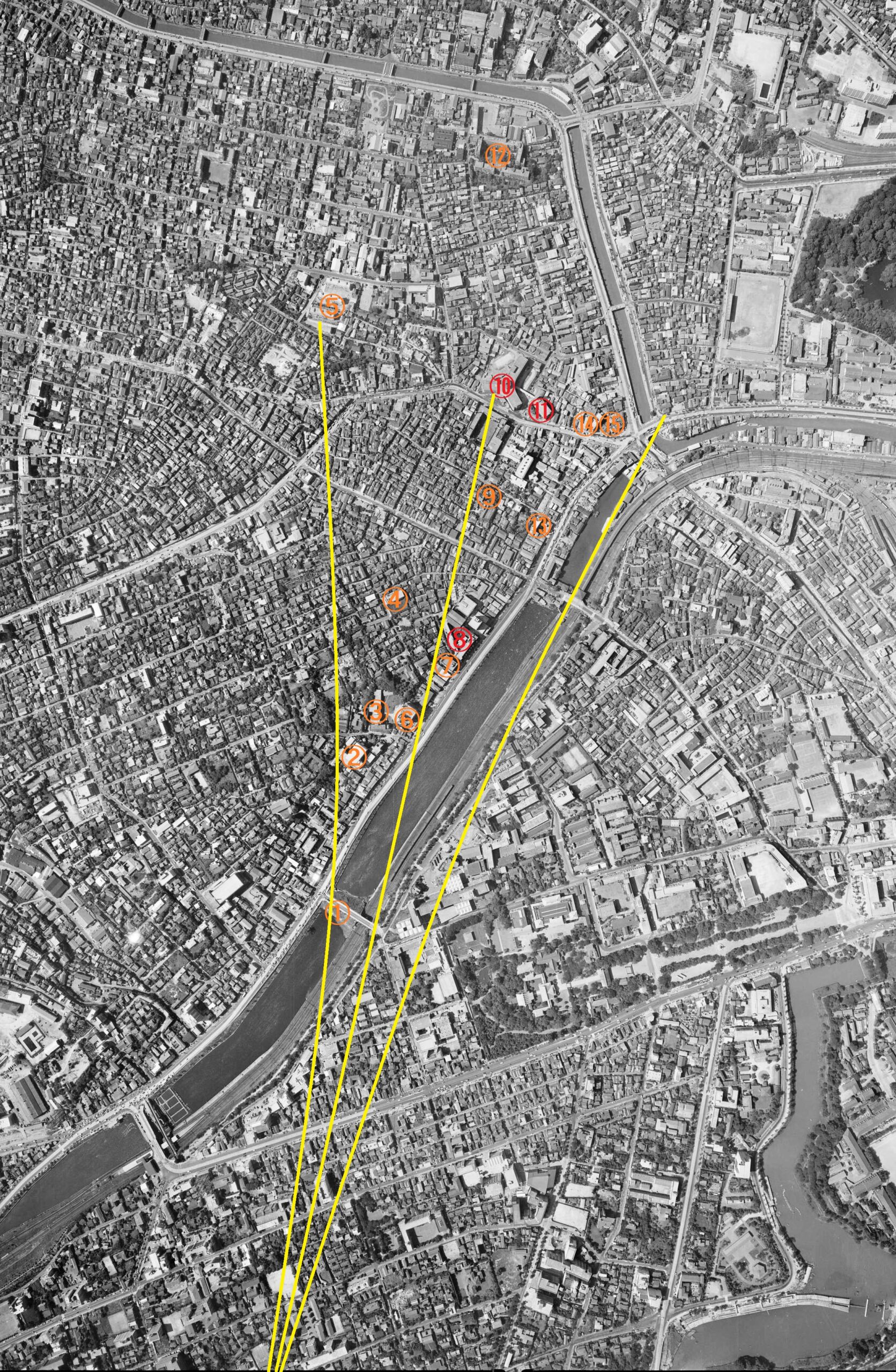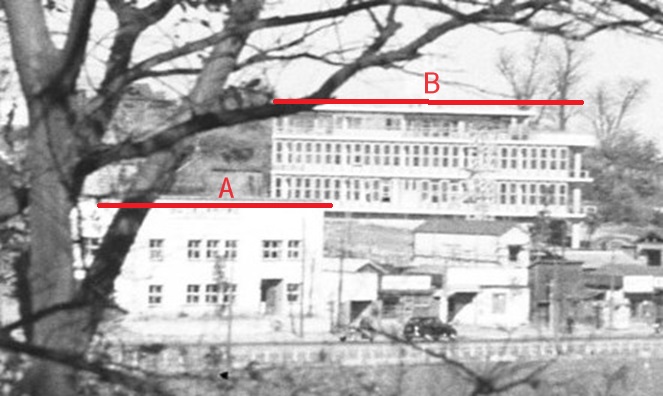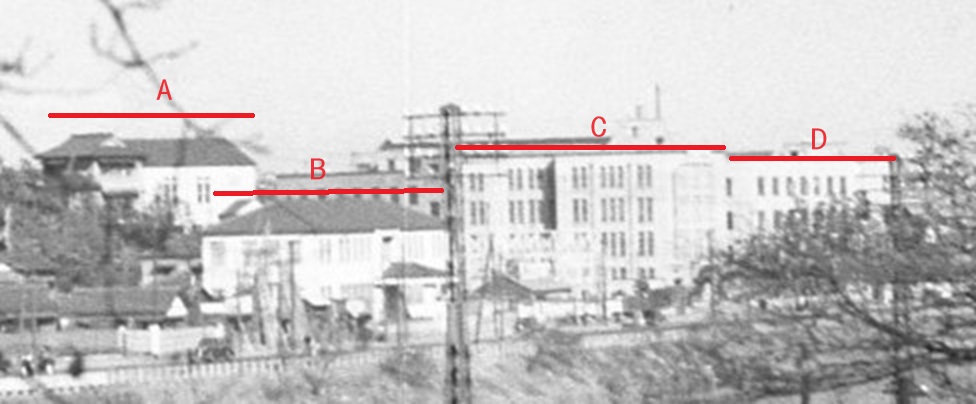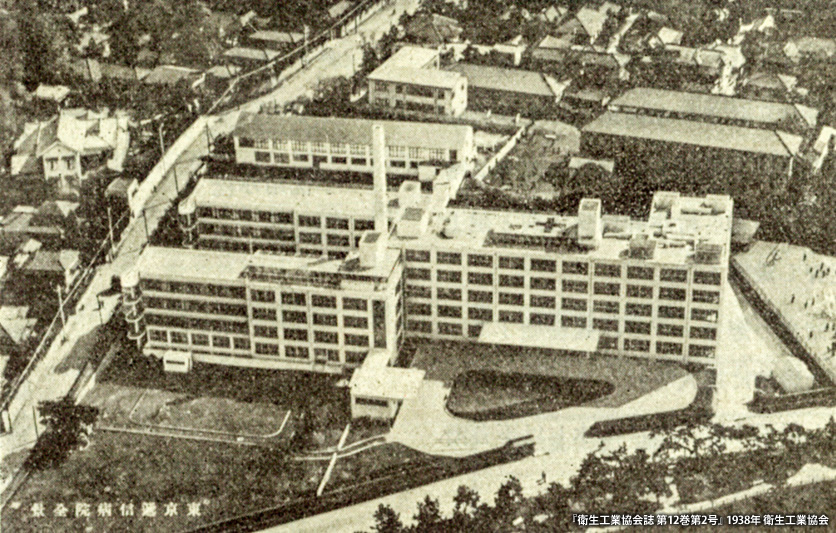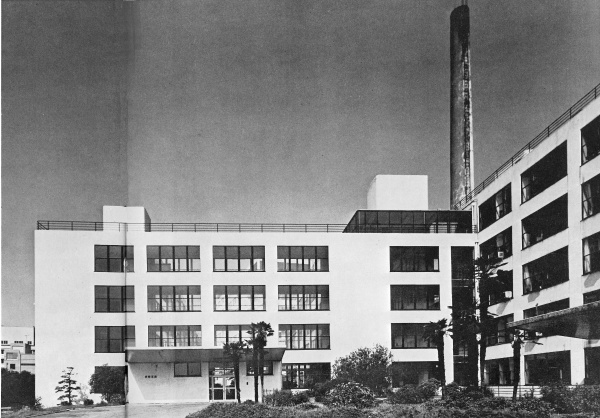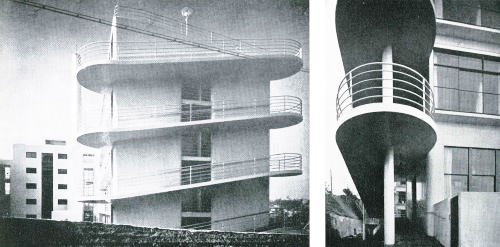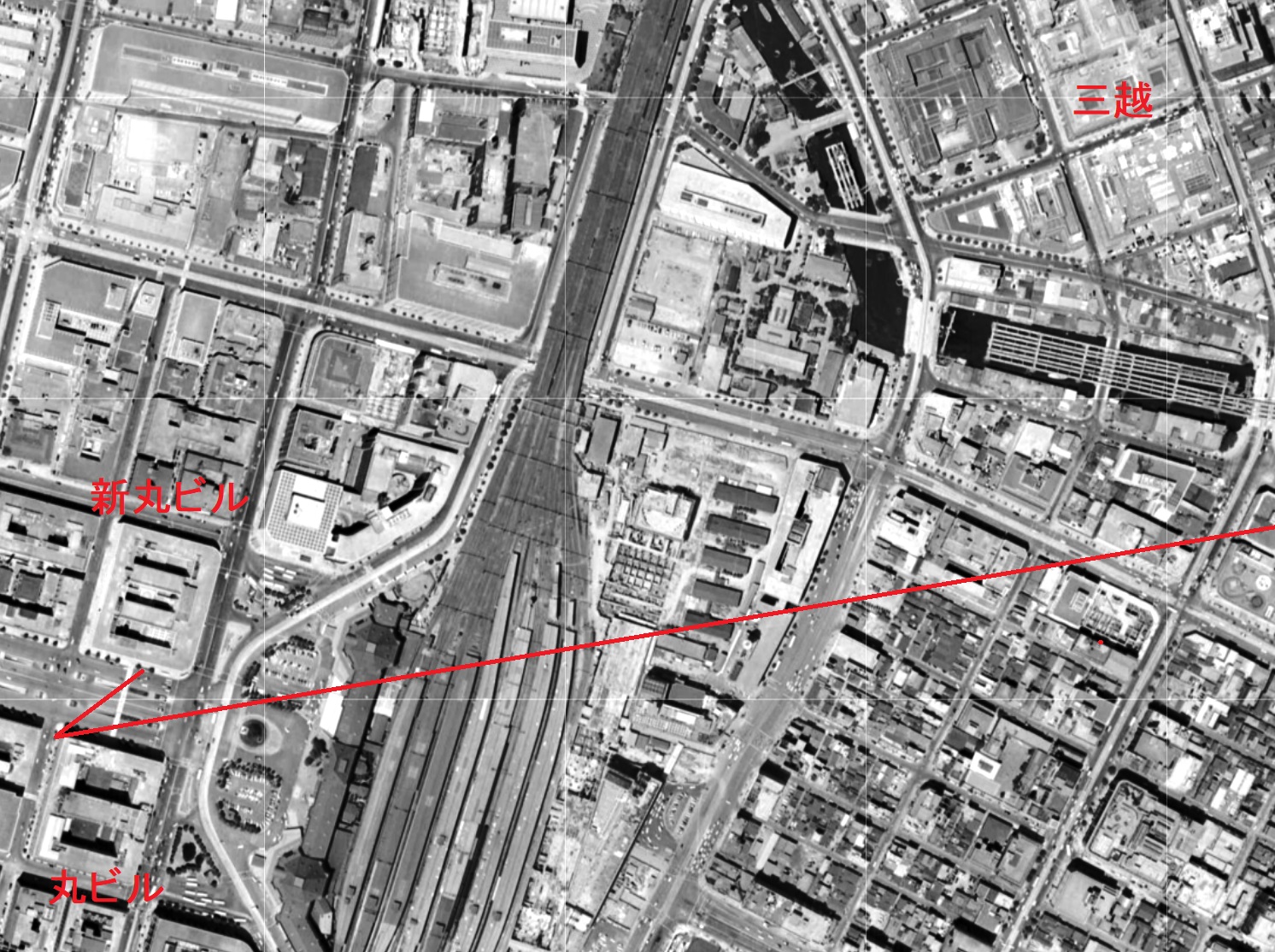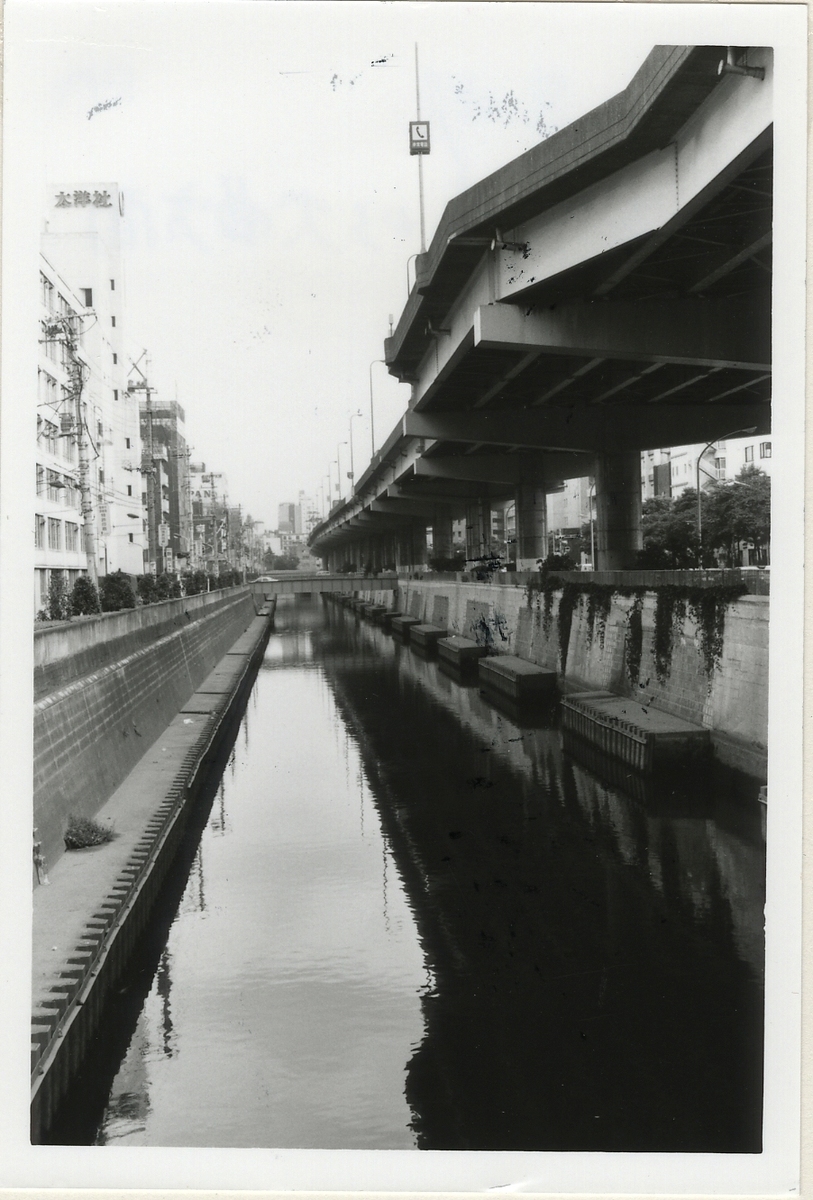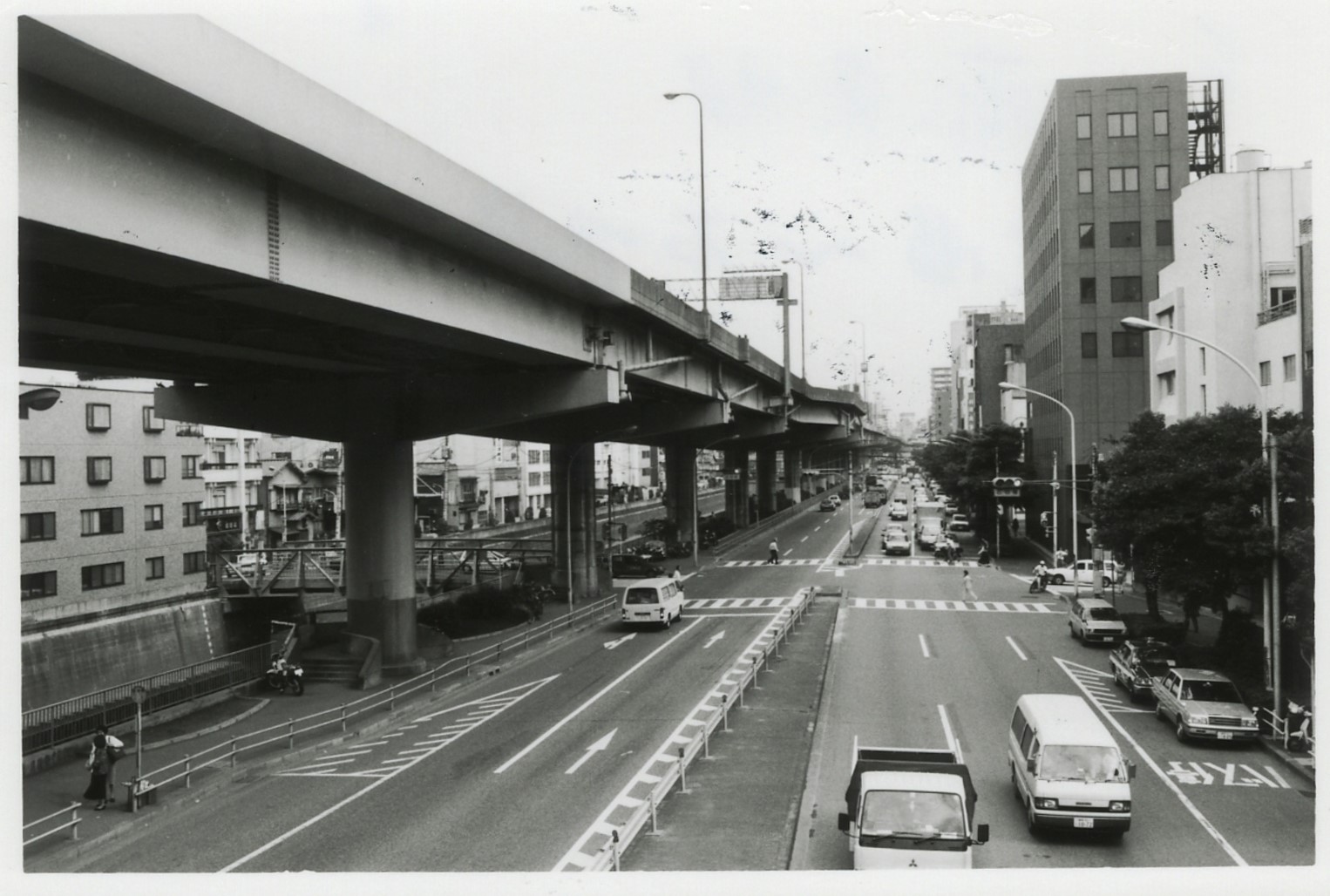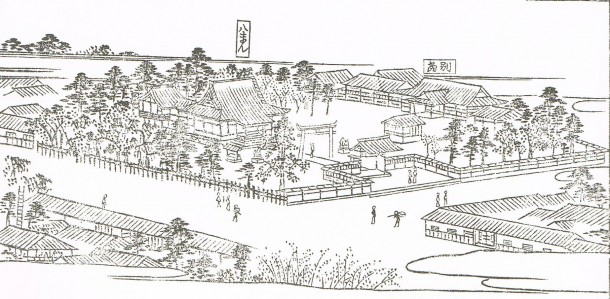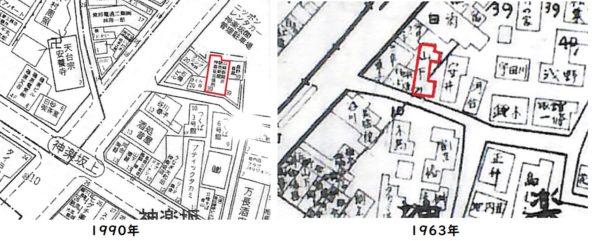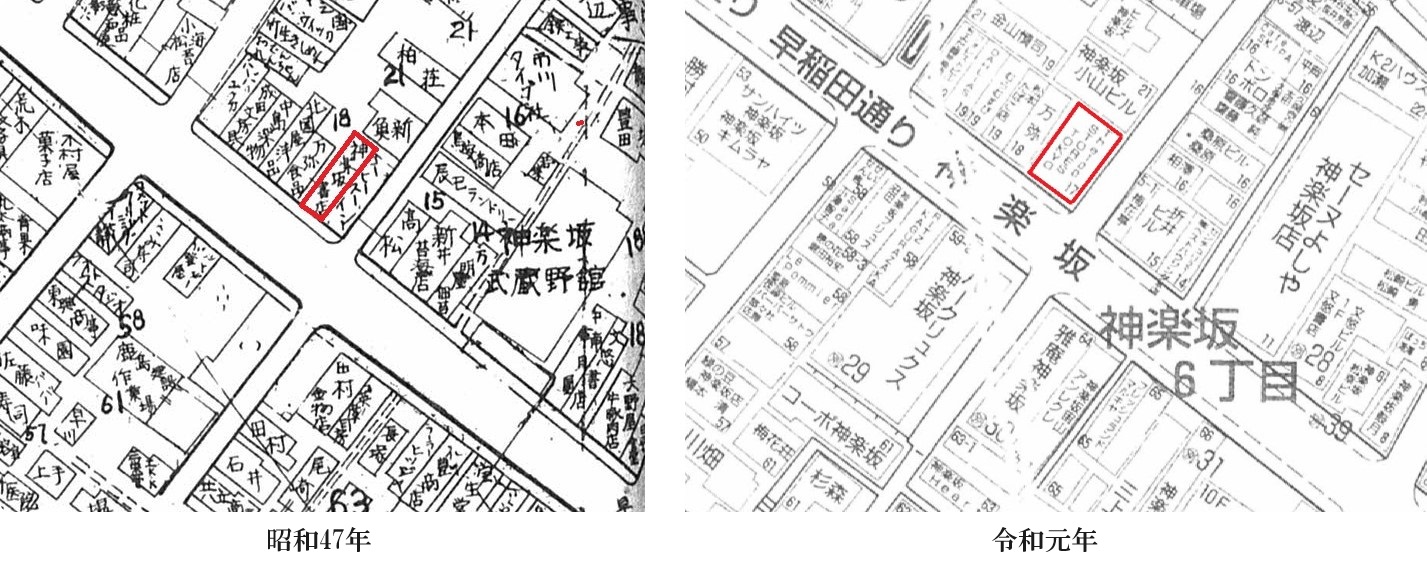神楽坂の地図と、路地、通り、横丁、小路、坂と石畳を描いてみました。
と
その名前の由来は……
軽子坂 軽子がもっこで船荷を陸揚した場所から
神楽小路 名前はほかにいろいろ。小さな道標があり、これに
小栗横丁 小栗屋敷があったため
熱海湯階段 パリの雰囲気がいっぱい(すこしオーバー)。正式な名前はまだなし
神楽坂仲通り 名前はいろいろ。「仲通り」の巨大な看板ができたので
見番横丁 芸妓の組合があることから
芸者新路 昔は芸者が多かったから
三年坂 寂しい坂道だから転ぶと三年以内に死ぬという迷信から。
本多横丁 旗本の本多家から。「すずらん通り」と呼んだことも
兵庫横丁 兵庫横丁という綺麗な名前。兵庫町とは違います
寺内横丁 行元寺の跡地を「寺内」と呼んだことから
毘沙門横丁 毘沙門天と三菱東京UFJ銀行の間の小さな路地
地蔵坂 化け地蔵がでたという伝説から
- 牛込駅
- 牛込橋
- 牛込見附(昔)
- 牛込見附(大東京繁昌記)
- 明治28年 通路新設
- 四谷・市ヶ谷の見附撤却
- 飯田河岸(中村道太郎と織田一磨)
- 停車場
- 下宮比町交差点
- 飯田橋の線路
- 牛込駅リターン
- 踏切計画
- 鉄道の複線化
- 飯田橋駅|原民喜
- 飯田橋交差点のロータリーの廃止 昭和28年
- 昭和49年 ダンディー
- ダンディー2
- ダンディー3
- 以下は写真中心(路面電車)
- 大正8年頃 飯田橋の市電
- 昭和12年 小石川区から飯田橋駅
- 路面電車 第3系統 昭和27〜42年
- 以下はJR内部
- 飯田橋駅 昭和44年 西口 ID 8267など
- 西口のビル 昭和44年
- 西口と東口のビル 昭和44年
- 以下は東口
- 昭和28年 東口 ID 13030 信号機
- 昭和41年 消防訓練 ID 12317-18
- 昭和43年 都電・飯田橋
- 昭和49年 神楽河岸 ID 8792, 8793
- 昭和51年 東口 ID 481~483
- 昭和51年 東口2 ID 480とID 494
- 水道局 昭和51年 ID 483 11459
- 昭和54年 東口
- 昭和54年 飯田橋交差点 ID 498-500, 12111
- 昭和54年 商店街 昭和54年 ID 12030など
- 昭和54年 飯田橋交差点
- 以下は西口
- 昭和44年 西口 ID 8267, 8269, 8270
- 飯田濠の近くのビル 昭和44年
- 昭和50年頃 西口 ID 9810
- 昭和50年頃 西口 千代田区 ID 9780
- 昭和50年 牛込見附 ID 9912-17
- 昭和51年 西口 埋立 ID 11468
- 以下は地下鉄
- 昭和54年 地下鉄
- 地下鉄2 s
- 昭和54年 目白通り ID 12019~22
- 昭和54年 目白通り ID 12023~36
- 昭和54年 目白通り ID 12074, 76-82
- 以下は文人から
- 野田宇太郎
- 野口冨士男
- 心の日月
- 原民喜
- 五叉路[明治市区改正](明治40年ごろ)
- 地理風俗大系 昭和12年
- 画家2人 昭和14年
- 中村道太郎と織田一磨 戦前
- 以下は写真中心
- ロータリーの廃止 昭和28年
- 昭和を走ったチンチン電車
- 下宮比町交差点
- ラムラ「ラムラの「せせらぎ」」
- ⑮飯田橋 昭和6年〜44年
- ③飯田橋 昭和27〜42年
- 神田川と船河原橋 昭和39年
- ⑬飯田橋 焼跡・都電 昭和41年
- ③飯田橋 升本酒問屋 昭和42年
- 消防訓練 昭和41年頃 ID 12317-18
- 飯田橋駅 昭和44年 西口 ID 8267など
- 西口のビル 昭和44年
- 西口と東口のビル 昭和44年
- 目白通り モリサワ 昭和44年 ID 12776-79
- 飯田橋駅 昭和48年 ID 8792など
- 飯田橋駅 昭和50年 西口 ID 652など
- 飯田橋と神田川 昭和51年 ID 479など
- 飯田橋 昭和51年 ID 495-497
- 首都高速 昭和52年 ID 12205など
- 目白通り 昭和54年 ID 12019など
- 目白通り 昭和54年 ID 12023など
- 目白通り 昭和54年 ID 12074, 76-82
- 目白通り 昭和54年 ID 12083など
- 飯田橋交差点 昭和54年 ID 498-90, 12111
- 飯田橋交差点 昭和54年 ID 12104
- 地下鉄 昭和54年 ID 642など
- 飯田橋駅 昭和54年 東口 ID 652など
- 飯田橋交差点 平成元年 ID 508
- JR飯田橋駅 令和4年 ID 17577
- 荷揚
- 広重
- 寒泉精舎 ID 17975
- 升本
- 地名考
- 浮世絵
- 江戸
- 明治
- 石黒忠悳
- 看護婦養成
- 医師荻野吟子 明治12年
- 軽子坂と揚場町の同居
- 柿の木横町
- どんどん橋
- むらさき鯉
- 船河原橋と蚊屋が淵
- 升本総本店(前後)
- 神楽河岸 松沢光雄 昭和43年
- 悪臭漂う飯田濠
- ラムラの「せせらぎ」
- 以下は写真中心
- 神楽坂下交差点 昭和37年 昭和43年 昭和44年 昭和46年
- 路面電車 升本酒問屋 昭和42年
- 加藤嶺夫氏 昭和46年
- 飯田橋駅東口 ID 475 481~483 11457 12190 昭和51年
- 駅東口2 ID 480 11455 494 11469 昭和51年
- 河岸埋立 ID 493 537 539 540 543 昭和51年
- 失われた新宿区 ID 484 478 11477 12204 昭和51年
- 神楽河岸 ID 474 11456 12189 昭和51年
- 千代田区 神楽河岸埋立 昭和51年 ID 11468
- 歌川広重団扇絵
- 神楽坂警察署
- 町名はいつから
- 悪臭漂う飯田濠
- ラムラの「せせらぎ」
- すっかり観光地な
- 以下は写真中心
- 飯田堀 昭和27年頃 ID 16566
- 池田信 昭和40年頃
- 松沢光雄 昭和43年
- 濠近くのビル 昭和44年
- 濠近くのビル 昭和44年
- 加藤嶺夫 昭和46年
- 飯田堀 昭和48年頃 ID 8792-93
- 駅東口 昭和51年 ID 475 481-83 11457 12190
- 神楽河岸 昭和51年 ID 474 11456 12189
- 神楽河岸埋立 昭和51年 ID 493 537 539-40 543
- 千代田区 埋立 昭和51年 ID 11468
- 駅東口2 昭和51年 ID 480 11455 494 11469
- 水道局 昭和51年 ID 483 11459
- 以下は戦前
- 1丁目
- 牛込駅
- 牛込見附(昔)
- 由来
- 大下水
- 牛込門以前
- 神楽坂下の五叉路案
- 牡丹屋敷(昔)
- 赤井(昔)
- 寿徳庵(昔)
- 紀の善|寿司屋時代
- わが青春の記
- ガス灯(昔)
- 小栗横丁
- 神楽小路
- 庾嶺坂
- 新坂橋
- 以下は道路と駅
- 飯田橋駅東口
- 飯田橋駅東口2
- 外堀通り
- ボート場
- 梟林漫筆 内田百閒
- 以下は店舗
- 翁庵
- のレン
- 不二家
- 紀の善
- 紀の善の閉店
- しんぱち食堂
- 紀の善の柳
- 神楽坂の立廻り
- 東京ワンタン本舗
- 1丁目+森川ビル
- 昭和42年 六さんの途中下車
- 記憶の中の神楽坂1
- 気まぐれ本格派(1)
- 三沢氏 変化40年(1)
- 変化40年(2)
- 変化40年(3)
- 2度目の事態宣言
- あの頃の神楽坂
- 以下は写真中心(交差点と外堀通り)
- 昭和6年 日本地理風俗大系 ボート乗り場
- 昭和29年頃 ID 14048
- 昭和33年? 夜景 ID 13505
- 昭和34年 夜景 芸者 ID 31-35
- 昭和34年 夜景 タワー ID 59-63
- 昭和35年頃 地元の方 ID 5510, 7002, 9109
- 昭和35年頃 地元の方 ID 5510, 7002, 9109
- 昭和43年 庾嶺坂 ID8016
- 昭和43年 警視庁と三富 ID8017
- 昭和48年 入口 ID 65
- 昭和51年 地下鉄 ID 69-71
- 令和元年 ID 13298
- 令和4年 ID 17576
- 以下は写真中心(1丁目)
- 明治中期 赤井足袋 ID 7640-7641
- 昭和10年代 神楽坂通り ID 1
- 昭和28年頃 ID 5190
- 看板 思い出 地元の方 4枚
- 昭和34年 夜景 着物 ID 40-45
- 昭和36年 外濠
- 昭和36年 鈴蘭灯 と 37年 蛍光灯
- 昭和36年頃 山田紙店 ID 54
- 昭和37年 神楽坂 ID 17-19
- 昭和41年 美観街× 「坂のある街」歩道の文様○
- 昭和41年 美観街○ ID 7658 歩道の文様×
- 昭和45年 ID 13198 外濠公園から
- 昭和48年 入口 ID 8801~ID 8804
- 昭和48年 地下鉄の掘削
- 昭和49年 ダンディー
- 昭和50年 山田紙店 ID 9781
- 昭和50年頃 外堀通り ID 9780
- 昭和51年 研究社 ID12201-03
- 昭和51年 研究社 ID11484-86
- 昭和54年 美観街○ ID 85、ID 86
- 昭和54年 外堀 ID 93
- 昭和54年 外堀 ID 94
- 平成2年
美観街ID 95 - 牛込橋
- 昭和5年頃 見附 ID 9378
- 昭和6年 ID 2
- 昭和20年代 ID 21, 23
- 昭和35年頃 牛込見附と山田紙店 ID 47-50
- 昭和36年頃 ID 52-53
- 昭和36年頃 ID 12125~27
- 昭和37年 桜の木 ID 55と56
- 昭和37年頃 桜の木 ID 5993~5955
- 昭和44年 駅内と警視庁 ID 8267, 8269, 8270
- 昭和44年 西口→交差点 ID 8283
- 昭和45年 外濠公園から ID 13198
- 昭和45年 西口→交差点 ID 13117+4枚
- 昭和45年 西口→交差点 ID 13126+1枚
- 昭和45年 地下鉄工事中 ID 64
- 昭和48年 地下鉄工事中 ID 8799
- 昭和48年 石畳の牛込橋 ID 67
- 昭和49年 石畳の牛込橋 ID 8791
- 昭和48年 交差点→ ID13158
- 昭和50年 ID 9808~9809
- 平成7年 ID 16074
- 平成23年 ID 16075
- 平成31年 ID 14049
- 令和元年 ID 13318
- 2丁目
- 志満金
- オザキヤ靴店
- 食堂トレド
- 千年こうじや
- 梅花亭
- 陶柿園
- 神楽坂写真館
- 肉のますだや
- 太陽堂
- アグネスホテル
- ギンレイ
- 泉・北原の旧居跡
- 2丁目のどこ
- 軽い心(昔)
- メトロ映画(昔)
- ユレカ(昔)
- パウワウ(昔)
- 広津氏の神楽館(昔)
- 神楽館(昔)
- 三孫質店(昔)
- 銀扇(昔)
- 大逆事件(昔)
- 神楽小路の池(昔)
- 神楽坂仲通り
- 神楽坂仲坂
- 小栗横丁
- 神楽坂通り(2丁目北西部)
- 上村一夫
- 上村一夫と神楽坂
- 記憶の中の神楽坂1
- 三沢氏 変化40年(1)
- 変化40年(2)
- 変化40年(3)
- あの頃の神楽坂
- 以下は写真中心
- 大正10年 お祭り
- 大正期の神楽坂通り
- 昭和27年 通り ID 28-30
- 昭和27年 ID 29とID 5081
- 昭和28年頃 ID 5190
- 昭和28年頃 七夕? ID 9506
- 昭和32年 大東京祭パレード
- 昭和33年 大島ビル
- 昭和33年 メトロ映画
- 昭和34年 芸者
- 昭和34年 芸者
- 昭和35年頃 地元の方 ID 5510, 7002, 9109
- 昭和36-37年 2つの街灯
- 昭和37-9年 Oリング ID12911
- 昭和37-9年 ポーラ化粧品 ID 13, 12912
- 昭和37-9年 クラウン ID 5, 12913
- 昭和37-9年 ニューイトウ ID 4, 12914
- 昭和37年 通り ID 17-19
- 昭和37-40年 ID 11と16
- 昭和40年以前 ID 8-12
- 昭和41年 美観街なし 「坂のある街」歩道の文様あり
- 昭和41年 美観街あり ID 7658
- 昭和42年 ID 6-7
- 昭和48年 牛込見附 ID 8801
- 昭和48年 入口 ID 8801~ID 8804
- 昭和48年 十奈美 ID 8805~ID 8806
- 昭和49年 ダンディー
- 昭和50年 大島歯科 ID 9778
- 昭和50年 山田紙店 ID 9781
- 昭和50年 さわや ID 9782
- 昭和54年 ビクターレゴ―ド ID 11869
- 昭和54年 志満金 ID 11871
- 3丁目
- 歴史
- 神楽坂之図碑
- 牛込神楽坂之図
- 伏見火防稲荷神社
- 明治26年 見番横丁
- 神楽坂仲通り
- 松平定安邸
- 出羽様下 再考
- 神楽坂仲坂
- 毘沙門横丁
- 万平の柳
- 菱屋
- きらく会館
- 龍公亭
- 助六
- 丸岡陶苑
- ヤマダヤ
- 椿屋
- ジョウトーヤ
- 三菱銀行神楽坂支店
- 熊公焼(昔)
- 春月(昔)
- 寿司作(昔)
- 魁雲堂(昔)
- 思い出|川村克己
- 木村屋(昔)
- 二葉(昔)
- 牛込会館(昔)
- 演芸場(昔)s
- 盛文堂(昔)
- 五十番(昔)
- 神楽坂通り(3丁目北西部)
- 神楽坂通り(3丁目南東部)
- 見番横丁
- 熱海湯階段
- 本多横丁
- 本多横丁の路地
- 大銀杏
- リンゴ
- 千寿(昔)
- 御旅所(昔)
- 「ほてや」と「ほていや」
- ほてや談
- 記憶の中の神楽坂2
- 珍味堂
- 松平定安邸
- 5つ子
- あの頃の神楽坂
- 以下は写真中心
- 昭和7年 ID 96
- 大正と昭和8年
- 昭和7年 ID 96
- 昭和12年(写真)
- 昭和27年 東京文学散歩
- 昭和27年 ID 4792-94
- 昭和28年 坂下から ID 99
- 昭和28年頃 坂上から ID 9504-9505
- 昭和28年頃 七夕? ID 9506
- 昭和30年 菊まつり
- 昭和32年 大東京祭パレード
- 昭和33年 明治神宮パレード ID 6338と6340
- 昭和39年以前 ID 8-12
- 昭和41年 縁日 ID 12272と12273
- 昭和42年 ID 6-7
- 2枚の写真
- 昭和44年 三つ叉通り ID 101
- 昭和47年秋~48年春 3丁目から ID 13152-53、ID 13159-60
- 昭和47年秋~48年春 ID13167~13170
- 昭和47年秋~48年春 ID13188~
- 昭和48年 1丁目から ID 8801
- 昭和48年 2丁目 ID 8805~ID 8806
- 昭和48年 3丁目 ID13154-55
- 昭和49年 ダンディー2
- 昭和51年 田原屋など ID 11482
- 昭和54年 毘沙門横丁 ID 74-75, 77-78, 83
- 昭和54年 毘沙門横丁 ID 11832, 11833
- 昭和54年 ID 87
- 昭和54年 ID 88
- 昭和54年 ID 89とID 11866
- 昭和54年 ID 92 八百屋
- 4丁目
- 五十番
- 楽山
- 鳥茶屋
- 尾沢追想録
- 尾沢薬局
- 2度目の事態宣言
- 鳥茶屋本店閉店
- せんべい福屋
- 伊勢藤
- ブルターニュ
- め乃惣
- 和可奈
- 三好野(昔)
- 山本珈琲(昔)
- 近江屋~宮崎
- メイセンヤ
- 神楽坂通り(4丁目南東部)
- 大正の神楽坂通り
- 兵庫横丁
- クランク坂
- 石畳
- 想像図
- 黒塀
- 和可菜
- 歴史
- 大久保通りの拡幅計画
- 喜久川
- 昭和33年 明治神宮パレード ID 6338と6340
- 昭和42年 六さんの途中下車
- 記憶の中の神楽坂2
- 以下は写真中心
- 昭和30年 菊まつり
- 昭和44年 ID 101 道路
- 昭和47年秋~ 3丁目から ID 13152-53、ID 13159-60
- 昭和47年秋~ 坂下 ID13167-13170
- 昭和47年秋~ 坂下 ID13165-66, ID13171
- 昭和47年秋~48年春 ID13188~
- 昭和48年 2丁目 ID 8805~ID 8806
- 昭和49年 ダンディー2
- 昭和51年 田原屋など ID 11482
- 昭和54年 ID 89とID 11866
- 兵庫横丁 平成31年
- 5丁目
- 牛込城の城下町
- 善国寺
- 七福神
- 楽楽散歩と新楽楽散歩
- 大久保通りの拡幅計画
- 大久保通りを越え
- 行元寺
- 山猫
- 柳水亭(昔)
- 寺内の人々
- 街頭テレビ|昭和28年
- 神楽坂アインスタワー
- 高島屋10銭20銭ストア(昔)
- 2度目の事態宣言
- 上村一夫
- ほてやとほていや
- あの頃の神楽坂
- きえたものー柳家金語楼
- こしかたの記|鏑木清方
- 店舗
- とんかつ
- ポール
- ポール以前
- うを匠
- 相馬屋
- 万長(昔)
- 丸屋(昔)
- 岩座とフルーツ店
- 布袋屋(昔)
- セイジョー
- 三角堂と買取り店
- アマリージュ
- 山下漆器店
- 河合陶器店
- マルゲリータ
- 紅谷(昔)
- くるみ
- 美濃屋(昔)
- キッコ
- 山せみ
- 近江屋
- 新泉とISSA
- 五十鈴
- 珍味堂
- 本家鮒忠(昔)
- 村松時計店(昔)
- 田原屋(昔)
- 川鉄(昔)
- 資生堂(昔)
- 以下は写真中心
- 昭和5年 上田屋
- 昭和12年 夜の繁昌
- 昭和20年代 新宿時物語
- 昭和20年代 クランク坂?
- 昭和20年後半 相馬屋 ID 24-27
- 昭和20年後半 同栄信用金庫 ID 9493-9494
- 都電⑬神楽坂 昭和45年 荻原二郎
- 都電⑬神楽坂 昭和45年 加藤嶺夫
- 昭和47年 色町(大正時代の神楽坂通り)
- 昭和47年秋~ 坂下から ID13164
- 昭和47年秋~ 坂下から ID13167-13170
- 昭和47年秋~ 坂下から ID13165-66, ID13171
- 昭和47年秋~ 坂上から ID 13174-
- 昭和47年秋~ 坂上から ID13188~
- 昭和47-49年 6→5丁目 ID 13227
- 昭和51年 田原屋など ID 11482
- 昭和54年 毘沙門横丁 ID 74-75, 77-78, 83
- 昭和54年 ID 11824 神楽坂上
- 昭和54年 ID 11864 鮒忠 五十鈴
- 平成31年 ID 14056 河合や山下が廃業
- 善国寺
- 昭和20年後半 ID 9503
- あの頃の神楽坂
- 昭和44年 正面 ID 8245
- 昭和44年 上階から ID 8271-ID 8272
- 昭和45年 正門 ID 8299-ID 8300
- 昭和50~51年 ID 9909-9911
- 昭和51年 東面 ID 11481
- 昭和54年 毘沙門寄席 ID 11829
- 昭和54年 ちんござん ID 11829
- 藁店
- 昭和28年 ID 7899
- 昭和49年 田口重久
- 昭和59年 田口重久
- 昭和54年 ID 79、80、81、82
- 昭和54年 毘沙門横丁 ID 74-75, 77-78, 83
- 昭和54年 毘沙門横丁 ID 11832, 11833
- 平成8年 ID 7900
- 令和4年 ID 17078-80
- 毘沙門天
- 文化財
- 七福神
- 新規街灯と古い街灯
- ひめ小判守
- 児童遊園
- あれこれ
- 由来
- 街頭テレビ|昭和28年
- 東京10000歩
- 野田宇太郎 昭和45年
- BU・SU
- 川柳
- 毒
- 3D
- 杉本苑子
- 上村一夫
- 毘沙門寄席
- あの頃の神楽坂
- 以下は写真中心
- 明治時代と昭和初期の善國寺
- 大正12年 善国寺
- 昭和20年後半 善国寺 ID 9503
- 昭和41年 縁日 ID 12272 73 75 76
- 昭和41年 縁日 ID 12280と12282
- 昭和44年 正面 ID 8245
- 昭和44年 上階から ID 8271-ID 8272
- 昭和45年 正門 ID 8299-ID 8300
- 昭和50~51年 正面 ID 9909-9911
- 昭和51年 東面 ID 11481
- 昭和54年 毘沙門寄席 ID 11829
- 昭和54年 ちんござん ID 11829
- 昭和54年 歳旦祝祷祈願会
- 平成22年 ID 13351
- 善国寺参道の石畳
- 現代
- 6丁目
- 川喜田屋横丁
- 安養寺
- 魚浅
- 成金横丁
- 船橋屋
- よしや
- 花豊
- コボちゃん像
- キムラヤ
- 新内横丁
- 三光院と養善院の横丁
- かぐらむら
- 神楽坂の大阪寿司
- 大阪寿司は絶滅品種?
- 三沢氏 変化40年(1)
- 変化40年(2)
- 変化40年(3)
- あの頃の神楽坂
- こしかたの記|鏑木清方
- 昔
- いろは
- 新宿の散歩道(火事)
- 牛肉店『いろは』と木村荘平
- 牛込亭
- ヤマニバー
- 求友亭
- 手の字
- 青木堂
- 青木堂2
- 大〆
- 昭和39年 地下鉄と大〆
- 成金横丁と大〆
- カフェトリエスティーノ
- きえたものー貸本、百円ショップ
- 文人
- 金子光晴邸
- 水谷八重子邸
- 田山花袋
- 写真(朝日坂は除く)
- 昭和35年頃 神楽坂上 ID 51
- 昭和45年 加藤嶺夫
- 昭和49年 田口重久
- 昭和47-49年 6→5丁目 ID 13227
- 昭和51年 赤城神社入口 ID 9905-9906
- 昭和51年 かのこ美容室 ID 9907-9908
- 昭和54年 音楽之友社 ID 90, ID 11857-11858
- 昭和54年 ID 91, ID 11861 チキータ
- 昭和54年 乾海苔問屋 ID 11862-11863
- 平成31年 ID 14056 河合や山下が廃業
- 令和4年 ID 17078-80
- 写真(朝日坂)
- 昭和44年 坂中腹 ID 8273~8276
- 昭和45年 坂下 ID 8316
- 昭和48年 坂下から ID 8807-8811
- 昭和48年 坂上から ID 8812
- 昭和48年 坂下から ID 8813-8819
- 昭和48年 ローラースケート ID 467
- 横寺町の由来
- 朝日坂の由来
- 昭和10年頃
- 公衆食堂
- 飯塚酒場
- 芸術倶楽部跡
- 芸術倶楽部館
- 小林アパート
- 十千万堂
- 和解
- 花袋と紅葉(1)
- 紅葉の葬式
- 上田敏
- 一水寮
- 浅田宗伯邸
- 稲垣足穂の家
- アルバム 東京文學散歩
- 飯塚友一郎
- 新宿の散歩道
- 以下は写真中心
- 昭和40年頃 飯塚酒場跡 ID 13610
- 昭和44年 荒井精肉店 ID id8273~8276
- 昭和44年 神楽坂眼科
- 昭和44年 旺文社駐車場
- 昭和45年 牛込中央通り ID 451-453
- 昭和45年 牛込中央通り~朝日坂 ID 455-463
- 昭和45年 朝日坂 ID 8316
- 昭和48年 朝日坂 ID 8807-8811 下から
- 昭和48年 朝日坂 ID 8812 上から
- 昭和48年 朝日坂 ID 8813-8819
- 昭和48年 ローラースケート ID 467
- 昭和48年 朝日坂 ローラー ID 8820-8823, 8826
- 昭和49年 田口重久
- 夜の矢来
- 矢来町
- 矢来屋敷
- 矢来公園
- 奇怪な事件
- 沓掛桜
- 矢来下
- 以下は人物中心
- 英国帰りの漱石
- ライオネル・チャモレー日記
- 広津和郎の生家
- 色川武大邸
- 福島安正邸
- 福島と単騎横断
- ヌエット邸
- ヌエットと鏡花
- 森田草平邸
- 金語楼邸
- 鏑木清方邸
- 絹もすりん
- 文士罷り通る
- 鷲尾雨工
- 直木の美醜(鷲尾)
- 峰竜太
- 以下は写真中心
- 赤城神社の山車 明治末期 ID 156
- 矢来能楽堂 昭和29年以降 ID 9842
- 新潮社 昭和30年後半 ID 121
- 日興銀矢来社宅? 昭和30年 ID 124
- 新潮社 昭和44年 ID 8282
- 牛込中央通り 昭和45年 ID 8
中の丸→旧殿 昭和45年 ID 118- 旧殿
- 牛込中央通り 71番 昭和45年
- 牛込中央通り 77-82番地 昭和45年 ID 107
- 東に矢来公園 昭和45年 ID 115
- 能楽堂 昭和45年 ID 117
- 能楽堂 昭和47年と令和4年 ID 12155など
- 21番地 昭和47年 ID 122
- 早稲田 X 牛込中央 昭和63年 ID 123
- 宮比神社
- 柿の木横町
- 下宮比町交差点
- 寒泉精舎 ID 17975
- 牛込区筑土方面遠望 大正8年頃
- 町会 大正13年 ID 10798
- ロータリーの廃止 昭和28年
- 飯田橋交差点の信号機 昭和28年 ID 13030
- 東京厚生年金病院 昭和30年代後半 ID 6998
- 船河原橋 昭和39年 ID 551
- 消防訓練 昭和41年頃 ID 12317-18
- 東京厚生年金病院 昭和44年頃 ID 14154
- 首都高 目白通り モリサワ 昭和44年 ID 12776-79
- 首都高 昭和51年 ID 476-77, 485, 488, 11460-61, 12187-88
- 飯田橋交差点 昭和54年 ID 12104
- 飯田橋交差点 昭和54年 ID 498-50, 12107-08, 12111
- 赤城
- 赤城神社
- 牛込氏の牛込移住
- 山猫
- 清風亭
- 赤城坂
- 赤城横町
- 石畳(昔)
- 明治の子供
- 以下は文人から
- 金子光晴
- 水上勉
- 稲垣足穂
- 水谷八重子
- 野田宇太郎
- 小林信彦
- 以下は写真中心
- 七五三 入口 ID 388 昭和28年
- 七五三 本殿と参道 ID 6869 昭和26-30年
- 拝殿と鳥居 ID 389など 昭和44年
- 清隆寺 ID 14134 昭和44年
- 鳥居 ID 8298 昭和44年
- 神輿蔵 眺め 境内 ID 14133など 昭和44年
- 北参道から遠景 ID 9899など 昭和50-51年
- 拝殿から昭忠碑 ID 9902など 昭和50-51年
- 拝殿と狛犬 平成29年
- 駐車場の眺望 ID 14051 平成31年
- 一の鳥居 ID 13302 令和元年
- 駐車場の眺望 ID 13303-06 令和元年
- 駐車場の眺望 ID 17063-66 令和4年
- 拝殿と鳥居 ID 17581-82 令和4年
- 道路通称名
- 牛込駅リターンズ
- 上村一夫と神楽坂
- 山の手と下町の同居
- 再開発と神楽坂
- 鳥茶屋
- 2度目の事態宣言
- ほてやとほていや
- 昭和30年代半ば
- 神楽坂上
- 逆転式一方通行
- 看板(写真)
- 失われた新宿区
- 神楽坂の中心
- 喜久川
- 飯田橋行き
- 毘沙門さま
- 神楽坂3~4丁目
- 街灯(戦前)
- 逆転式の延長
- 三菱銀行神楽坂支店
- 菊まつり
- 大東京祭の花自動車
- 昭和44年 善国寺 上階から ID 8271-ID 8272
- 神楽坂落語まつり
- 善国寺参道の石畳
- きらく会館
- 昭和20年代 ひょうたん
- 昭和20年代 祭風景
- 昭和44年 若宮神社 ID 14124~25
- 牛込見附と桜の木
- 青木堂
- 青木堂2
- 渡邊坂の廃道
- 下宮比町(飯田橋)交差点
- 四谷・市ヶ谷の見附撤却
- 明治26年 大久保通りの拡幅
- 明治26年 見番横丁の開設
- 松平定安邸
- 明治28年 牛込駅通路
- 明治26年 新見附の新設
- あまざけや
- 明治38年 路面電車の新見附
- 新見附の前史
- 神楽坂通りの迂回
- 踏切計画
- 飯田橋の五叉路
- 鉄道の複線化
- 神楽坂下の五叉路案
- 紀の善の閉店
- ラムラの「せせらぎ」
- 牛込電話局
- 出羽様下 再考
- 逆転式の補遺
- 牛肉店『いろは』と木村荘平
- 足立屋と岡田常次郎氏、東京シティ信用金庫
- 万平の柳
- 以下は写真中心
- 中の丸
- 日興銀矢来社宅?|昭和30年
- 牛込柳町|昭和51年
- 新丸ノ内ビルヂング
- 飯田橋駅東口 昭和54年
16/3/13⇒20/8/6⇒21/6/16⇒21/9/23