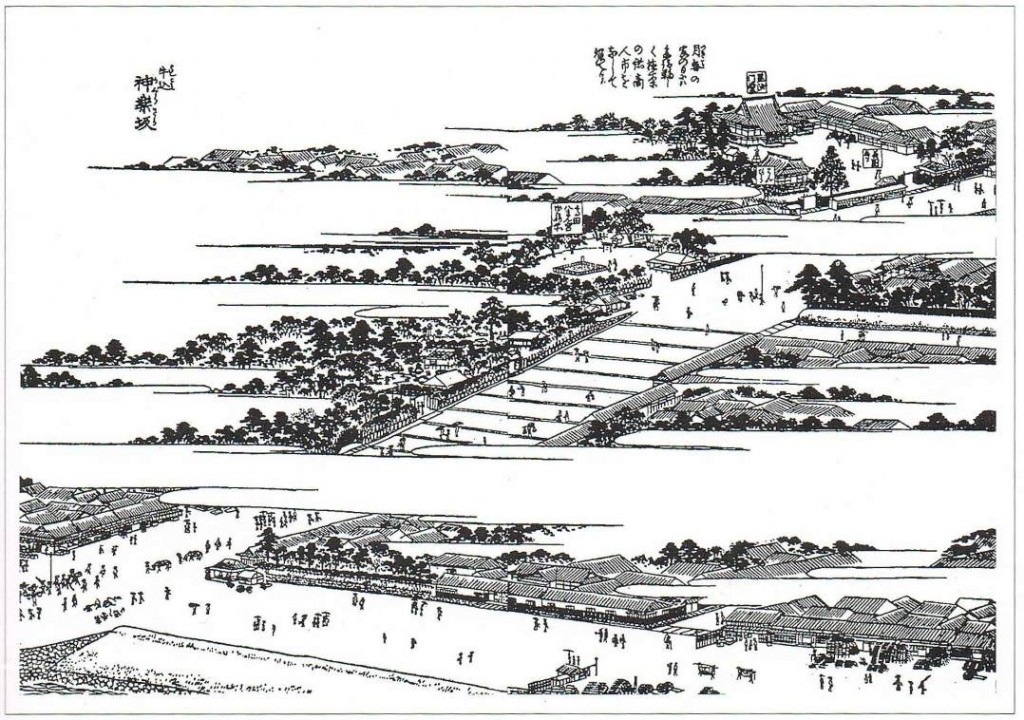「牡丹屋敷」は明治20年の地図でも出てきますが、江戸時代にすでに三分割し、この屋敷自体はまったくありません。この典雅な名前「牡丹屋敷」のいわれですが、東京市企画局都市計画課編「東京市町名沿革史 上巻」(昭和13年)では……
| 亨保14年11月岡本某この地を借り牡丹を植えこれを将軍吉宗に呈す、よって牡丹屋敷の称あり |
亨保14年11月は1729年12月から1730年1月までです。
また新宿歴史博物館の『新修 新宿区町名誌』でこう書いています。
 牡丹 牛込牡丹屋敷 豊島郡野方領牛込村内にあったが、武家屋敷になった。八代将軍吉宗の時代、岡本彦右衛門が吉宗に供して紀伊国(現和歌山県)から出てきた際、武士に取りたてようと言われたが、町屋が良いと答えこの町を拝領した。屋敷内に牡丹を作り献上したため牡丹屋敷と唱えた。その後上り屋敷となり、宝暦12年(1762)12月24曰に地所を三分割し、そのうち一ケ所が拝領町屋となった(町方書上) |
拝領町屋 江戸で下級の幕臣に与えられた拝領屋敷内に長屋を建て、町方の者を居住、賃貸料を取ることを認められたもの。
江戸幕府が編集した江戸の地誌「御府内備考」(大日本地誌大系。第3巻。雄山閣。1931年)では
| 牡丹屋舗 當町之儀往古は武州豊島郡野方領牛込村の内に有之其御武家方御屋舗に相成候處 有德院樣御代岡本彦右衛門と申者紀州ゟ御供仕武家に御取立之蒙臺命候得共御免相願町家望のよし奉申上候に付當町拝領仕致住居候而 御傳法の熱湯散と申藥相弘大鷲壹羽御預被爲遊屋敷内にて牡丹花を作御て致献上候よし依之町名を牡丹屋舗と唱家號牡丹屋彦右衛門と申寵在侯處其後賓暦年中故有て蒙御咎を家財被召上上地上り屋舗に相成候趣申傳候其後右上り屋舗寳曆十二十年十二月廿四日町御奉行土屋越前守様御掛町年寄樽屋彥右衛門殿調之上三ツ割屋鋪に相成表間口拾貳間三尺西奥行貳拾壹間貳尺東奧行貳拾式間裏幅拾壹間壹尺五寸此坪數貳百五拾七坪餘大奧女中方御年寄飛鳥井樣表間口六間貳尺五寸西奥行式拾式間東奥行式拾三間九寸裏幅六間貳尺五寸此坪數百四拾四坪餘御年寄花園様表間口同八間三尺… |
往古 遠い過去。大昔
有徳院 江戸幕府第8代将軍の徳川吉宗のこと。有徳院は戒名。
ゟ より。平仮名「よ」と平仮名「り」を組み合わせた平仮名。合略仮名。
台命 将軍や皇族などの命令。
拝領 目上の人、身分の高い人から物をいただくこと。
伝法 でんぽう。師が弟子に仏法を授け伝えること。秘伝
大鷲 おおわし。タカ目タカ科の猛鳥。
家號 やごう。商店の呼び名。店名。
故 ゆえ。事の起こるわけ。理由。原因。
江戸時代の『御府内風土記』編纂で、江戸の町の由来について町名主に提出させた書類「町方書上」(新宿近世文書研究会、1996年)でも中身は同じです。
| 當町之義、往古者武州豊嶋郡野方領牛込村之内二有之、其後武家方御屋鋪二相成候處、 有徳院様御代、岡本彦右衛門与申者紀州ゟ御供仕、武家二御取立之蒙 台命候得共御免相願、町家望之由奉申上候二付、當町拝領仕致住居候而 御傅法熱湯散卜申薬相弘メ、大鷲壱羽御預ヶ被為遊、屋敷内二而牡丹花ヲ作候而献上致候由、依之町名ヲ牡丹屋舗卜唱、屋号ヲ牡丹屋彦右衛門与申罷在候処其後、宝暦年中故有而蒙御咎ヲ、家財被召上、地面上り屋敷二相成候趣申傅候、其後右上り屋鋪… |
岡本彦右衛門(屋号は牡丹屋彦右衛門)は家伝の薬「熱湯散」をつくっていましたが、宝暦11年(1761)、岡本彦右衛門が故あって咎めをこうむり、このため屋敷を没収、屋敷は上り屋敷になりました。翌12年、地所は3つにわけられ、大奥女中方御年寄飛鳥井、同花園、御表使三坂の3人の女性が拝領することになりました。文政10年(1827)の家数は16、うち家主10・地借1・店借5(文政町方書上)。
大奥女中方御年寄 江戸幕府大奥の職名。将軍や御台所(将軍の正室)への謁見が許可された女中。
御表使 おもてづかい。江戸幕府大奥の職名。御台所の買物や代参に随行する上級女中。
明治2年(1869)に玉咲町と改称、明治4年には神楽町1丁目と改称、明治26年になってから神楽坂1丁目になります。
なお他の牡丹屋敷と区別するため新宿歴史博物館は牛込牡丹屋敷と書いています。現在はスターバックスコーヒーなどが林立しています。